-
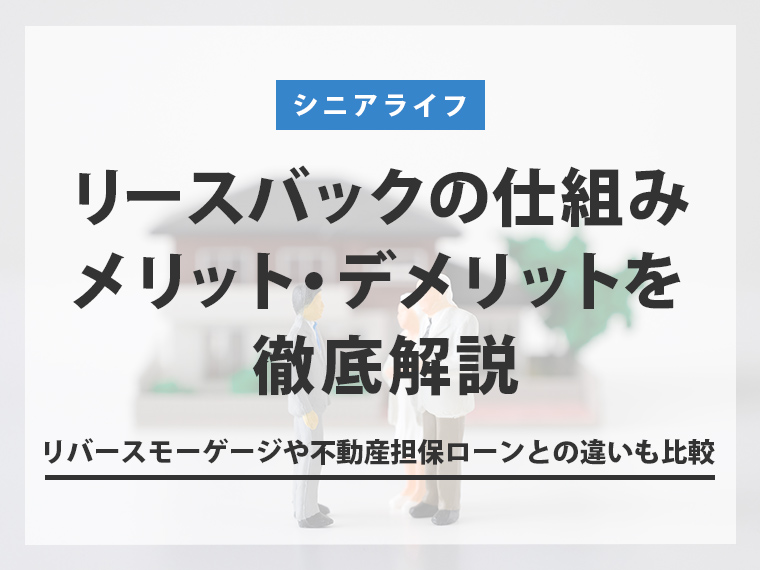
リースバックの仕組み・メリット・デメリットを徹底解説|リバースモーゲージや不動産担保ローンとの違いも比較
リースバックとは、自宅を売却して現金化しながら住み続けられる仕組みです。 この記事では、リースバックのメリット・デメリットや契約時の注意点を詳しく解説し、リバースモーゲージや不動産担保ローンとの違いや比較のポイントも紹介します。 所有している不動産を活用した資金調達方法を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
-

借地権の相続ガイド|手続き・税金・注意点をわかりやすく解説
借地権は財産権の一種であり、土地の所有権と同様に相続の対象になります。 しかし、土地の所有権を相続する場合と比べると、借地権の相続には複雑な法的・実務的な注意点があります。 契約条件や地主との関係によって対応が変わるため、事前に理解しておくことが重要です。 本記事では、借地権を相続する際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
-

認知症の代表的な4つの種類とは? 症状・進行・早期発見の大切さを解説
「同じことを何度も聞く」「最近の出来事をすぐ忘れてしまう」――そんな変化に気づいたとき、心配になるのが認知症です。 日本では高齢化が進み、認知症は介護が必要になる主な原因のひとつとなっています。 認知症には複数の種類がありますが、代表的な4タイプで全体の約92%を占めています。 本記事では、認知症の代表的な4つの種類とその症状、進行の特徴、そして早期発見の重要性についてわかりやすく解説します。
-
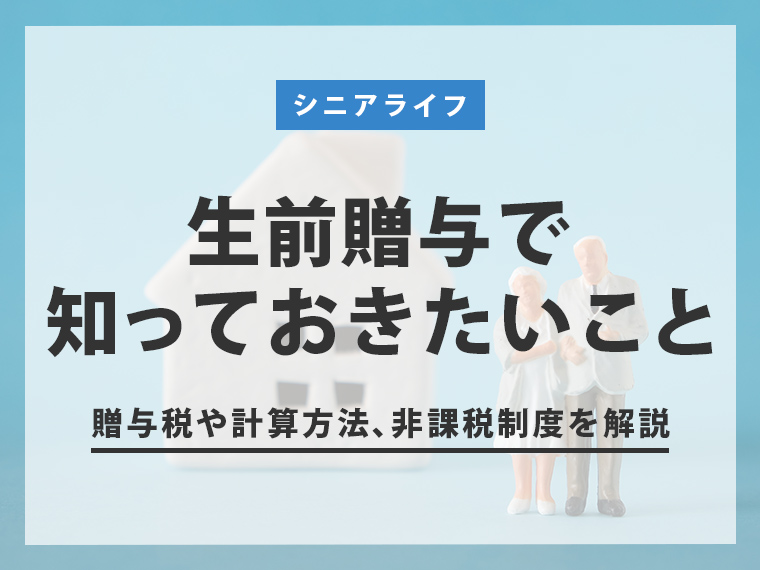
生前贈与で知っておきたいこと|贈与税の税率や計算方法、非課税制度をわかりやすく解説
家族や大切な人に財産を渡す方法として注目されているのが「生前贈与」です。相続税の節税や相続トラブルの回避に役立つ一方で、贈与税のルールや計算方法を理解しておかないと、思わぬ税負担が生じる可能性もあります。 本記事では、贈与税の基本的な仕組みや税率・計算方法に加えて、非課税で活用できる制度についてもわかりやすく解説します。
-
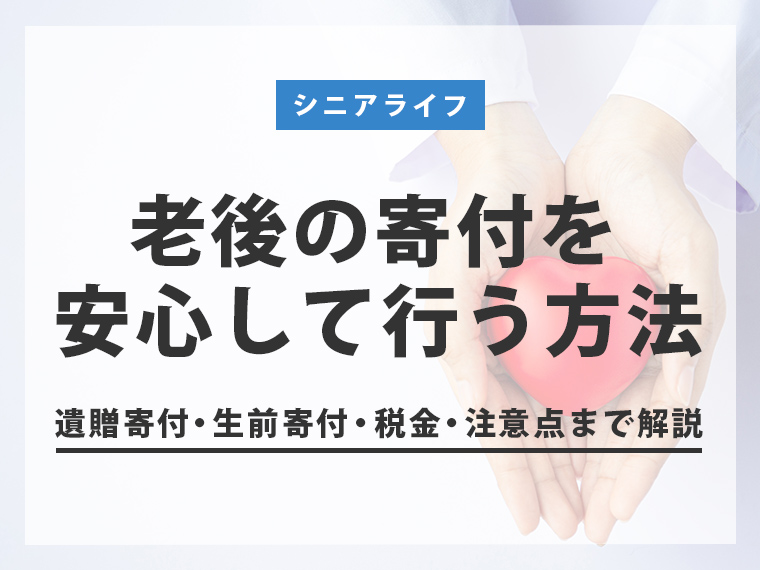
老後の寄付を安心して行う方法|遺贈寄付・生前寄付・税金・注意点まで解説
老後の暮らしを見据えて、自分の財産の一部を行政や慈善団体に寄付して社会貢献したいと考える方もいるのではないでしょうか。 本記事では、生前寄付や遺贈寄付の方法や注意点のほか、相続税の非課税制度や寄付金控除などの税制上のメリットも紹介し、安心して寄付を実行できるポイントを解説します。
-
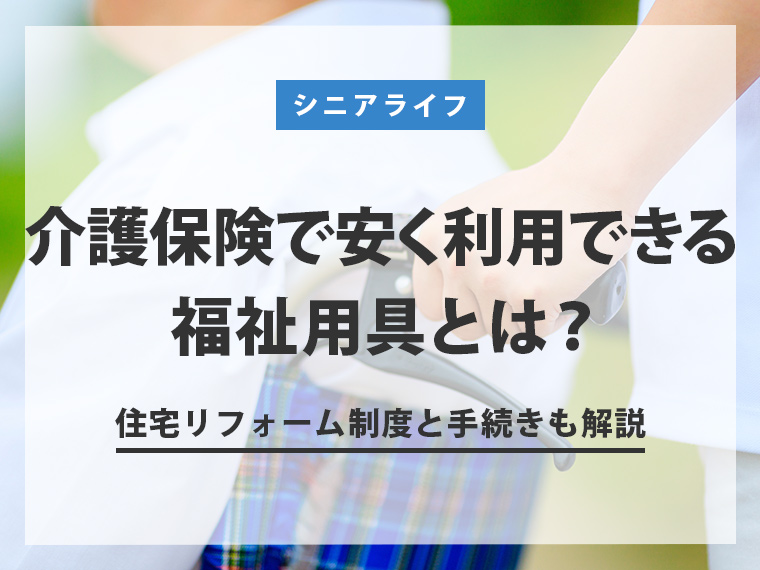
介護保険で安く利用できる福祉用具とは? 住宅リフォーム制度と手続きも解説
福祉用具とは、高齢者や障がいのある方が日常生活を自立して送れるよう支援するための道具や機器のことです。 介護する方にとっても、負担を軽減できる大切な役割を担っています。 この記事では、代表的な福祉用具の種類や、介護保険を利用して安価に利用できる福祉用具、さらに介護保険を活用したバリアフリー住宅へのリフォームについても解説します。
-
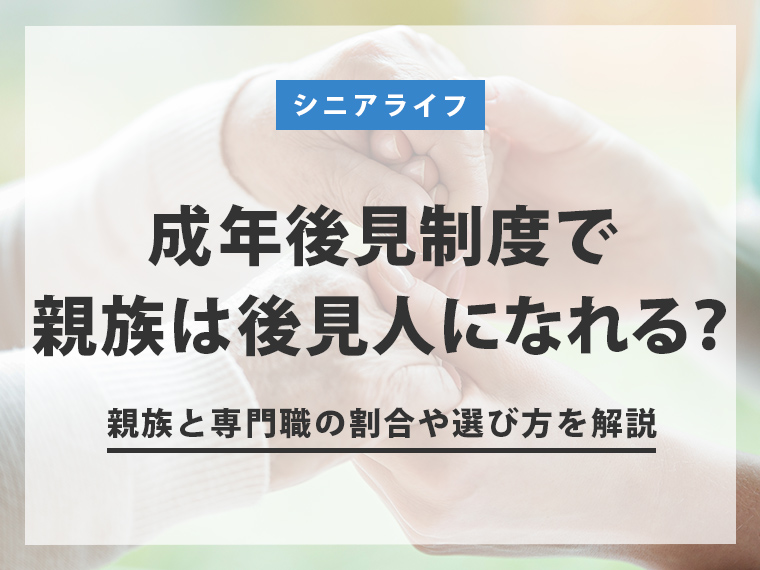
成年後見制度で親族は後見人になれる?親族と専門職の割合や選び方を解説
例えば、親が認知症になり「成年後見制度を利用したい」と考える時、専門家に依頼すると費用がかかるため、できれば息子や娘である自分が後見人になれないかと考える方は多いでしょう。 しかし、成年後見人は家庭裁判所が選任する仕組みであり、必ずしも家族が選ばれるとは限りません。 家族を後見人候補として申立てをしても弁護士や司法書士などの専門職が任命されることもあります。 本記事では、家族や親族が成年後見人になれるケースと、そのポイントについて分かりやすく解説します。
-
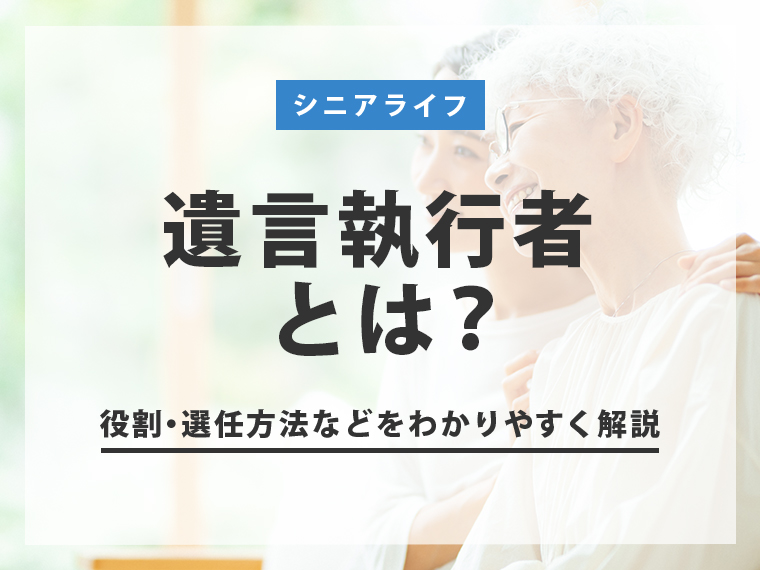
遺言執行者とは?必要なケース・役割・選任方法をわかりやすく解説
遺言執行者とは、故人が残した遺言の内容を実現するために選任された人です。どのような場合に必要なのか、そしてその役割はどういったものなのかをわかりやすく解説します。
-
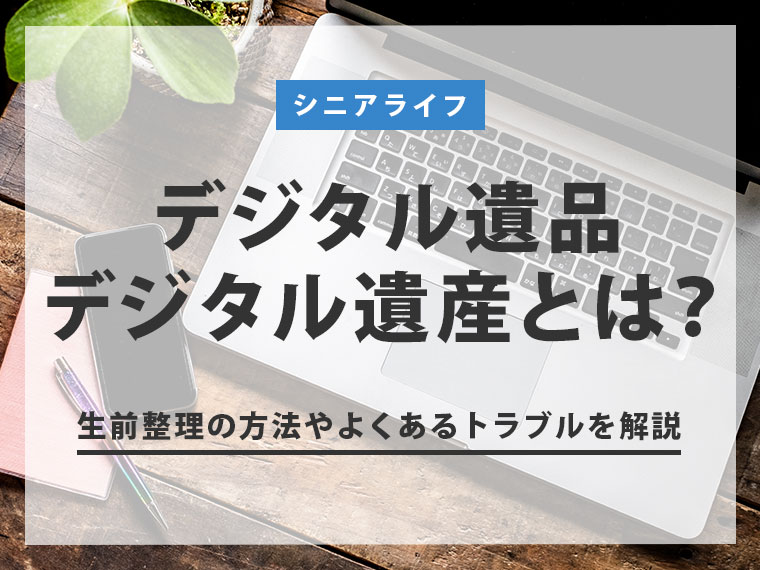
デジタル遺品・デジタル遺産とは?生前整理の方法やよくあるトラブルを解説
今やスマートフォンやパソコンなどデジタル機器は、シニア世代にとっても生活に欠かせない存在です。 もし所有者が亡くなった場合、これらの機器の中にあるデータ(デジタル遺品・デジタル遺産)はどうなるのでしょうか? 本記事では、デジタル遺品・デジタル遺産の概要とトラブル事例、さらに生前整理のポイントをわかりやすく解説します。
-
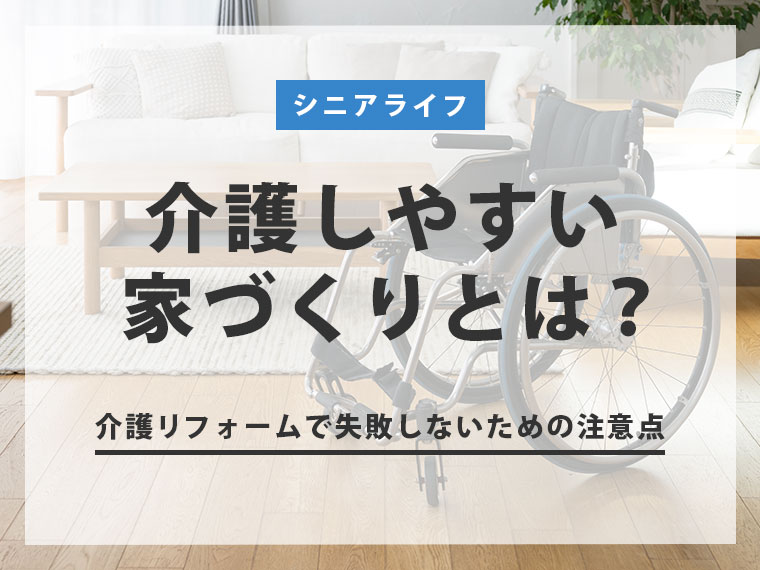
介護しやすい家づくりとは?介護リフォームで失敗しないための注意点
高齢になり身体機能が低下すると、自宅での暮らしにさまざまな不便が生じるようになります。 介護が必要になったご本人が安心して暮らせるだけでなく、介護をする家族にとっても負担が少ない家とは、どのような住まいでしょうか。 本記事では、「そろそろ介護が始まりそう」と感じたときや、すでに介護が始まっているご家族向けに、介護しやすい住まいづくりのポイントや、リフォーム時に気をつけたい点をわかりやすく解説します。
-
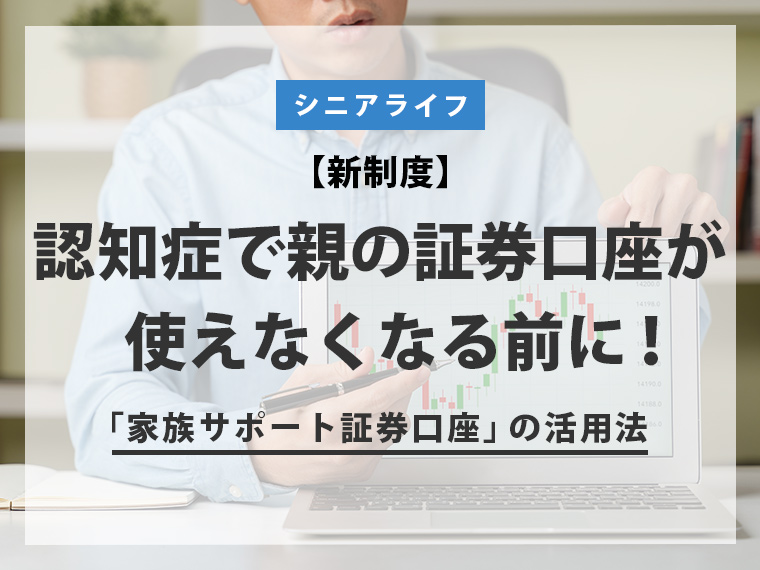
【新制度】認知症で親の証券口座が使えなくなる前に!「家族サポート証券口座」の活用法
家族が認知症を発症すると、判断能力が低下したと見なされ、法律上の契約行為ができなくなります。 その結果、銀行口座が凍結されるだけでなく、証券口座も同様に、株式や投資信託の購入・売却ができなくなってしまいます。 こうした「資産が動かせないリスク」に備える新たな制度として、日本証券業協会は2025年2月、「家族サポート証券口座」を創設しました。 本記事では、新制度の概要や活用のポイントをわかりやすく解説します。
-

親の介護費用が足りないときどうする?困ったときの対処方法を解説
介護保険制度の導入により、介護が必要になっても安心して生活ができる環境が整いました。 しかし、実際に介護サービスを利用しようとしたときに「お金が足りない」「利用中に資金が不足してしまった」といった経済的な不安を感じる方も少なくありません。 この記事では、介護サービスの費用が不足したときに取るべき具体的な対処法について、わかりやすく解説します。
-
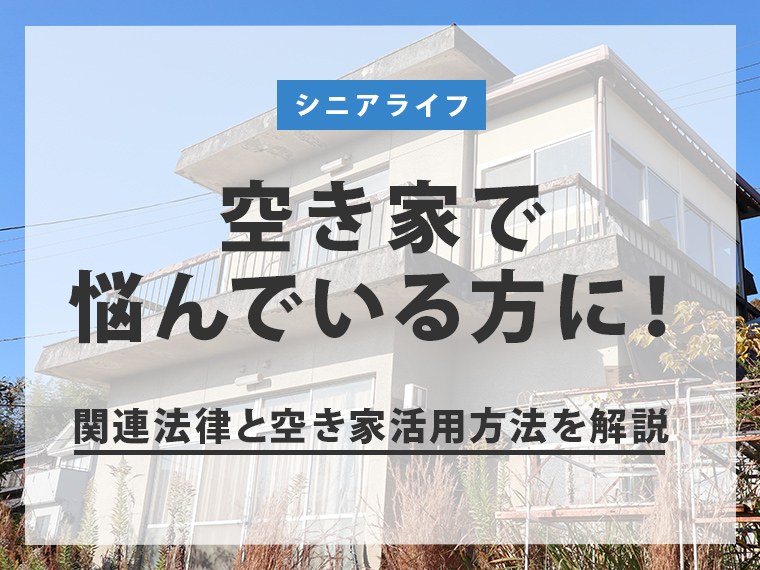
空き家で悩んでいる方に! 関連法律と空き家活用方法を解説
「空き家の管理が大変」「使い道がない」「売却や活用方法がわからない」など、空き家を所有している方の多くが、このような悩みを抱えています。 しかし、空き家を放置したままにしておくと、近隣への悪影響や法的なトラブルにつながるリスクがあることをご存じでしょうか? この記事では、空き家が抱える代表的な問題点や、政府が打ち出した関連法律、具体的な解決策についてわかりやすく解説します。
-
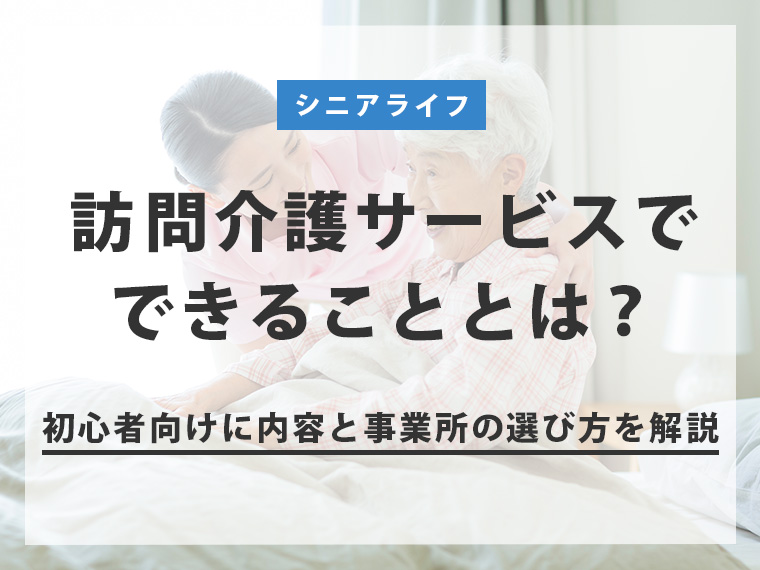
訪問介護サービスでできることとは?初心者向けに内容と事業所の選び方を解説
訪問介護サービスは、介護が必要な方が住み慣れた自宅で安心して生活を送れるように、介護スタッフが自宅を訪問して日常生活のサポートを行うサービスです。 この記事では、訪問介護の具体的なサービス内容や信頼できる訪問介護事業所の選び方について、わかりやすく解説します。
-
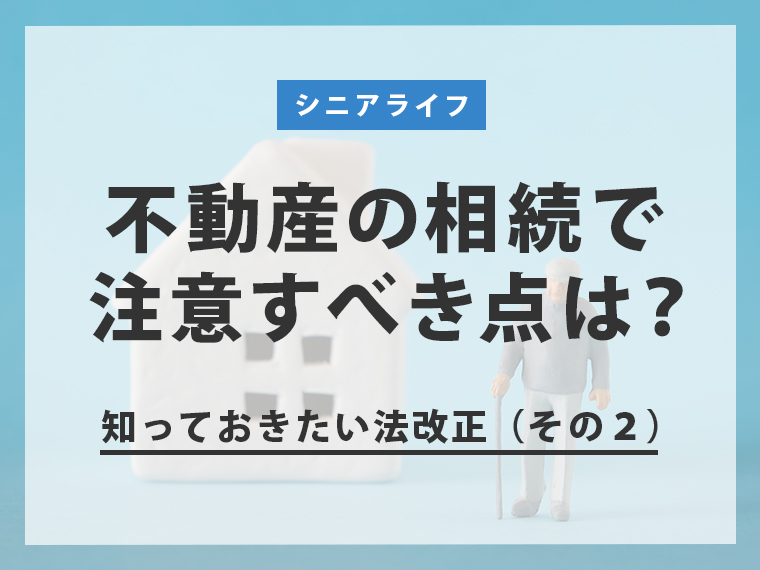
不動産の相続で注意すべき点は?知っておきたい法改正(その2)
近年、所有者不明土地の解消を目的として、いくつかの新しいルールが設けられています。 財産管理制度や共有制度、遺産分割、相隣関係といった分野でも見直しが行われており、今後の不動産の管理や相続に関わる方々にとって重要な改正となっています。 本記事では、これらの法改正の見直しについて説明します。
-

【初心者向け】デイサービスの選び方|種類・費用・選ぶ際のポイントを解説
デイサービス(通所介護)は、高齢者が自宅での生活を続けながら、日中に入浴・食事・リハビリ・レクリエーションなどを受けられる介護サービスです。 リハビリ特化型や認知症対応型、趣味特化型などいくつかの種類があるため、目的に応じた選び方が重要になります。 本記事では、各デイサービスの特徴や費用の目安、失敗しない施設選びのポイントをわかりやすく解説します。
-
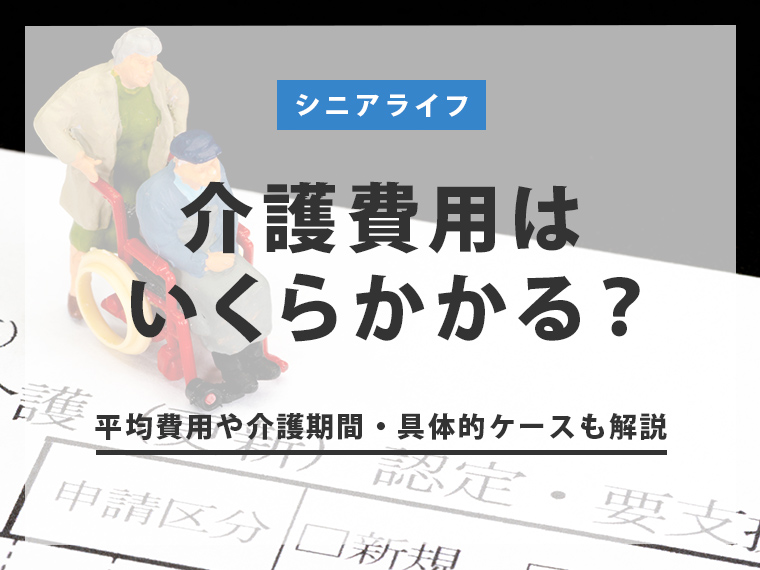
介護費用はいくらかかる?平均費用や介護期間・具体的ケースも解説
老後資金を計画するうえで、介護費用がいくらかかりそうなのか知っておくことは大切です。 本記事では介護費用の平均データと、具体的なケースを挙げて解説していきます。
-
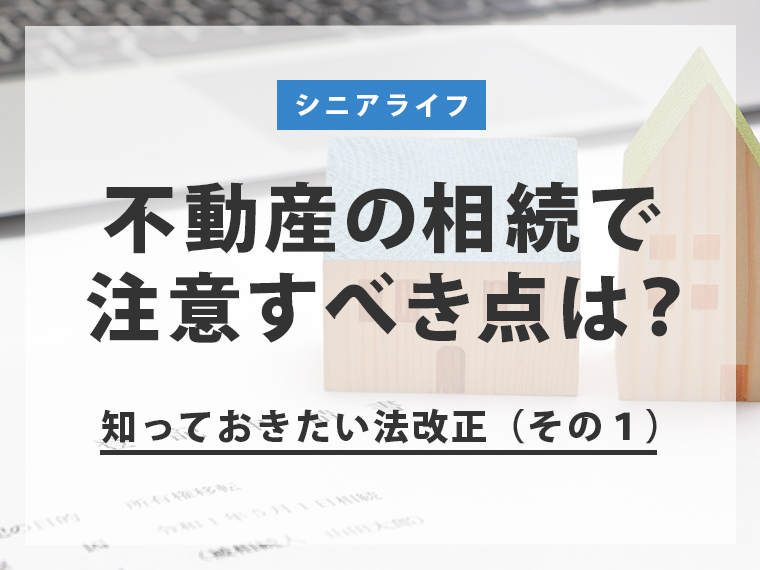
不動産の相続で注意すべき点は?知っておきたい法改正(その1)
近年、日本では「所有者不明土地」問題の解消を目的として、不動産に関する新たなルールが施行されました。 さらに、今後も追加の法改正が予定されており、不動産所有者や相続人にとって重要なポイントとなります。 本記事では、日常生活や相続時に知っておくべき主な変更点について、わかりやすく解説します。
-

一人暮らしの自分が死んだら、ペットはどうなる?行っておくべき生前対策
ペットは私たちに癒しと喜びを与えてくれる大切な存在です。 万が一飼い主が先立ってしまった場合に備え、飼い主ができる対策やペットの将来を守る方法について詳しく解説していきます。
-
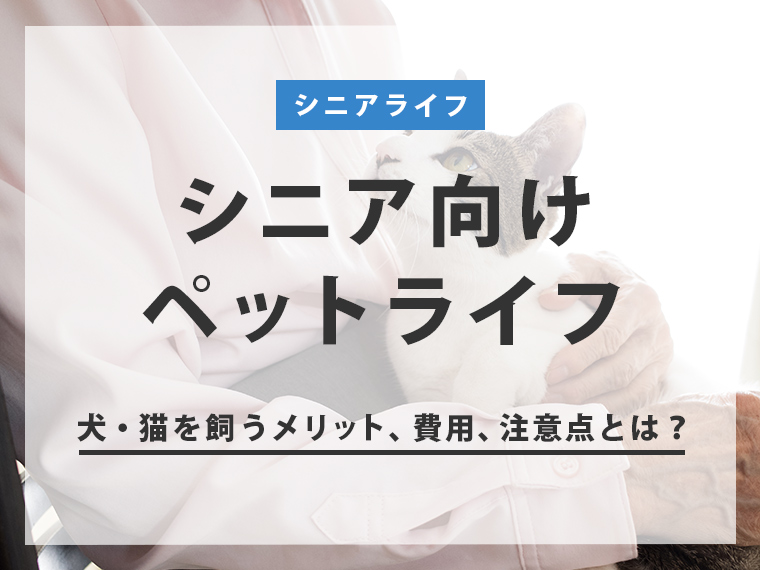
シニア向けペットライフ|犬・猫を飼うメリット、費用、注意点とは?
高齢者にとって犬や猫などのペットは、心を癒し、生活に張り合いをもたらしてくれる大切な存在です。 愛らしいしぐさに心が和み、お世話をすることで生活リズムも整うなど、多くのメリットがあります。 本記事では、シニアが犬や猫を飼う際の費用、メリット、そして注意点について詳しく解説します。
-
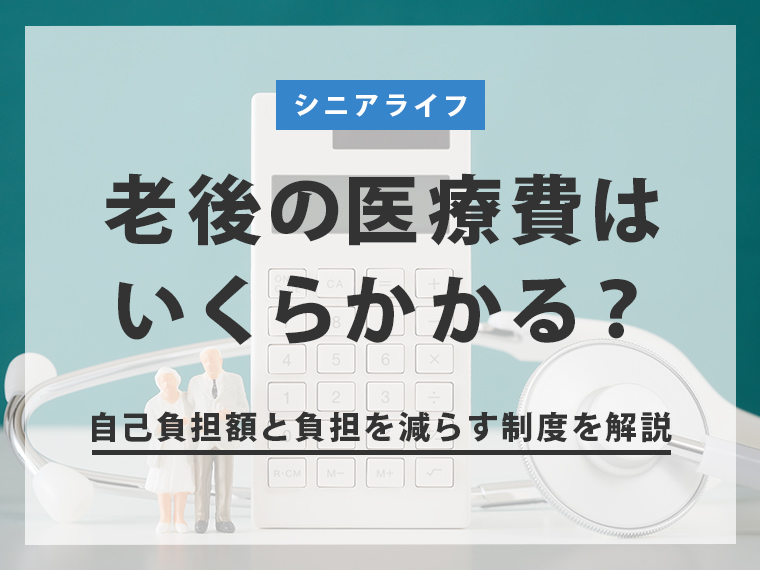
老後の医療費はいくらかかる?自己負担額と負担を減らす制度を解説
老後の資金計画を立てる際、医療費がどれくらいかかるのか、心配な方も多いのではないでしょうか。今は健康でも、将来自分の体がどうなってしまうのか予測がつきません。本記事では、政府のデータをもとに、老後の医療費の目安と、高額な医療費負担を軽減するための制度について解説します。
-
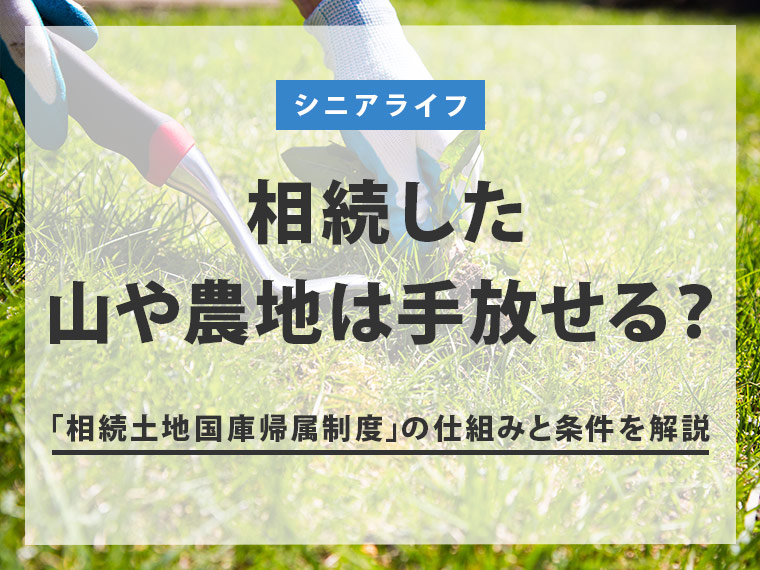
相続した山や農地は手放せる?「相続土地国庫帰属制度」の仕組みと条件を解説
相続した土地が市街地の宅地なら、自分で住んだり売却や活用したりすることも容易ですが、山林や農地、地方の実家や別荘などは「使い道がない」「売るのも難しい」と悩む方も少なくありません。 そんな時に検討したいのが「相続土地国庫帰属制度」です。 本記事では、この制度の概要や利用条件をわかりやすく解説します。
-
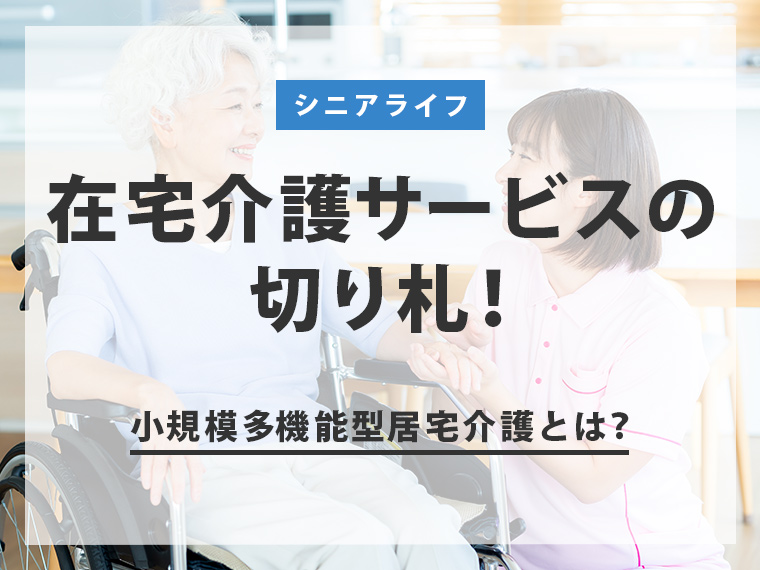
在宅介護サービスの切り札!小規模多機能型居宅介護とは?
在宅での介護保険サービスには、「通い」・「訪問」・「宿泊」の3種類がありますが、小規模多機能型居宅介護は、これらを一つの事業所で受けることができる便利なサービスです。 本記事では、小規模多機能型居宅介護の特徴やメリットについて解説します。
-
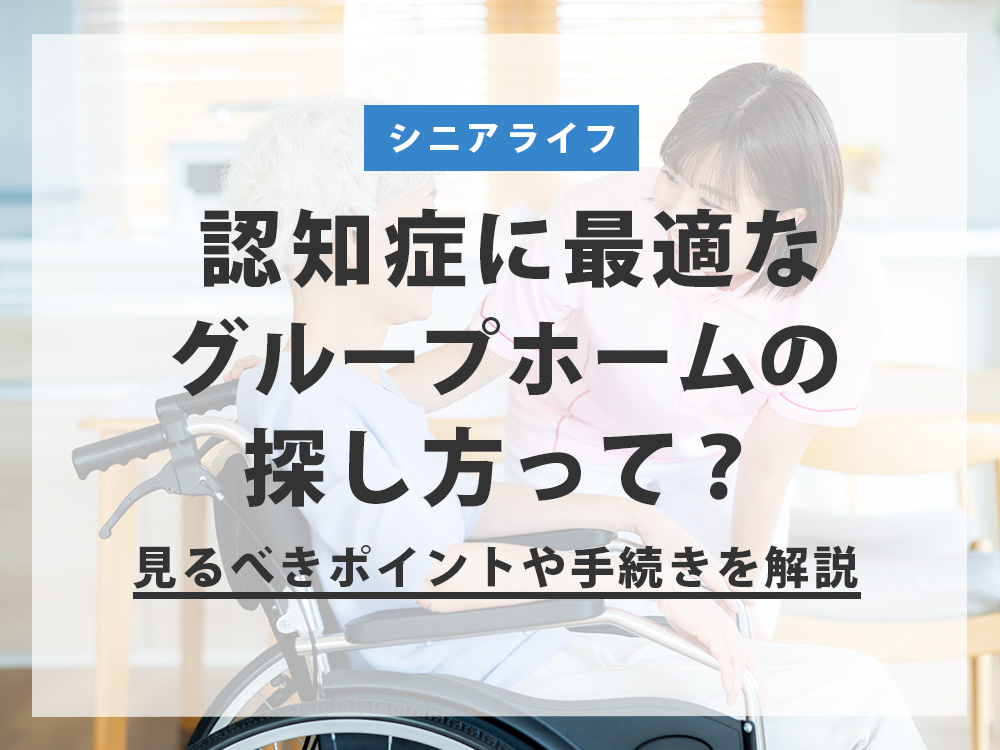
認知症の方に最適なグループホームの失敗しない探し方って?見るべきポイントや手続きを解説
介護施設にはさまざまな種類がありますが、グループホームは「認知症対応型共同生活介護」という正式名称のとおり、認知症ケアに特化した、認知症の方たちが共同で生活する施設です。 本記事では、グループホームの特徴や探し方、見学時のポイントから入居までの流れを解説します。
-
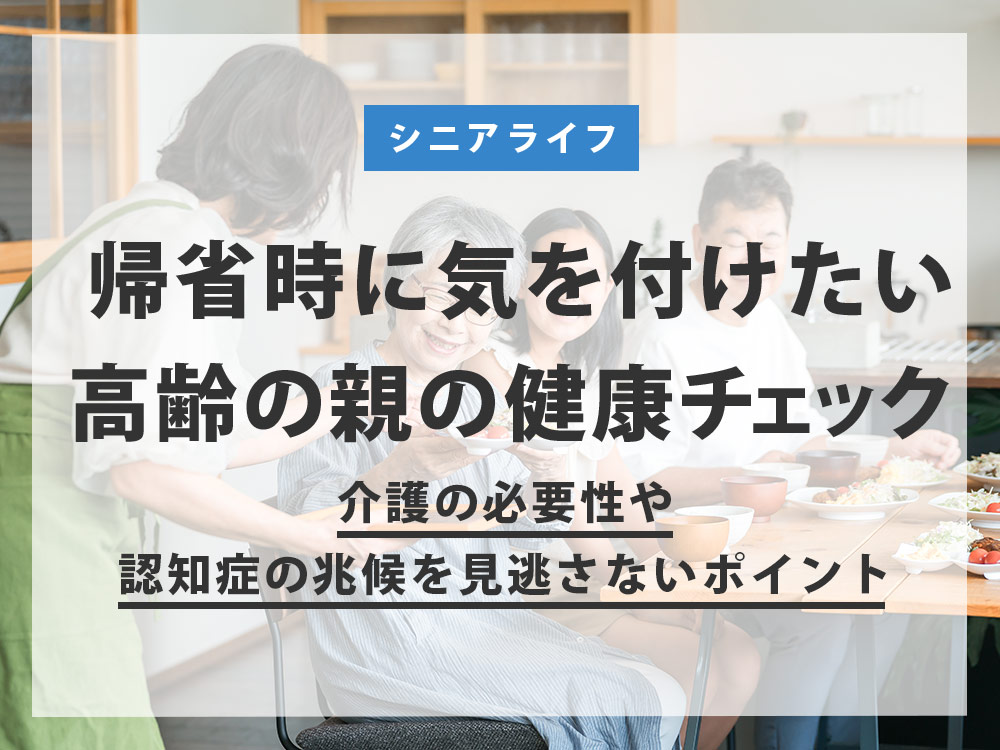
帰省時に気を付けたい高齢の親の健康チェック|介護の必要性や認知症の兆候を見逃さないポイント
高齢の親と離れて暮らしていると、体調の変化や認知症の兆候が出ていないか気になるものです。普段の電話や連絡では気づきにくい変化も、実際に会うことで見えてくることがあります。この記事では、帰省した時に確認したいポイントを「介護サービスが必要かどうか」「認知症の疑いがないか」の二つの視点で解説します。
-
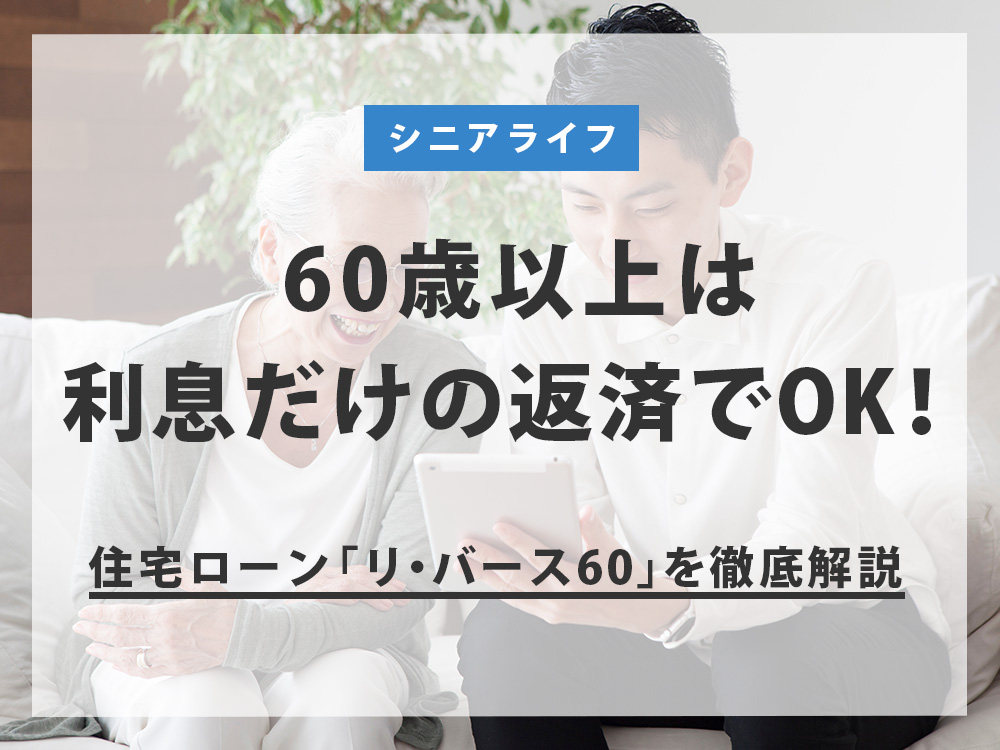
60歳以上は利息だけの返済でOK!住宅ローン「リ・バース60」を徹底解説
リ・バース60は、住宅金融支援機構と提携している金融機関が提供する、60歳以上の方を対象とした住宅ローンです。 このローンでは、毎月の返済が利息のみで済むため、老後の返済負担を大幅に軽減できます。 老後の資金確保の手段として一般的な「リバースモーゲージ」や「リースバック」もありますが、それぞれの違いも詳しく解説します。
-
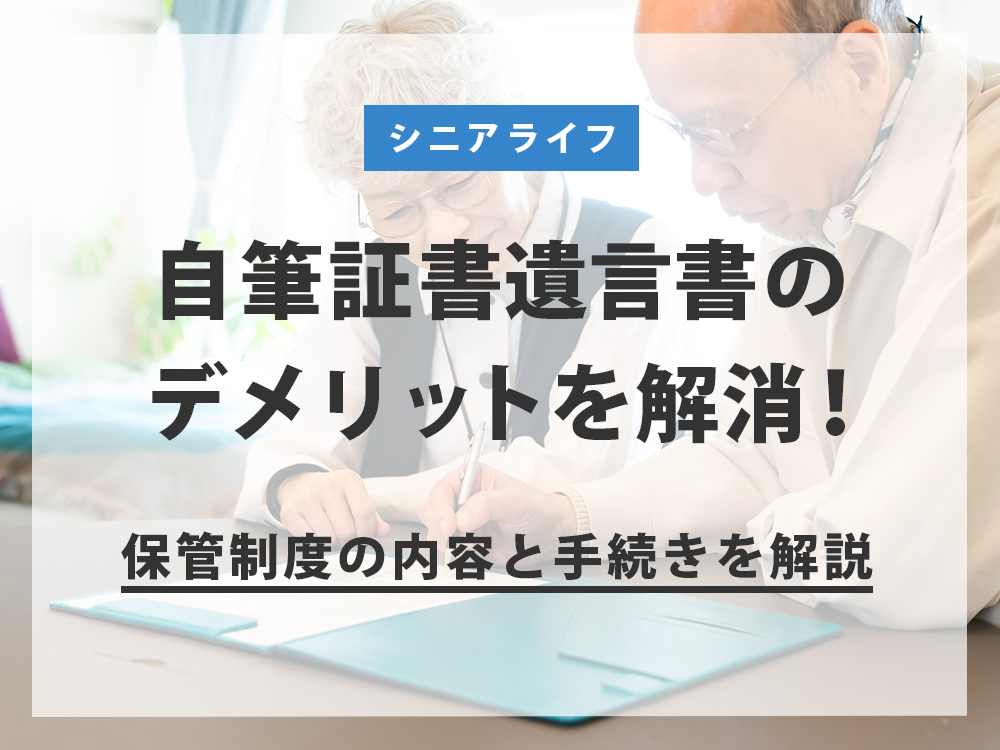
自筆証書遺言書のデメリットを解消!自筆証書遺言保管制度の内容と手続きを解説
自筆証書遺言保管制度は、2020年7月から開始された制度で、自筆証書遺言で作成された遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらえるサービスです。 この制度では、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、遺言者が亡くなった後に相続人などに遺言書の存在を通知してもらうこともできます。 本記事では、自筆証書遺言保管制度の内容や手続き方法について詳しく解説します。
-
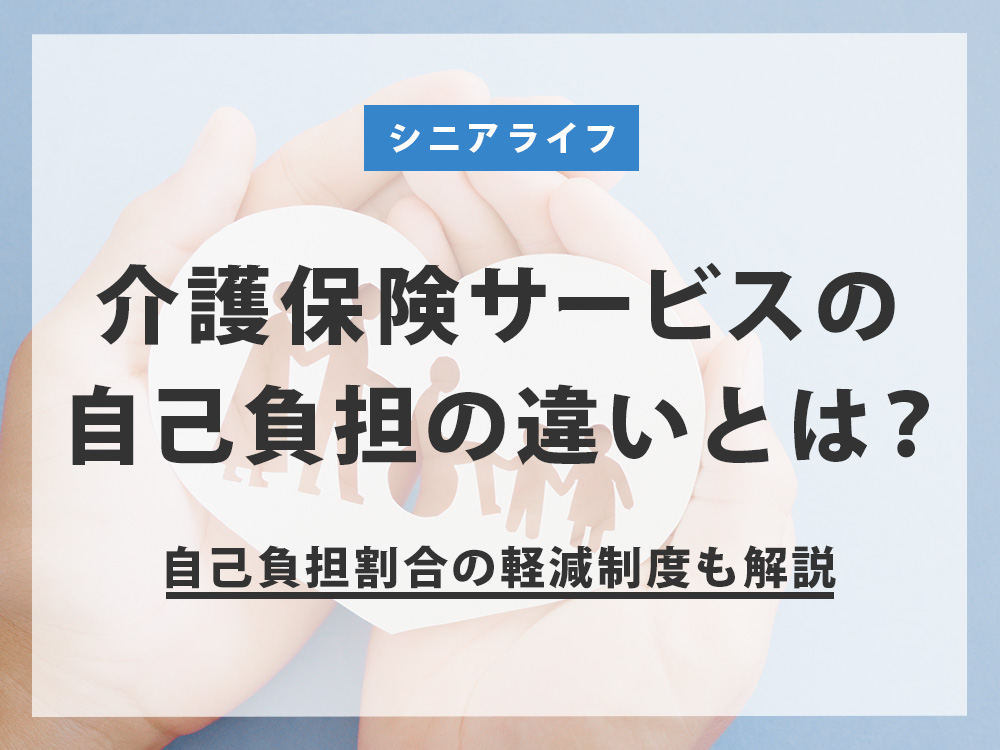
介護保険サービスの自己負担割合(1~3割)の違いとは?自己負担額の軽減制度も解説
介護保険サービスを利用すると、1~3割の自己負担額が発生します。介護保険の自己負担割合は、どのようにして決まるのでしょうか。 本記事では、介護保険サービスの自己負担割合の決め方や、要介護度ごとの支給限度額(利用限度額)、そして自己負担額を軽減する制度について解説します。
-
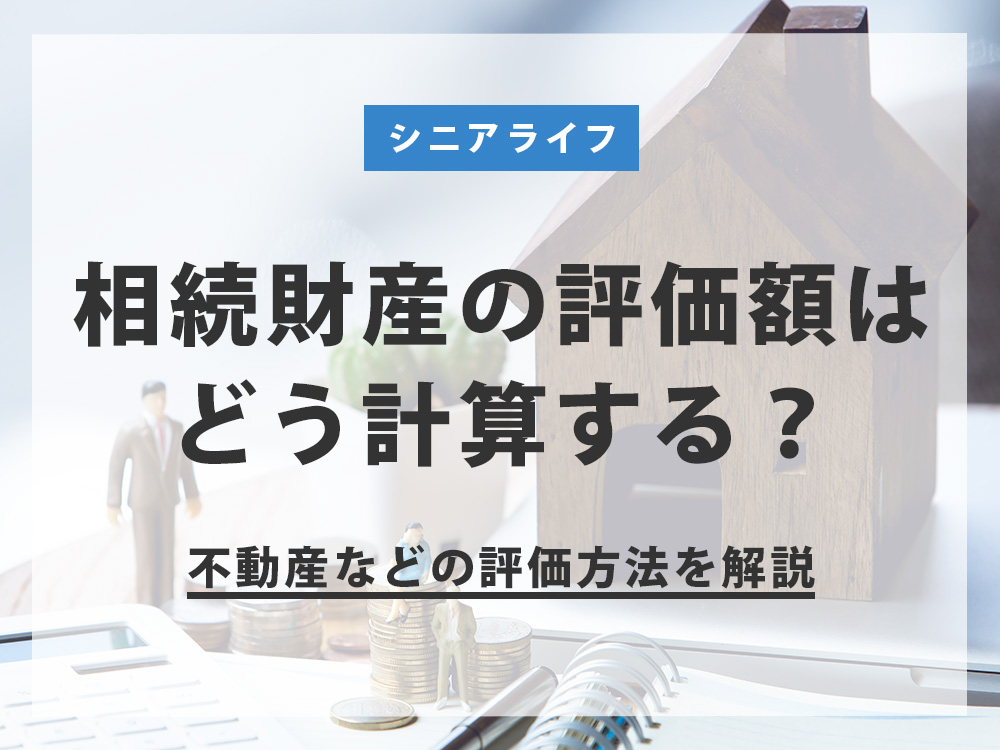
相続財産の評価額はどう計算する?不動産・株式・生命保険などの評価方法を解説
相続財産を分割したり相続税を計算する際には、相続財産を正確に評価することが重要です。 本記事では、現金・預貯金をはじめ、不動産、株式、生命保険など、一般的な相続財産の評価方法について解説します。
-
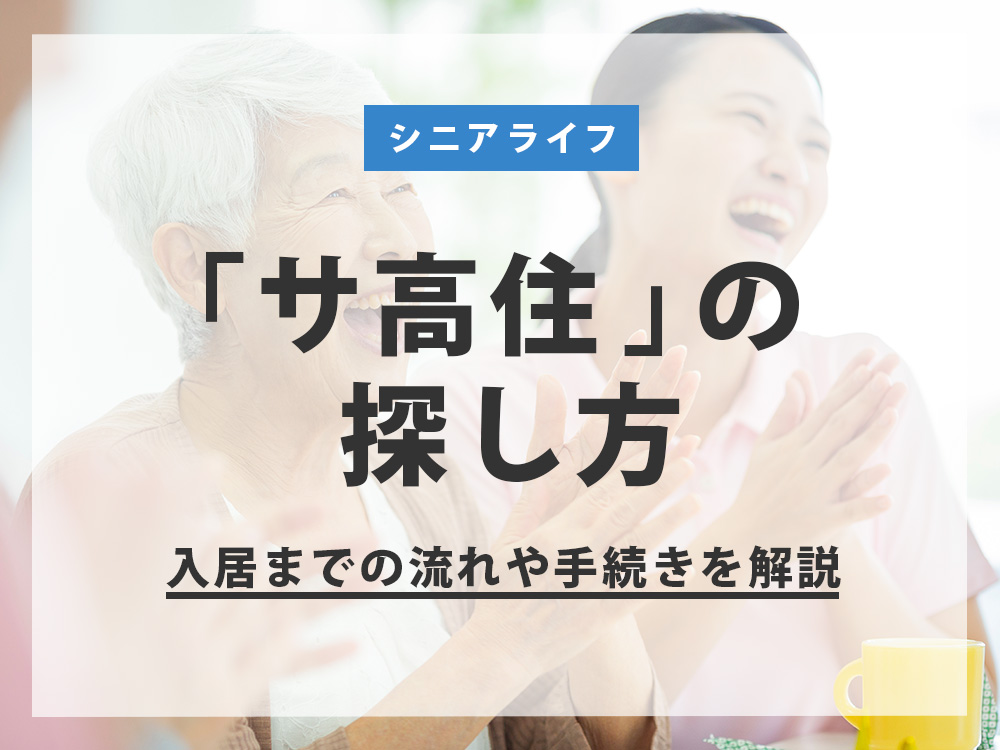
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の探し方|入居までの流れや手続きを解説
介護はまだ必要ないものの、一人暮らしには不安がある方におすすめなのが「サービス付き高齢者向け住宅」です。 サービス付き高齢者向け住宅には、基本的なサポートを提供する「一般型」と、有料老人ホームと同等のサービスを受けられる「介護型」があります。 今回は、「一般型」のサービス付き高齢者向け住宅(以下、『サ高住』)について、その特徴や探し方、見学時の注意点、そして入居までの流れや手続きについて解説します。
-
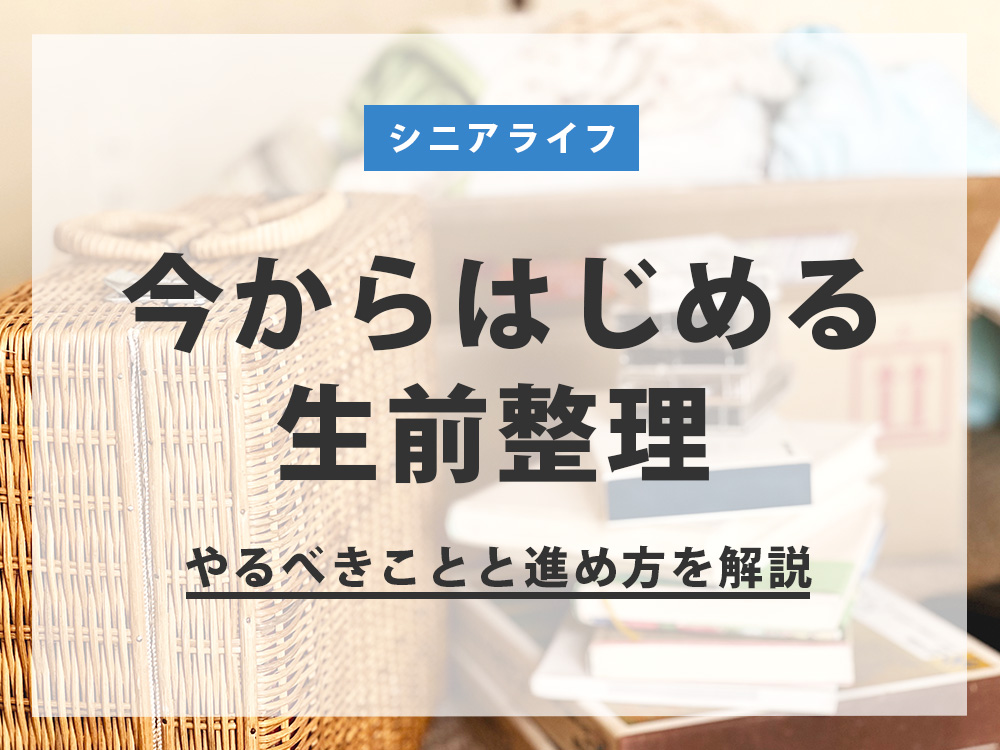
今から始める生前整理|やるべきことと進め方を解説
生前整理とは、終活の一環として、また「もしものとき」に備えて、自分の持ち物や財産、情報を整理することを指します。 自身が亡くなった後、家族や周囲の人々が負担を抱えることがないように、身の回りを整理整頓しておくことが目的です。 本記事では、整理すべき物や事項、具体的な進め方について解説します。
-
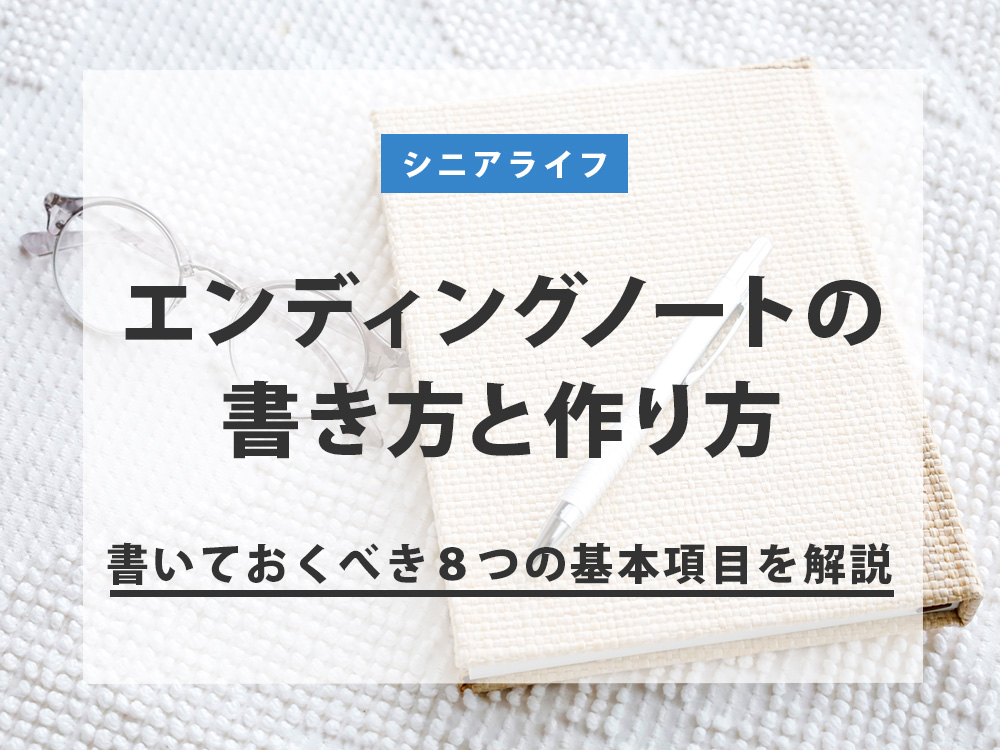
エンディングノートの書き方と作り方、家族や知人のために記す8つの基本項目を解説
終活のひとつとして、家族や友人・知人に自分の想いなどを伝える方法にエンディングノートがあります。 決まった書き方はありませんが、どんなことを書けばよいのか、ポイントをご紹介します。
-
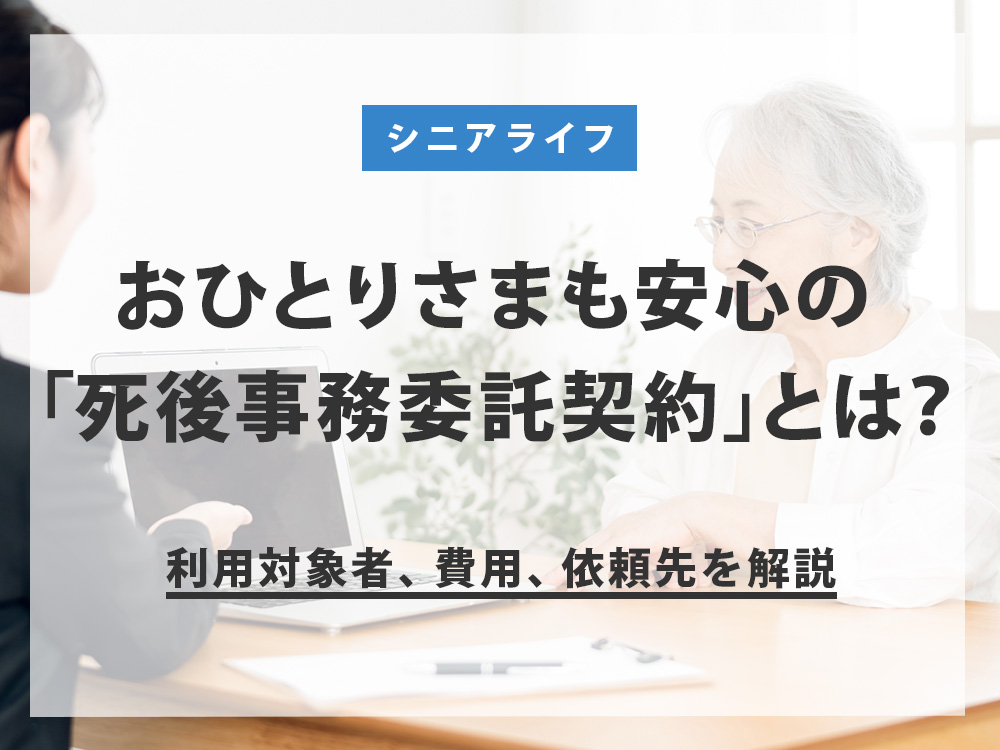
おひとりさまも安心の「死後事務委任契約」とは?利用対象者、費用、依頼先を解説
一人暮らしをしていて、親戚とは疎遠だったり、身寄りがなく親しい友人や知人もいない方は、ご自身が亡くなった後にどのように手続きが進むのか不安を感じているかもしれません。 このような場合に役立つのが、死後の様々な手続きを依頼できる「死後事務委任契約」です。 本記事では、この契約の内容とその重要性について解説します。
-
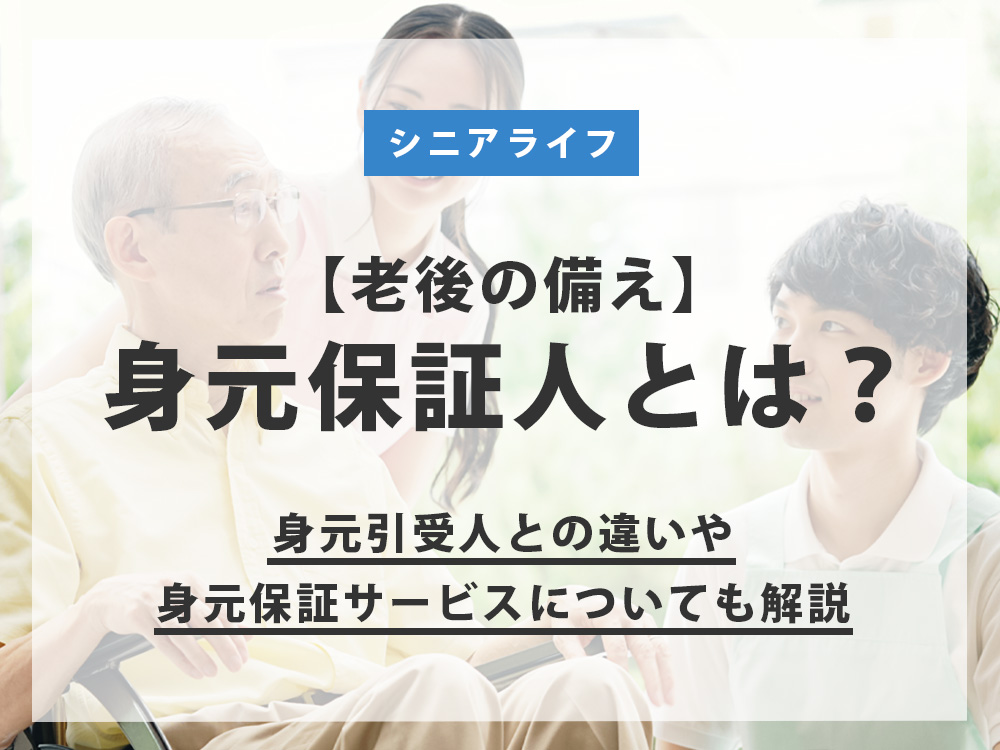
【老後の備え】身元保証人とは? 身元引受人との違いや身元保証サービスについても解説
高齢になり、病院への入院や老人ホームなどの施設入居時には、「身元保証人」が必要となることが一般的です。身元保証人は、施設との契約において利用者の責任を担う重要な役割を果たします。この記事では、身元保証人の具体的な役割と、もし身元保証人を頼める人がいない場合の対処方法について、わかりやすく解説します。
-
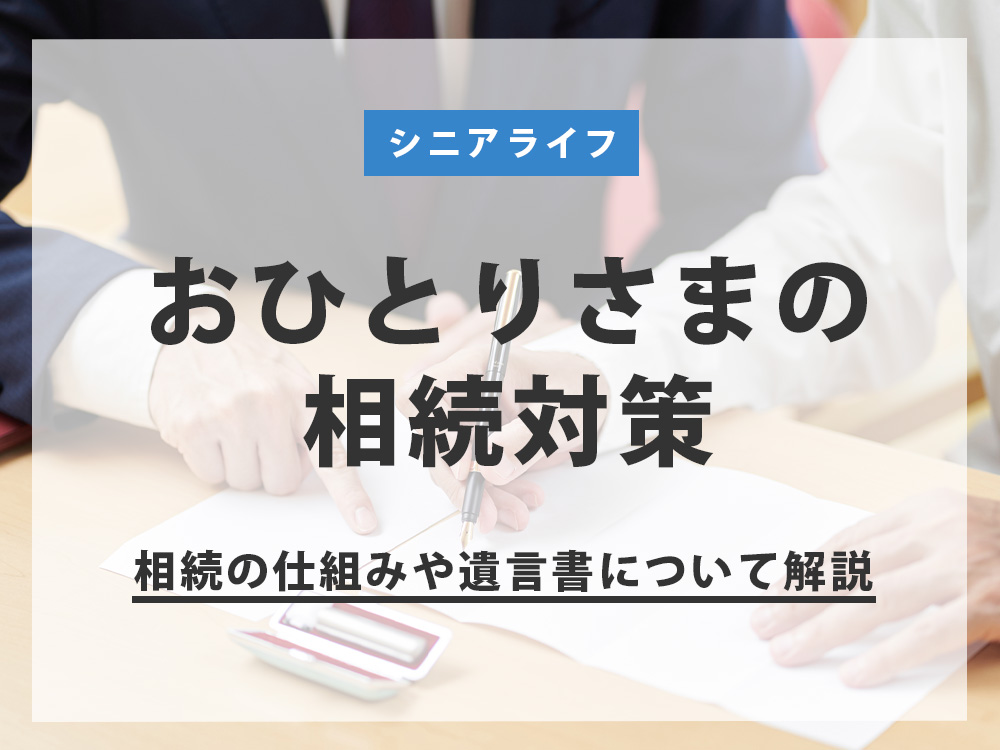
【おひとりさまの相続対策】相続の仕組みや遺言書についてわかりやすく解説
おひとりさまの場合、遺産は誰に引き継がれるのでしょうか? 子どもや親、兄弟姉妹といった法定相続人がいる場合と、そうでない場合では相続の流れや手続きが異なります。本記事では、法定相続人の概要や独身の方が自分の大切な財産を適切に遺すためのポイントを分かりやすく解説します。
-
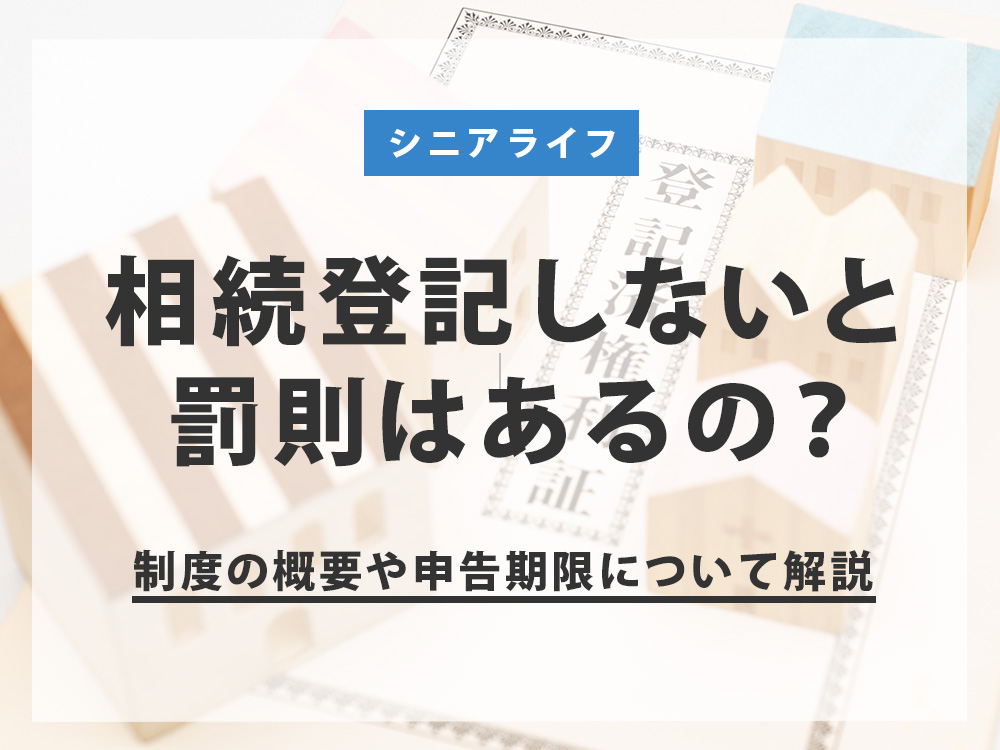
相続登記しないと罰則はあるの?制度の概要や申告期限について解説
「不動産がまだ亡くなったおじいさんや父親の名義のままになっている」というケースは、よく見られます。 しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、放置することが法律で認められなくなりました。 本記事では、この相続登記義務化の詳細と、対処法についてわかりやすく解説します。
-
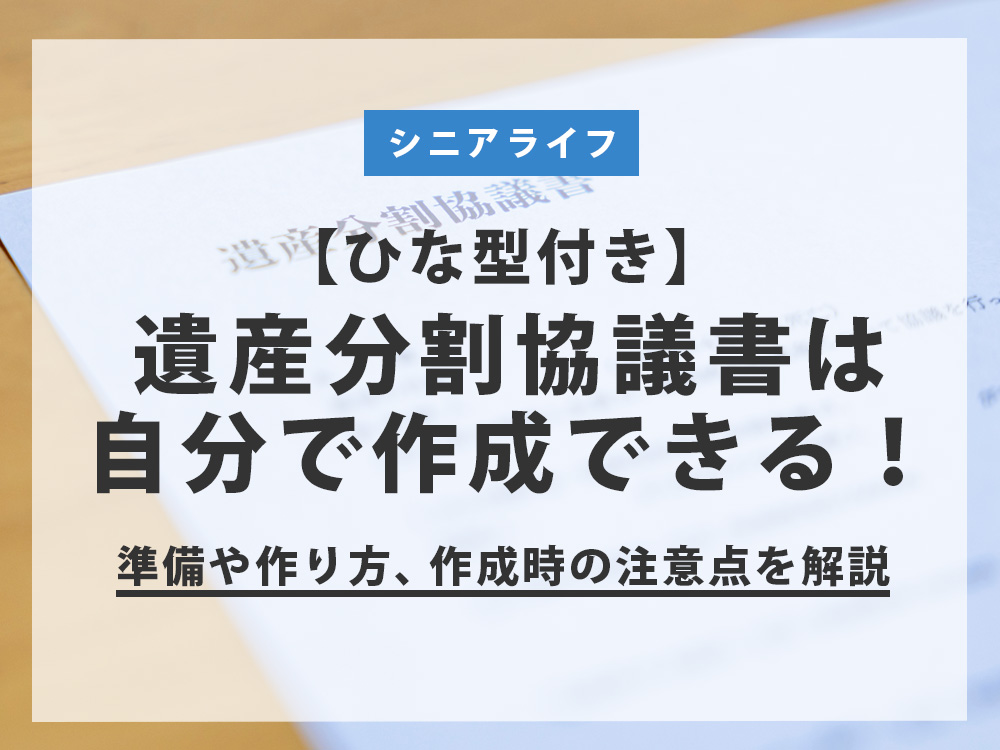
【ひな型付き】遺産分割協議書は自分で作成できる!準備や作り方、作成時の注意点を解説
相続の手続きにおいて、遺産を分割するには遺言書か遺産分割協議書が必要です。 被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合や遺言書が見つからない場合は、相続人全員の協議(=遺産分割協議)によって、被相続人が残した財産の分割方法を決める必要があります。 本記事では、遺産分割協議のための準備と協議書の作り方、作成するときに気をつけるべきポイントを解説します。
-
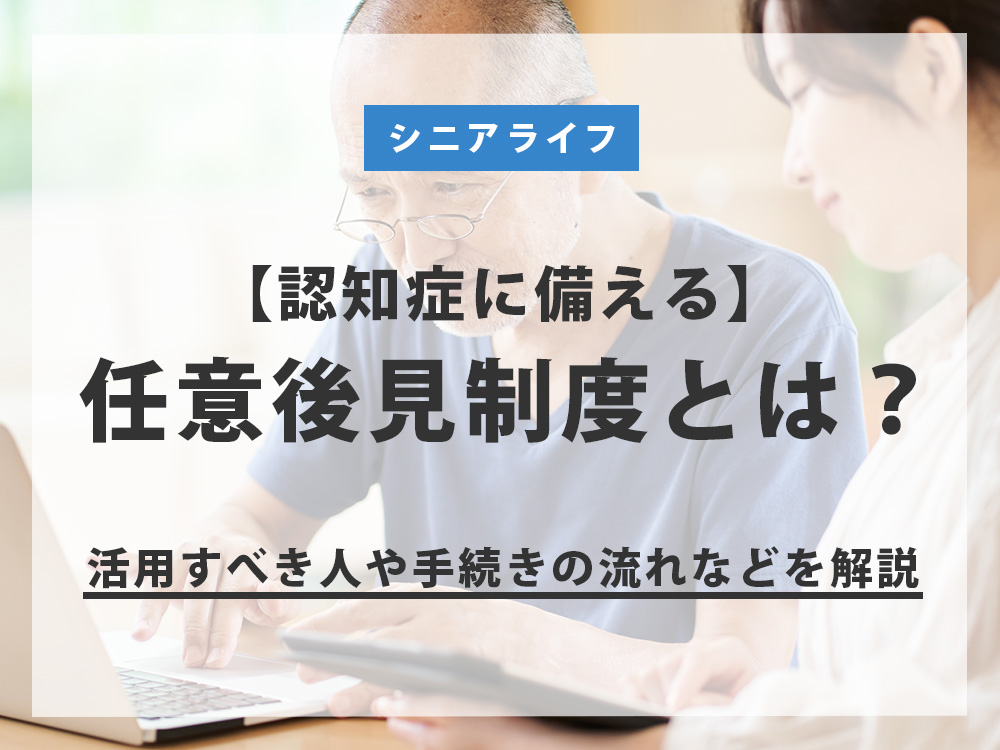
認知症に備えて任意後見制度を!活用すべき人や手続きの流れなどをわかりやすく解説
任意後見制度は、将来認知症や精神障害になってしまった場合に備えて、まだ元気で判断能力が低下する前に、あらかじめ「自分の代わりに意思決定してくれる人」を選んでおく制度です。事前に契約を取り交わし、認知症や障害などで判断能力が低下した状態になったら、手続きを経て任意後見人の役割が始まります。 この記事では、任意後見制度の内容や手続きについて解説します。
-
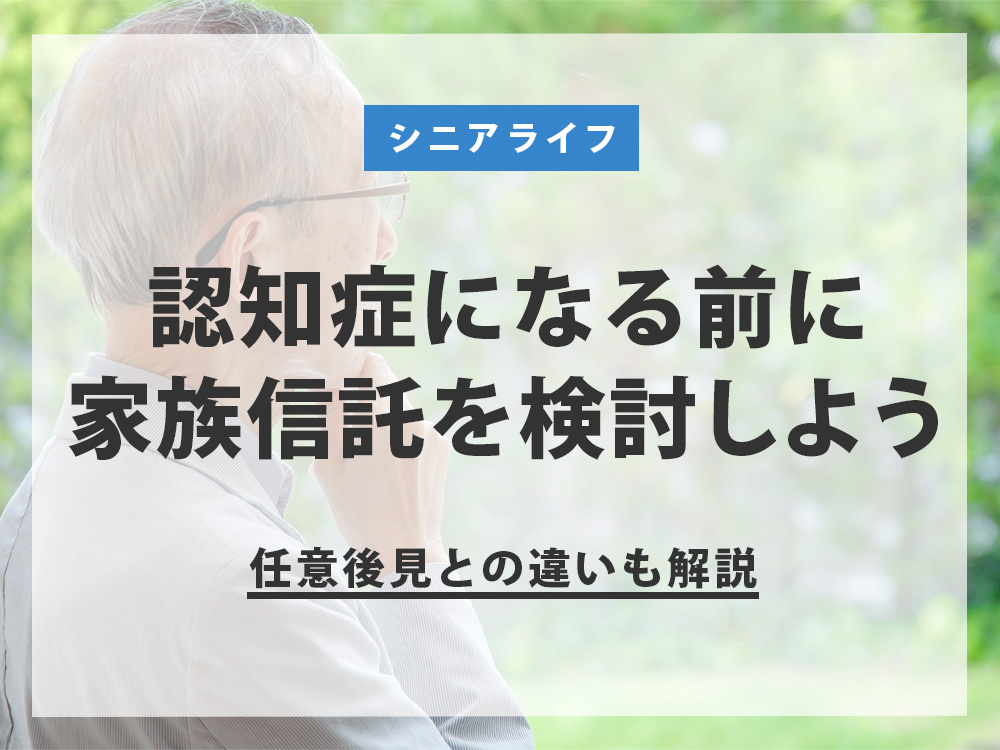
認知症になる前に家族信託を検討しよう|任意後見との違いも解説
厚生労働省の2022年のデータによると、80歳以上85歳未満の方は6人に1人、85歳以上では3人に1人が認知症を発症しています。認知症が進行すると、介護する家族の負担が増えるとともに、銀行口座が凍結されたり、介護費用に充てようと不動産や株式を売却しようとしてもできないなどの問題が生じたりすることがあります。このようなリスクを避けるために効果的なのが「家族信託」です。今回は、家族信託の仕組みとそのメリットについて解説します。
-
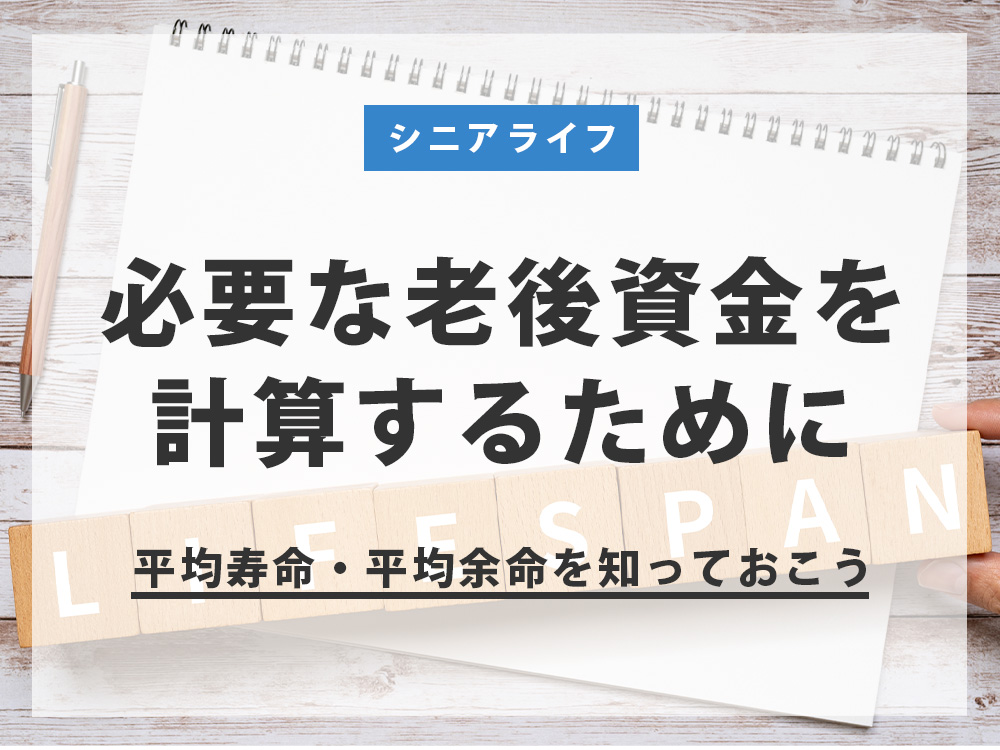
必要な老後資金を計算するために|平均寿命・平均余命を知っておこう
老後資金を計算するのに自分が何歳まで生きるのか、ある程度の予想をつけておくことは必要です。また、自分だけでなく、パートナーや親があと何年生きて老後資金はいくら必要なのかを考えるためにも、平均寿命と平均余命のデータを確認しておきましょう。
-
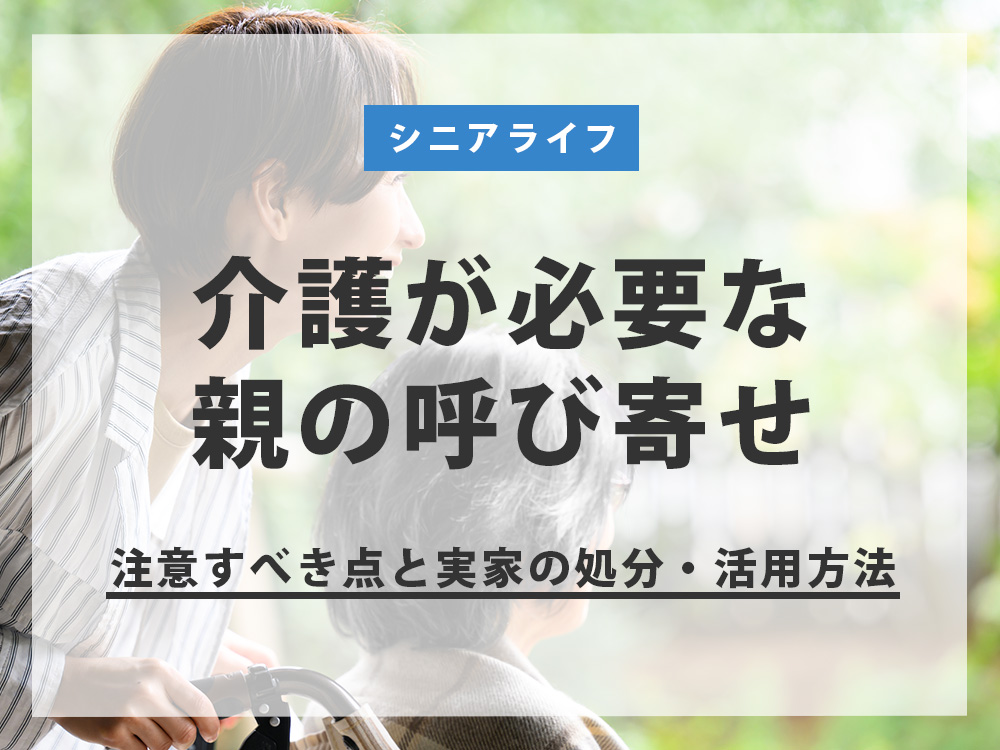
【介護が必要な親の呼び寄せ】注意すべき点と実家の処分・活用方法
遠くで暮らしている介護が必要な一人暮らしの親や、高齢の夫婦で支え合う「老々介護」になってしまった両親を自分の近くに呼び寄せることを検討している方もいるでしょう。 核家族化が進む現代において、こうした「親の呼び寄せ」という選択肢は、今後さらに増えることが予想されます。 この記事では、介護が必要な親を呼び寄せる場合の暮らし方や、空き家になった実家の処分方法などについて詳しく解説します。
-
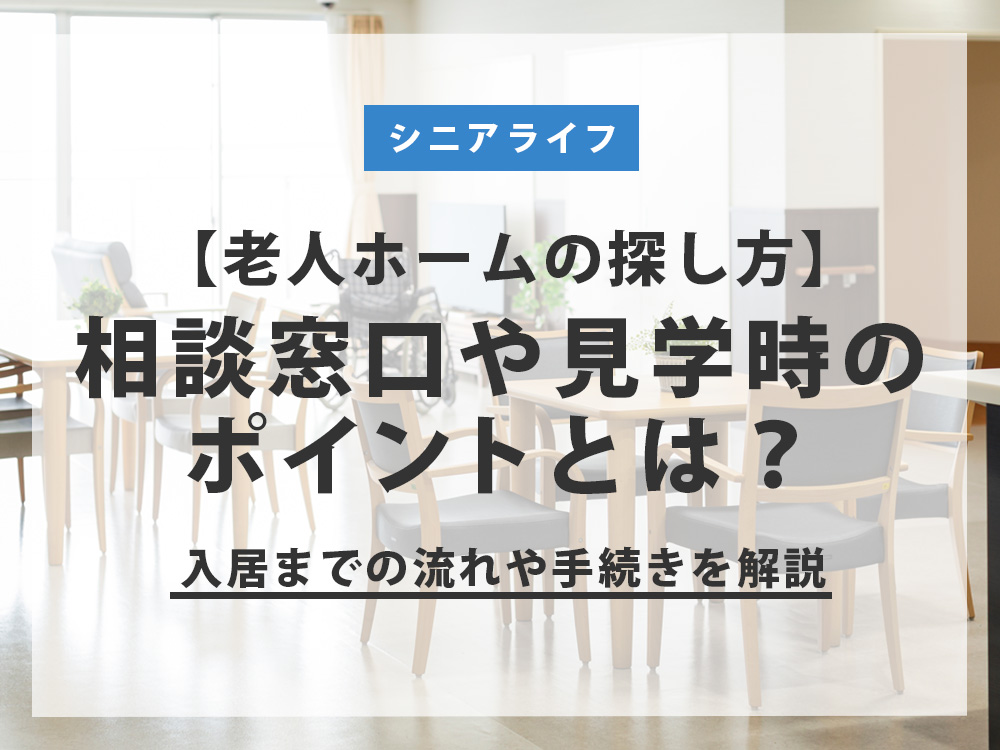
老人ホームの探し方|相談窓口や見学時のポイント、入居までの流れや手続きを解説
介護施設には、利用者の介護度や生活スタイル、ニーズに応じたさまざまな種類があります。今回は、介護が必要な方が「介護付き有料老人ホーム」および「住宅型有料老人ホーム」を選ぶ際の探し方と、見学時に気をつけたいポイント、そして入居までの手続きや必要な期間について解説します。
-
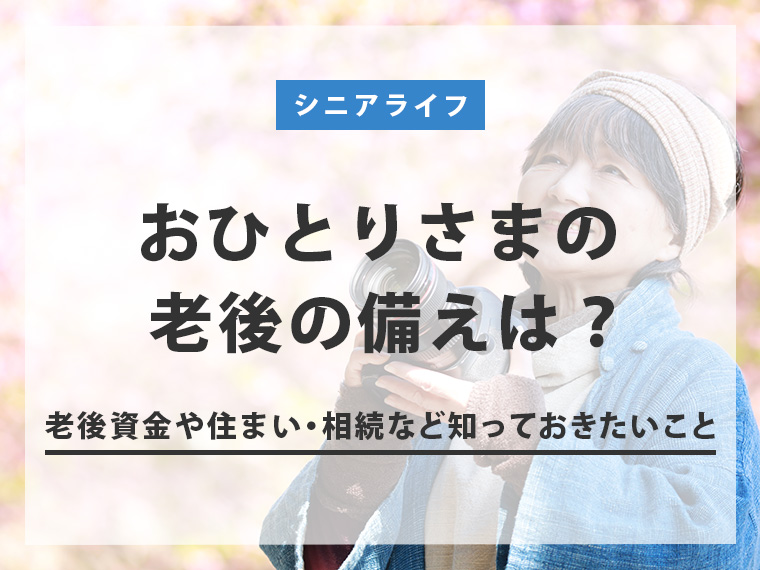
おひとりさまの老後の備えは? 老後資金や住まい・相続など知っておきたいこと
おひとりさま、いわゆる単身世帯の方はたいへん増えています。 日常生活の中で、老後資金や介護(健康面)、相続(財産処分)など、年齢とともにさまざまな心配が増えてくるのではないでしょうか。 面倒を見てくれる親戚が近くにいれば不安も軽減されますが、親戚とは疎遠の方や頼れる親族がいない方にとっては、より大きな不安が募るかもしれません。 本記事では「おひとりさま」が老後に向けて知っておくべきことや、備えておくべきポイントについて解説します。
-
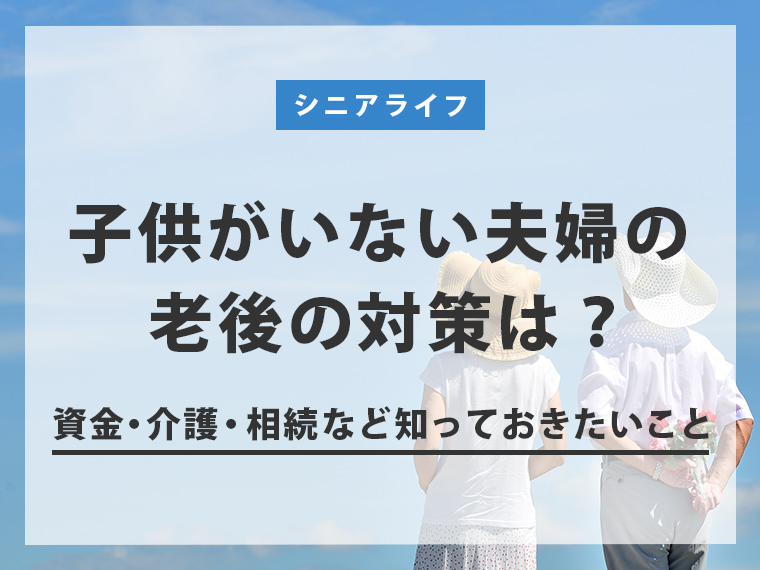
子供がいない夫婦の老後の対策は? 資金・介護・相続など知っておきたいこと
老後の暮らしを支えてくれる子供がいない夫婦にとって、老後資金や介護(健康面)、住まい、相続(財産処分)など、年齢を重ねるごとにいろいろな心配が増えてくるのではないでしょうか。 面倒を見てくれる親戚が近くにいれば不安も軽減されますが、親戚とは疎遠な方や頼れる親族がいない方は、より不安が大きいかもしれません。 本記事では、そんなご夫婦が知っておくべきポイントを解説します。
-
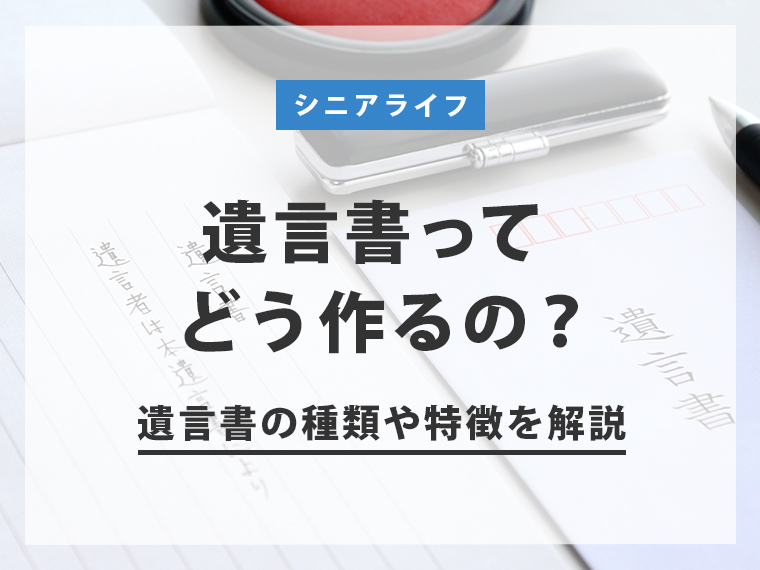
遺言書ってどう作るの?遺言書の種類や特徴を解説
遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいかを明確に示す手段であり、トラブルを避けるための重要な方法の一つです。 しかし、遺言書が正しく作成されていないと無効になってしまう可能性があります。 また、自分で遺言書を保管している場合、紛失や改ざんのリスクがあり、せっかく作成した遺言書が見つからないこともあります。 この記事では、遺言書の種類とそれぞれの特徴、注意すべきポイントについて詳しく解説します。
-
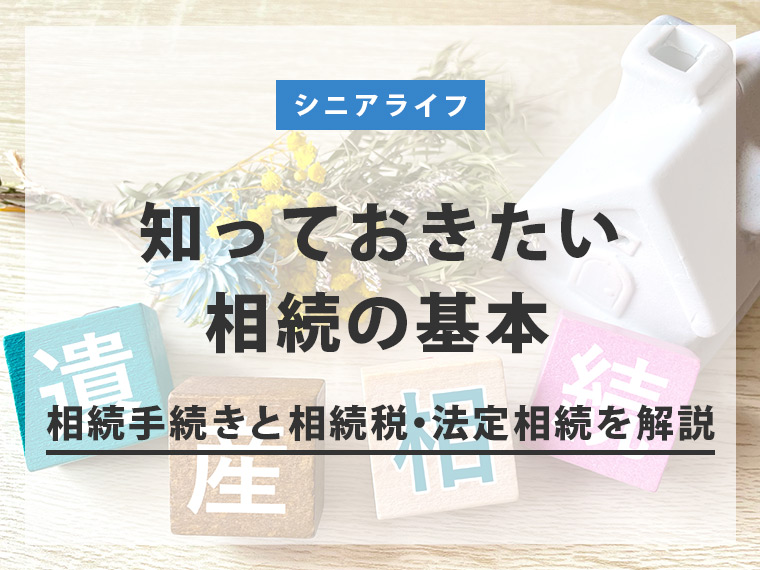
知っておきたい相続の基本。相続手続きと相続税・法定相続を解説
相続は、人生の中で誰もが経験する出来事であり、場合によっては何度も直面することがあります。しかし、初めてその状況に直面した際には、何から始めればよいのか分からず、戸惑う方も少なくありません。 相続のことでまず知っておきたいことは「相続手続き・相続税・法定相続」の3つです。 いざというときに慌てることのないよう、事前に把握しておきましょう。
-
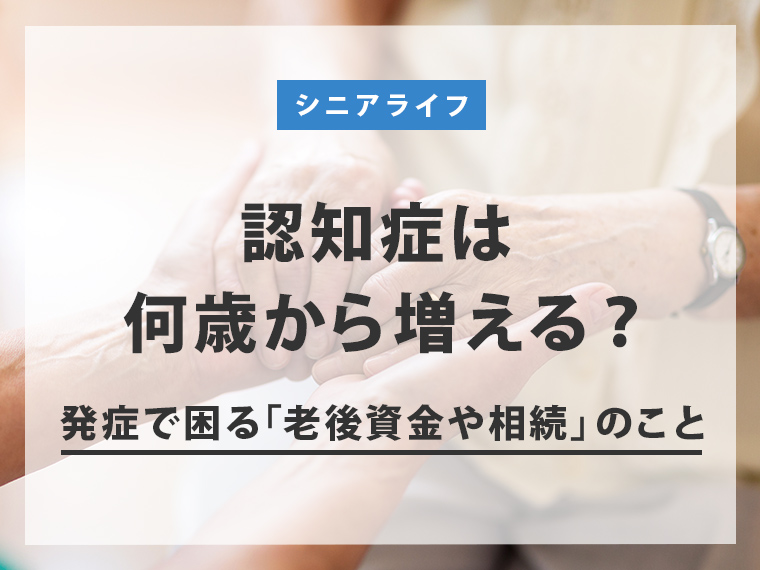
認知症は何歳から増える?発症で困る「老後資金や相続」のこと
「親に認知症の兆候が見られるように感じる」「私も将来認知症になってしまうのではないか」と心配する方は多いでしょう。 本記事では、認知症に関するデータや、物忘れと認知症の違いについて考察します。 さらに、認知症を発症すると老後資金や相続に関してどのような問題が発生するか、注意すべきポイントも解説します。
-

老後資金2,000万円の根拠は?必要な介護費用の目安も解説!
厚生労働省が2024年に発表したデータによると、日本の平均寿命は男性で81.09歳、女性で87.14歳に達しています。 平均寿命が年々延びる中で、これからの長期的な老後資金がいくら必要になるのか、誰もが関心を寄せるテーマです。 よく「老後資金は2,000万円必要」という話を耳にしますが、その根拠は何でしょうか? 最近の統計に基づく具体的な金額を算出してみましょう。
-
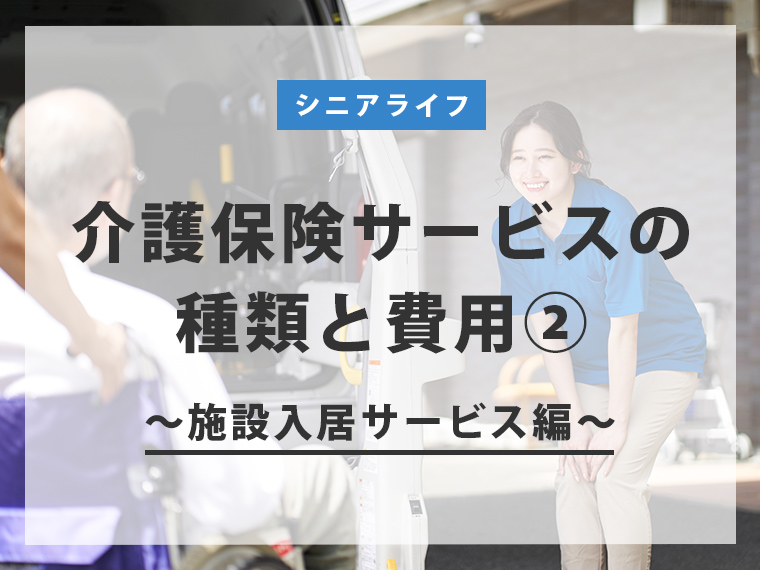
【一覧表あり】介護保険サービスの種類と費用② ~施設入居サービス編~
介護について考えるとき、まず「どんな介護サービスがあるのだろう?」と調べ始める方も多いでしょう。しかし、その種類の豊富さに戸惑うこともあるかもしれません。 介護保険サービスは主に「在宅介護サービス」と「施設入居サービス」に分けられます。 この記事では、「施設入居サービス」の種類や費用の目安について説明していますので、介護保険サービスを選ぶ際の参考にしてみてください。
-
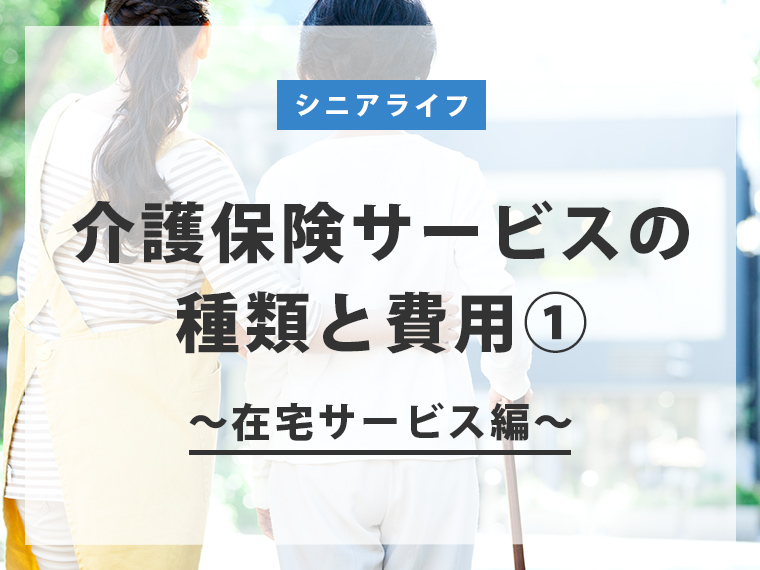
【一覧あり】介護保険サービスの種類と費用① ~在宅サービス編~
ご自身やご家族の介護を考える際、多くの人が「介護サービス」について調べると思いますが、その種類の多さに戸惑うこともあるでしょう。 介護保険サービスは大きく分けて、「在宅介護サービス」と「施設入居サービス」の二つに分類できます。 この記事では、「在宅サービス」の種類とその費用の目安についてご紹介しますので、介護保険サービスを検討する際の参考にしてください。
-
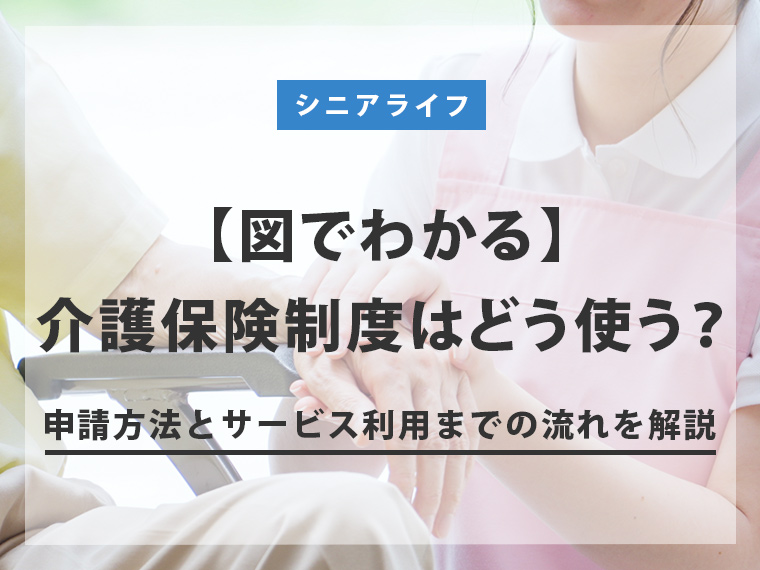
【図でわかる】介護保険制度はどう使う?申請方法とサービス利用までの流れを解説
介護保険はお年寄りが利用できるものだというイメージがありますが、何歳から利用可能で、心身がどのような状態になったら利用できるのでしょうか。 また、介護保険サービスを受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。 本記事では、介護保険の利用条件をはじめ、申請方法や受けられるサービスについて、詳しく解説します。

スターツS-LIFE相談室
シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。
⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら

