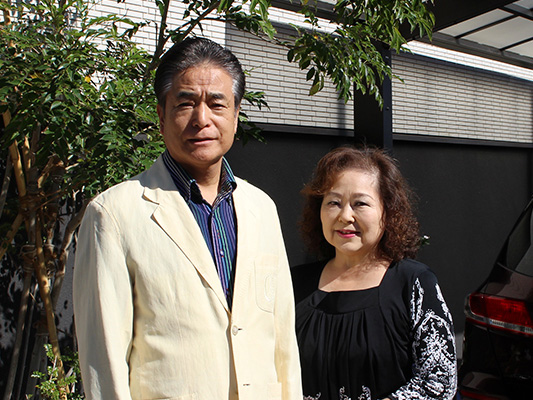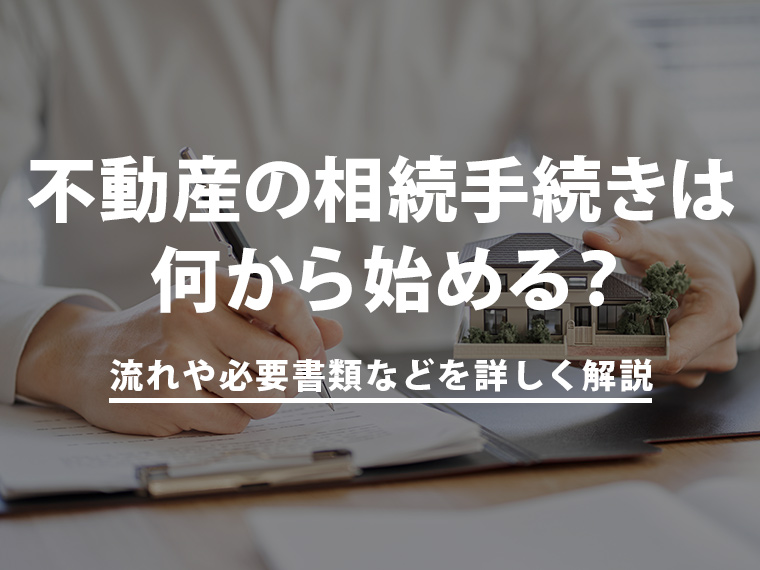- 賃貸不動産で相続税評価額を減らす
- 養子を迎え入れると控除がアップする
- 寄付をした相続財産は相続税の対象外になる
節税の選択肢1:アパート・マンションの経営
大きな節税につながる方法に、アパートやマンションの賃貸経営が挙げられます。まずは、その仕組みと注意点を見てみましょう。
アパート・マンションの経営が節税になる仕組み
富裕層の方にとって、アパートやマンションの経営は大きな節税につながる可能性があります。なぜなら、資産を現金で持っているよりも、土地や賃貸不動産として持っているほうが評価額は少なくなるからです。
現金で相続する場合、評価額は100%となりますが、相続するのが土地だと評価額が約20%下がります。たとえば、2億円の土地を購入した場合の評価額は1億6,000万円ほどになります。土地を購入するだけで、相続税の評価額を4,000万円も下げられるのです。また、その土地を第三者に貸し付けていると、「貸家建付地(かしやたてつけち)」という扱いになり、さらに評価額が1~2割下がります。先述した1億6,000万円の評価額が、1億2,800万円ほどに減額される計算です。
加えて、アパートやマンションを建てることも評価額を下げることにつながります。アパートやマンションといった建物は固定資産税評価額(一般的に取得価額の60%程度)で評価されるため、仮に1億円で集合住宅を建てた場合、その建物の評価額は4,000万円に減額されます。
2億円で購入した土地の評価額が1億2,800万円になり、1億円で建てた集合住宅の評価額が4,000万円になる可能性がある。アパート・マンションの経営が、いかに相続税上で大きなメリットになるかおわかりいただけるでしょう。
アパート・マンション経営を行うときの注意点
相続税対策として不動産経営は大変有効な手段ですが、注意点もあります。それが、空室の問題です。賃貸アパート・マンションに空室が目立つと、賃貸割合が下がり、空室部分の減額措置がなくなるからです。
賃貸経営は節税対策としておすすめの方法ですが、より効果を得るには、満室の維持を目指すとよいでしょう。
節税の選択肢2:養子縁組を活用して基礎控除額を増やす
相続税の節税対策として、養子を迎え入れる方法もあります。その節税効果と注意点を見てみましょう。
養子縁組で得られる節税効果
1人養子縁組をした場合、「相続税基礎控除」「生命保険の非課税額」「死亡退職金の非課税枠」の3つを増やすことができます。夫婦と子2人の4人家族で親が1人亡くなったとして、養子がいる場合、いない場合でどれくらい節税につながるのでしょうか。
相続税基礎控除
相続税基礎控除は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算するため、養子がいない場合の相続税基礎控除は、「3,000+(600×3)=4,800万円」です。1人養子縁組をした場合は法定相続人の数が1人増えるため、相続税基礎控除は「3,000+(600×4)=5,400万円」になります。
生命保険の非課税額
生命保険の非課税額は、「500万円×法定相続人の数」で計算するため、養子がいない場合の非課税額は「500×3=1,500万円」です。1人養子縁組をした場合は法定相続人の数が1人増えるため、非課税額は「500×4=2,000万円」になります。
死亡退職金の非課税額
死亡退職金の非課税額は、生命保険の非課税額と同じ計算で表すことができます。そのため、養子がいない場合の非課税額は1,500万円。1人養子縁組をした場合は法定相続人の数が1人増えるため、非課税額は2,000万円になります。
- 養子を1人迎え入れた場合、養子がいない場合と比べて合計で1,600万円控除額がアップ
養子縁組を活用するときの注意点
相続税対策として養子縁組を活用するとき、きちんと話し合わないと実子と養子で相続トラブルに発展しやすくなります。また、法定相続人の数に含まれる養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までという点も注意しておきましょう。
節税術3:財産を寄付して非課税扱いにする

最後に、財産を寄付して非課税扱いにする方法をご紹介します。
寄付をした財産は相続税の対象外に
相続した財産を、国、地方公共団体、公益事業を行う法人、認定非営利活動法人(認定NPO法人)などに寄付をした場合、寄付金額は相続税の課税対象外になります。
相続人が相続税を支払ったとしても、税金の用途を決めることはできません。しかし、寄付を選択すれば、お世話になった学校や進めてほしい公益事業など、相続人の意思で公共の利益に役立てることが可能です。
控除しきれない相続財産を公共団体などに寄付をすることで、相続税の節税にもつながります。
寄付で節税するための注意点
ここでは、相続税節税のために相続財産を寄付する場合の注意点を3つ、ご紹介します。
- 寄付をするお金は相続や遺贈で得たものに限る
- 寄付先は国・地方公共団体や公益法人、NPO法人であること
- 相続開始後10ヶ月以内に寄付する
なお、寄付をして2年の間に寄付先が公益目的の事業をしなくなったり、寄付金が公益事業に使われていなかったりした場合は、非課税の特例が適用されません。寄付先の選定は、注意して行いましょう。
3つの方法を活用して節税対策をしよう
富裕層の方にとって、重くのしかかる相続税は大きな課題でしょう。相続税を節税する方法には、「賃貸不動産の取得」「養子縁組の活用」「相続財産の寄付」などが挙げられます。これらを上手に活用し、きちんと相続税の対策をしておきましょう。不慣れな方が自分の力だけで土地などの賃貸不動産を取得することは難しいため、専門家の力を借りるのも手です。
相続対策についてさらに詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方