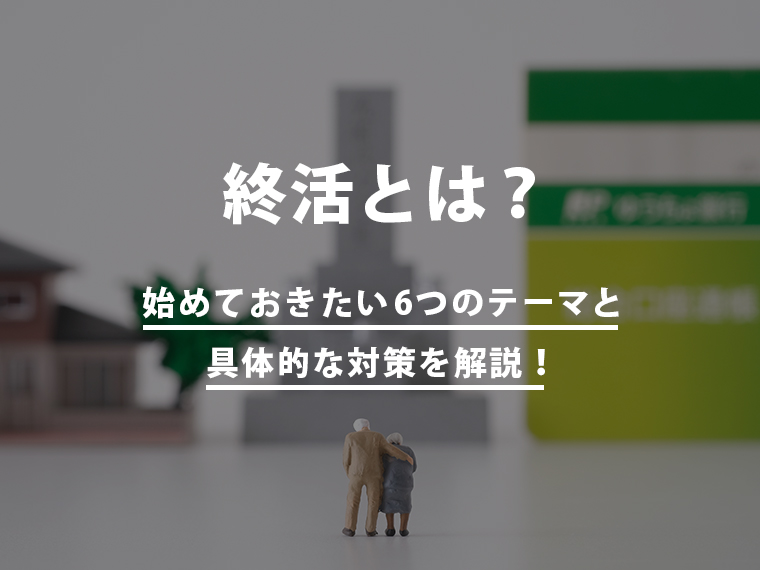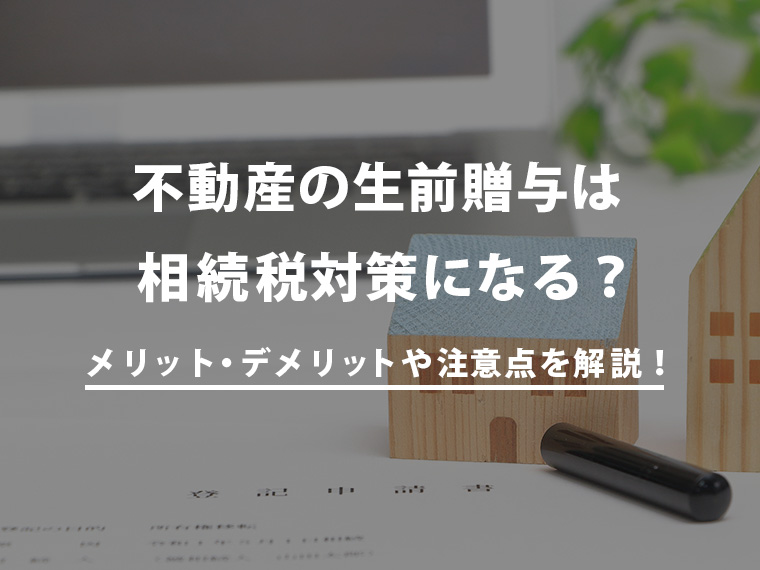相続の手続きに関して、ほとんどの方が「何から始めたらいいのかわからない」と回答するのではないでしょうか。そこで今回は、いざというときに慌てないために、相続後の手続きについての手順と、各手続きで注意したいポイントについてご紹介します。
- 相続手続きには期限があり、期限を過ぎると延滞税を支払わなければならないケースがある
- 遺言書の確認は検認が必要で、勝手に封を開けると処罰を受ける可能性がある
- 相続財産はプラスの財産だけでなく、マイナスの権利も含まれるため注意が必要
なるべく早く行いたい相続開始後に取るべき行動
相続開始後には、相続財産を引き継ぐための手続きが必要です。相続手続きの簡単な流れは、以下の通りです。
- 死亡届の提出や葬儀
- 遺言書の検認
- 相続財産や相続人の確定
- 相続するかどうかの判断
- 確定申告
- 遺産分割協議
- 相続税の申告
ここでは、ステップごとに分け、注意事項と合わせて解説します。また、手続きには期限があるため、まずは早めの手続きが必要なものを見ていきましょう。
<7日以内の手続き>死亡届の提出・葬儀
亡くなったことを証明するものが死亡診断書です。死亡診断書は医師による判断が必要なため、病院で発行してもらいます。また死亡理由が不明の場合は、死体検案書が死亡を証明する書類となるケースもあります。
亡くなったことを証明する書類と一緒に死亡届を市区町村役場に提出することで、火葬許可証をもらえます。火葬許可証を葬儀社に提出すると火葬の申し込みが可能となり、葬儀ができるようになります。
死亡届は、亡くなった日から7日以内に提出しなければならないため、注意してください。また、死亡診断書は今後の手続きで必要になることもあるため、コピーをとっておくとよいでしょう。
<なるべく早く>遺言書の検認
相続財産を分ける前に、遺言書があるかどうかの確認をする必要があります。遺言書があった場合には、遺言書をもとに相続財産を分ける必要があります。
ただし、遺言書を見つけた場合、勝手に封を開けないようにしましょう。勝手に封を開けると、5万円以下の過料を科されるケースもあります。
そのため、遺言書を見つけたら、まずは亡くなった方の住所地を管轄している家庭裁判所に問い合わせましょう。そして家庭裁判所にて遺言書の検認を申し立てて、内容を確認してください。
<なるべく早く>相続財産・相続人の確定
遺言書が見つかったら遺言書通りに、遺言書がなければ相続人同士で、分割方法について話し合いを行います。そのためには、どれだけの相続財産があって、相続人は誰なのかを確定しなければなりません。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を役場で取り寄せることで、相続人の確認が可能です。自分以外に子どもはいないと思っていても、戸籍謄本を取り寄せることでほかに相続人がいることが発覚するケースもあります。
<なるべく早く>遺産分割協議
相続財産や相続人の確定後、遺言書がない場合は遺産分割協議を行います。大半の方が行う一般的な方法と言えるでしょう。
遺産分割協議で遺産分割協議書を作り、その内容に沿って分割を行いますが、相続人のうち1人でも反対すると成立しません。そのため、遺産分割協議決裂によって調停や審判を利用する方もいます。遺言書は、トラブル防止に有効なため、生前に遺言書を作成しておくとよいでしょう。
こちらの記事も読まれています
数ヶ月以内に行いたい相続開始後に取るべき行動

次に、数ヶ月以内に行いたい相続手続きと注意点についてご紹介します。
<3ヶ月以内>相続の放棄
相続は、銀行預金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、多額の借金ばかりが残されている場合は、相続しないほうがよいケースもあります。そういった場合には、相続を放棄することも可能です。
相続の放棄に関しては、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりません。相続放棄の手続きをしないと相続を受け入れたことになるため、注意しましょう。
手続きの方法や相続放棄したほうがよいかどうかの判断に困った場合は、税理士や司法書士、弁護士に相談するとよいでしょう。
<4ヶ月以内>準確定申告
亡くなった方に所得がある場合は、亡くなるまでに受け取った所得に関して確定申告を行う必要があります。これを所得税の準確定申告と呼び、亡くなって4ヶ月以内にしなければなりません。
通常の確定申告は、翌年の2月から3月に行いますが、準確定申告は確定申告の期間に関係なく、亡くなって4ヶ月以内に行わなければ延滞税がかかる可能性があるため、注意しましょう。
<10ヶ月以内>相続税の申告・納税
相続の最後の手続きが、相続税の申告や納税です。亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に行わなければなりません。相続税の計算では基礎控除があるため、すべての相続財産から基礎控除を差し引き、基礎控除を上回る金額に応じて相続税率が決まります。
遺産分割協議がこじれている場合、10ヶ月以内に間に合わない場合もあるでしょう。そういった場合でも10ヶ月以内に申告をしなければならず、法定相続分で相続したとして申告と納税を行います。
そして遺産分割協議が終わったあとに、相続財産を計算し直して税務署で手続きを行い、還付を受けたり追加で相続税を支払ったりすることが可能です。
相続手続きで困らないために事前の話し合いが必要
相続手続きでは、このほかに生命保険金の請求や公的年金・健康保険の停止など、さまざまな手続きをしなければなりません。
いざというときに慌てないためにも、どこにどんな書類を置いているのか、誰に連絡したらよいのかなど、日頃から話し合っておきましょう。さらに、相続人の間でトラブルにならないためにも、できれば遺言書を作成してもらっておくと安心です。
相続後の手続きに関して詳しく知りたい方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方