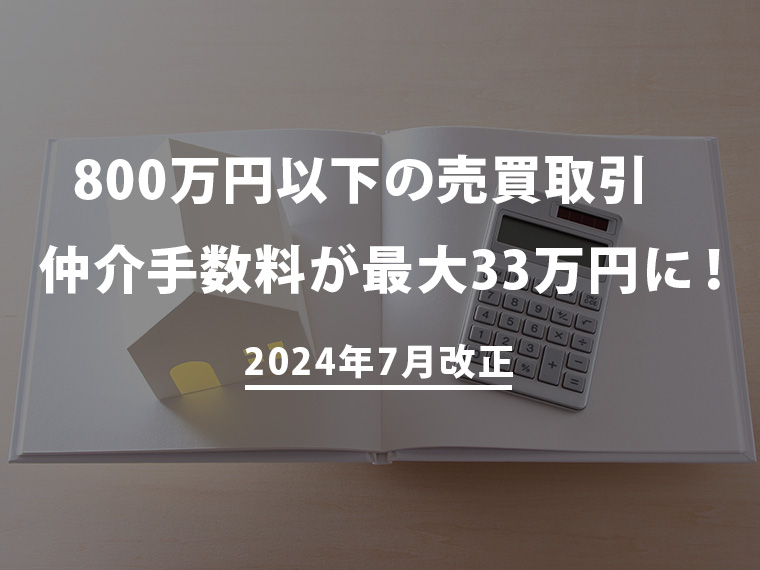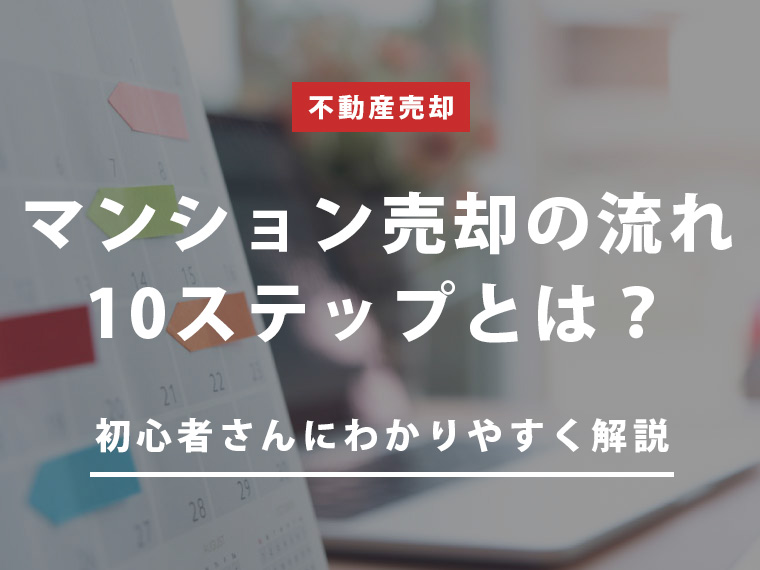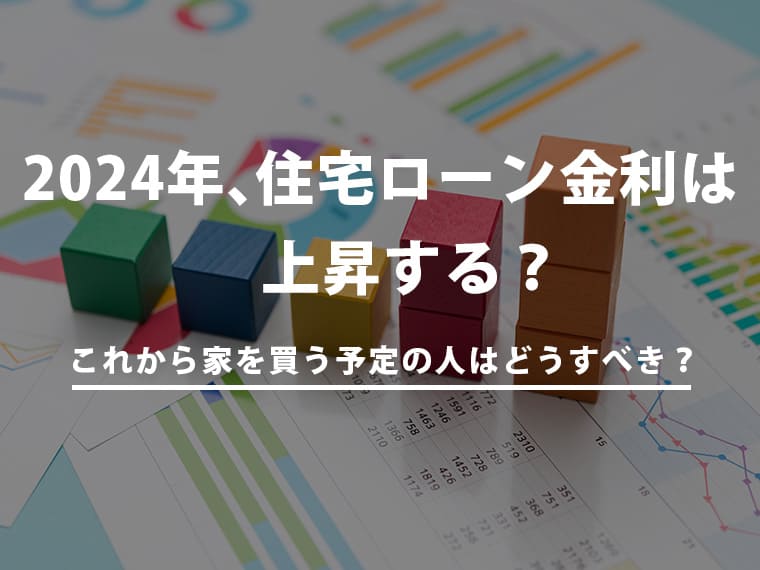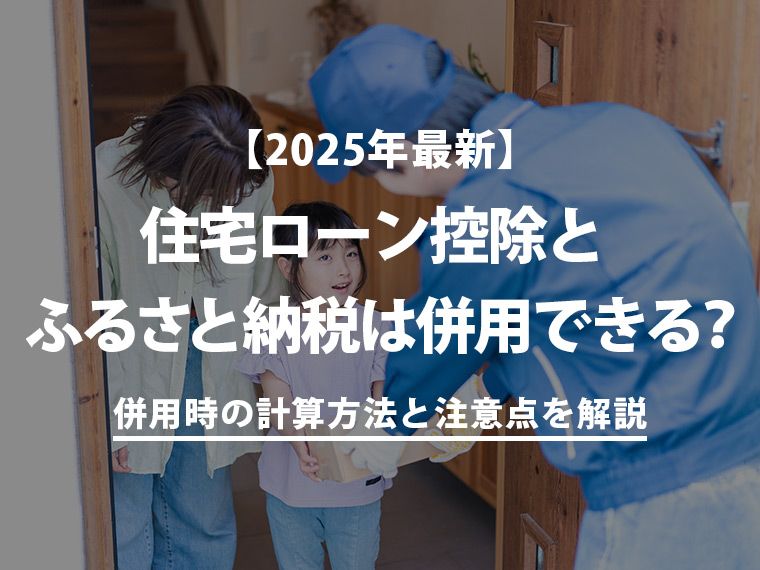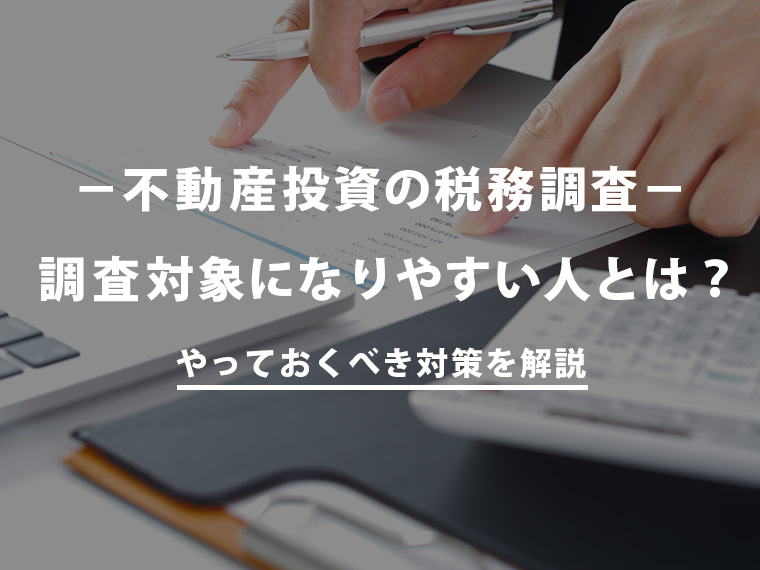- 小規模宅地等の特例を使えば、最大80%も不動産の評価額を下げられる
- 小規模宅地等の特例を適用できるかどうかは、同居要件がポイント
- 二世帯住宅で区分所有登記をしていた場合は、同居に該当しないため注意
「小規模宅地等の特例」って何?
相続税は、故人(被相続人)の財産総額をもとに税率が決まる「累進課税(るいしんかぜい)方式」を採っています。そのため、相続財産の評価額を下げることが相続税の減額に直結します。
土地や建物などの不動産は、相続財産のなかでも高額な相続税が発生しやすいものの一つ。しかし、高額な相続税を支払うために、相続人が住居や事業で使う不動産を手放したり、それによって生活に困ったりするのは非常に酷な話と言えるでしょう。
そこで設けられたのが、「小規模宅地等の特例」です。小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たした小規模宅地の評価額を大幅に減額できる制度のこと。被相続人と生計を一にしていた相続人が相続するという条件のもと、居住用に供された宅地等であれば330㎡を上限に、また事業用の宅地等であれば400㎡上限として、不動産の評価額を最大で80%(評価額が1億円の不動産なら2,000万円に)減額することが可能です。
ただし、「生計を一にしていた」という、いわゆる同居要件にはいくつかのポイントがあります。次の章で、同居が認められる事例と認められない事例を確認しましょう。
特定居住用宅地等における同居要件とは?

特例の対象となる小規模宅地等には「事業用」と「居住用」がありますが、ここでは多くの方に関係する居住用についてご説明します。この特例に該当する不動産を「特定居住用宅地等」と呼び、特定居住用宅地等に該当するには「相続人の要件」と「同居の要件」を満たさなければなりません。
相続人の要件とは?
小規模宅地等の特例を適用できるのは、相続人のなかでも、被相続人の配偶者と被相続人の同居家族、被相続人と生計を一にしていた親族だけです。
同居の要件とは?
一般的に同居とは、一つの家に住み寝食をともにする状況を指します。ただし、なかには単身赴任や老人ホームに入居するなど、別々に住むこともあるでしょう。相続人が単身赴任の場合は、単身赴任が終われば戻ってくる可能性があることが同居の定義。被相続人が老人ホームに入居している場合は、相続人がそのまま家に入居していれば同居と認められます。
また、二世帯住宅のケースもあるでしょう。こちらは登記によって異なり、共有登記であれば同居と認められます。しかしその一方で、区分所有登記をしていた場合はマンションと同じように建物を区切っていることになるため、同居には該当しません。
このほか、介護のために一時期だけ泊まり込みで一緒に住んでいたケースや、住民票だけ被相続人の住所に移しておいたケースも同居とは認められないため、注意しましょう。
小規模宅地等の特例を使うには専門家に相談しよう
「小規模宅地等の特例」を使えば、大幅に相続税評価額を低減できる可能性がありますが、要件に該当していなければそもそも適用されません。今回は被相続人の同居要件を簡単に説明しましたが、親族の場合は「配偶者や同居家族に該当する相続人がいないこと」などの細かい要件も含まれます。そのため、特例の適用を検討する際は相続税に詳しい専門家に相談するのがよいでしょう。
小規模宅地等の特例を使った相続税対策についてさらに詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-
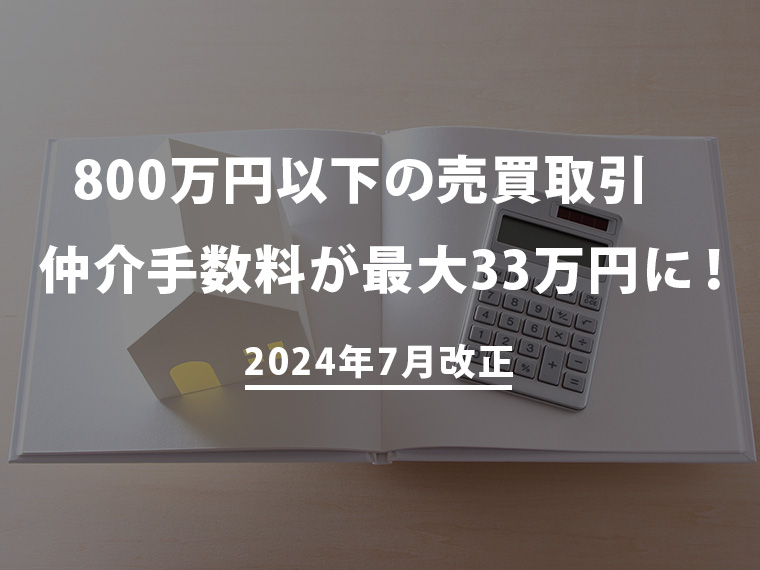
【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-
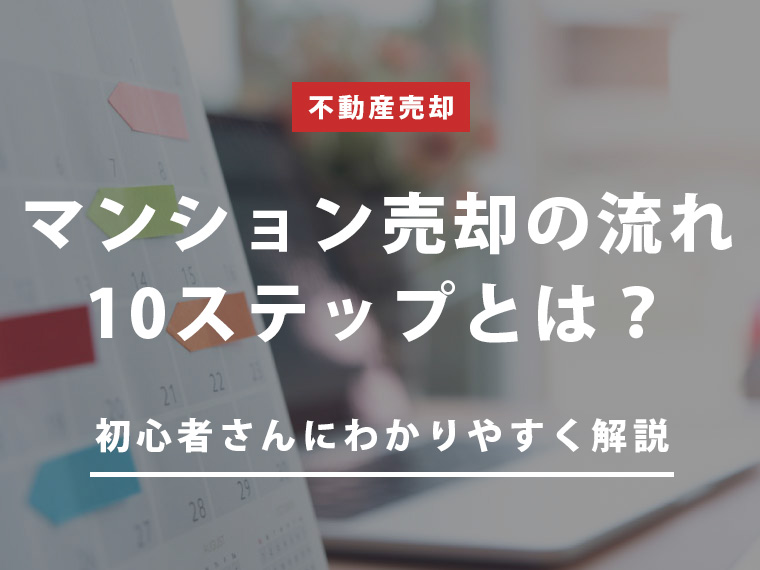
マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-
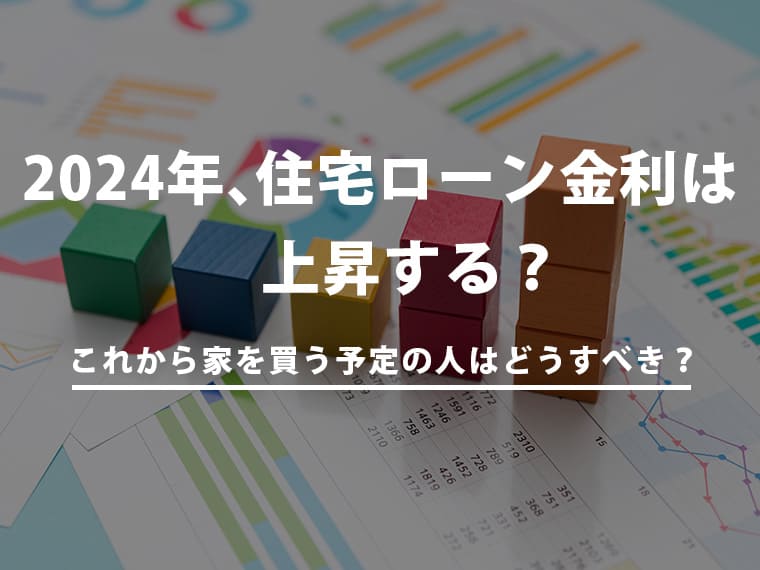
2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-
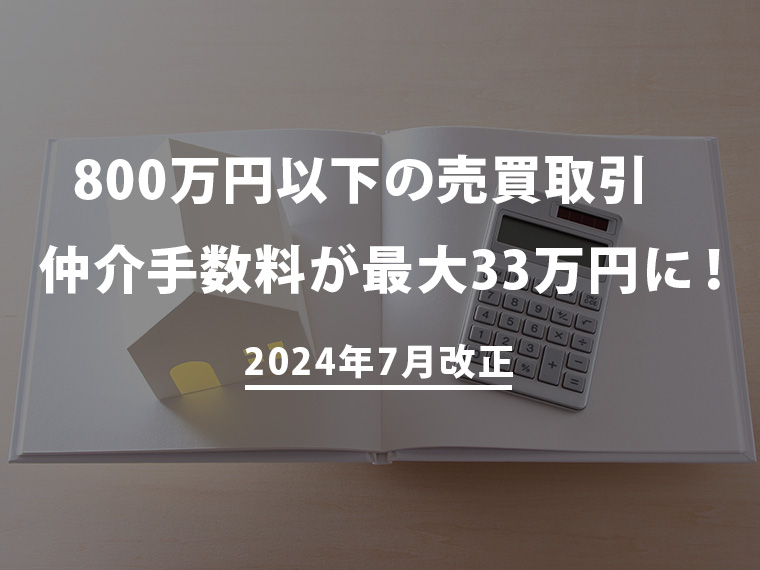
【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-
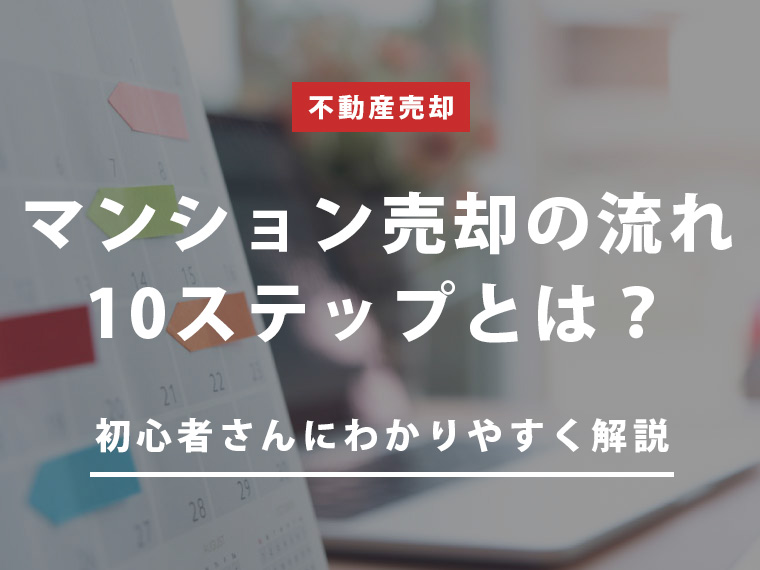
マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-
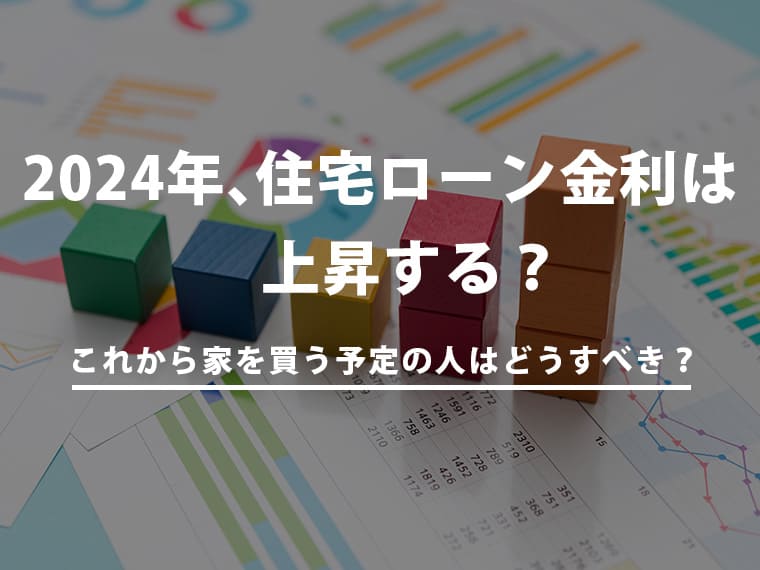
2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方