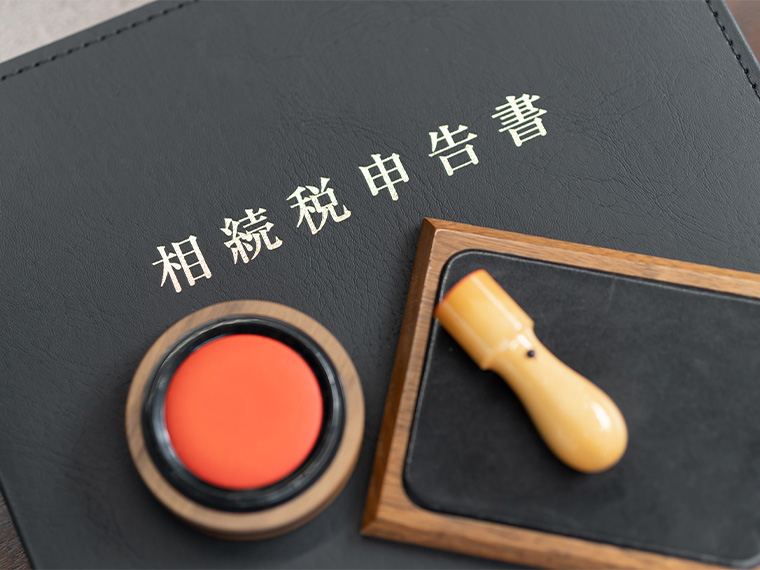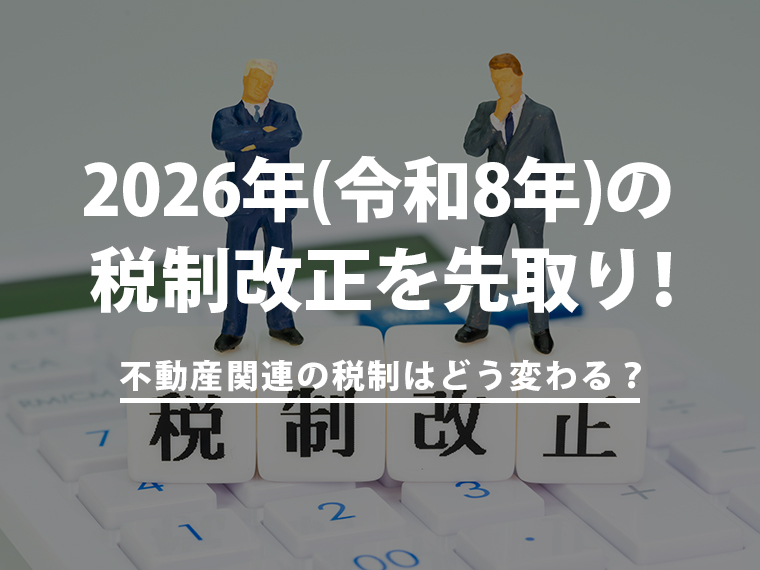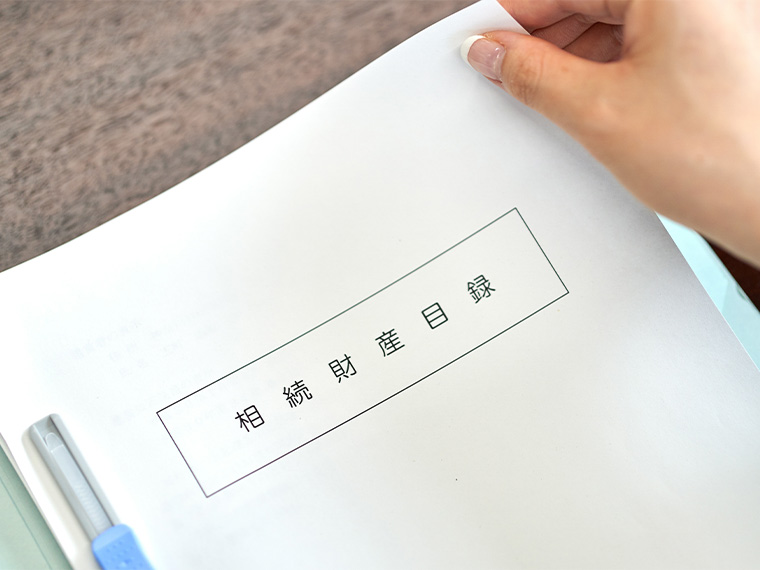- 生前贈与により相続税を抑えることが可能
- 年間合計110万円の贈与税の非課税枠を活用するのがおすすめ
- 贈与額2,500万円まで非課税の相続時精算課税制度の適用も検討を
一定の金額以上の財産を相続すると相続税などの税金が発生しますが、相続税は対策を講じることで節税が可能です。今回は、生前贈与で相続税を抑える手法と、節税のポイントや注意点を解説します。
生前贈与による節税方法は、一つではありません。財産や相続・贈与する相手によって適した対策は異なります。自身のケースに合う方法を検討する際に、ぜひ参考にしてみてください。
こちらの記事も読まれています
生前贈与で相続税を抑える
相続税を抑えるにはさまざまな手法がありますが、生前贈与もその一つです。贈与とは無償で財産を贈ることを意味し、生前贈与では被相続人が生きているうちに財産を贈与することで、相続財産を事前に分散させることができます。
ここからは、難易度の易しい順に生前贈与によって相続税を抑える方法をご紹介します。
方法①暦年贈与の非課税枠で生前贈与
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、暦年課税には年間合計110万円までの非課税枠があります。この非課税枠を活用して生前贈与する方法が一つです。
仮に、被相続人が財産を分配したい相手へ年間110万円の贈与を10年に渡って続けた場合、1,100万円を非課税で贈与できることになります。基本的に、相続時には法定相続人が財産を受け取る仕組みとなっていますが、生前贈与であれば相続人以外にも財産を分配することが可能です。
方法②生活費や教育費の一括贈与
30歳未満の人が両親や祖父母といった直系尊属から教育資金に充てるための財産贈与を受ける場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。ただし、金融機関などの営業所を通して教育資金非課税申告書を提出することが必要です。
方法③結婚や子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の人が直系尊属から結婚資金や子育て資金の贈与を受ける場合、1,000万円までの金額については贈与税が非課税となります。金融機関などの営業所を通して結婚・子育て資金非課税申告書の提出が必要ですが、こちらも相続時の節税対策につながると言えるでしょう。
方法④相続時精算課税制度で生前贈与
相続時精算課税は2,500万円の贈与まで非課税となる制度で、60歳以上の親や祖父母から20歳以下の子どもや孫へ贈与する場合に適応できる制度です。贈与税の申告書の提出が必要ですが、財産の種類や贈与回数、年数などの制限はありません。
これら4つの方法は、相続時精算課税と暦年課税(年間合計110万円の基礎控除)が併用できない点は、おさえておきたいポイントです。
生前贈与で節税対策をする際の注意点
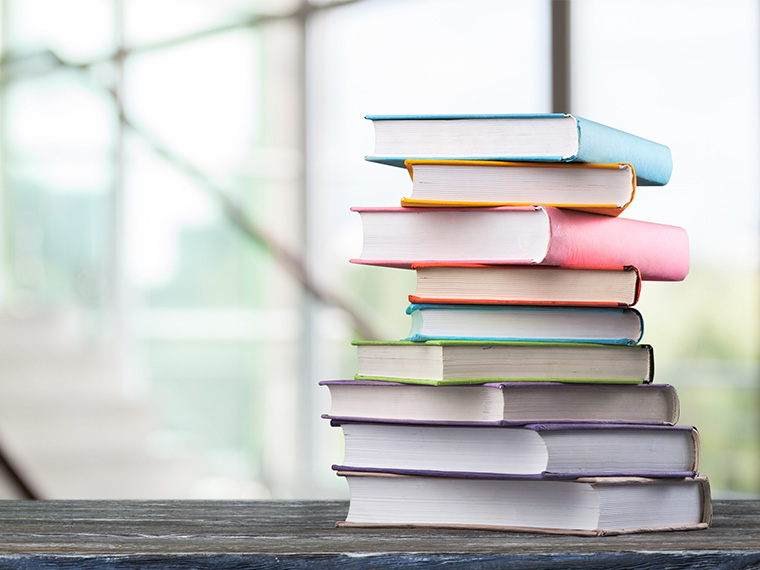
税金を抑えることを目的として生前贈与をする場合、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
暦年贈与の非課税枠で生前贈与を行うなら110万円以内で
暦年贈与の非課税枠で生前贈与を行う場合、年間110万円の基礎控除枠を超えないよう確認しましょう。一度の贈与額が少なくても、複数の贈与があり合計で110万円以上の贈与があった場合は、以下の計算方法にもとづき贈与税がかかります。
贈与税
=(年間贈与額-基礎控除枠110万円)
×税率-控除額
暦年贈与の税率には「一般贈与財産(一般税率)」と「特例贈与財産(特例税率)」の2パターンがありますが、仮に250万円の贈与を受けた場合、税率はどちらも15%、控除額もどちらも10万円となり、贈与税は「(250万円-110万円)×0.15-10万円=11万円」の贈与税がかかります。
暦年贈与は定期贈与とみなされないよう注意
暦年贈与を行う場合、毎年贈与を重ねると定期贈与とみなされることがあり、注意が必要です。定期贈与とみなされると、合計金額に贈与税が課税されるケースがあります。対策として、毎年の贈与でも「時期をバラバラにする」「金額を一定にしない」といった工夫をするとよいでしょう。
生前贈与した財産が相続税に加算されるケースもある
暦年贈与の基礎控除枠内で生前贈与をしていても、注意が必要なケースがあります。贈与する方と贈与される方の関係が被相続人と相続人であった場合、被相続人の死亡から過去3年以内に贈与された財産は相続財産に加算され、相続税がかかるので心しておきましょう。
相続時に精算課税制度を活用して生前贈与した相手が相続人だった場合も、相続時に生前贈与分の財産が相続財産に加算されます。この場合は過去3年以内にかかわらず、相続財産とみなされます。
ただし、たとえば配偶者と子どもがいる方が孫に相続時精算課税制度を活用して生前贈与した場合、孫は原則相続人ではないため、相続税はかかりません。
贈与税より相続税を払うほうが得なケースもある
実は、贈与税の税率は相続税の税率よりも高いので、財産の額によっては税金が高くついてしまうケースもあります。たとえば200万円の贈与の場合、贈与税率は15%と紹介しましたが、1,000万円の場合は特例税率で40%(控除額190万円)、一般税率で45%(控除額175万円)です。
これに対し、相続税率は10%となります。暦年贈与の非課税枠を超えて贈与を受ける場合などは、税金の計算を綿密に行いましょう。
生前贈与の仕組みを理解して効果的な節税を
相続税を抑える手法の一つとして生前贈与をする場合、暦年課税の基礎控除枠110万円以内で贈与することが、一つの基準となるでしょう。贈与税と相続税の仕組みを知り、ご家庭のケースに合わせて相続時精算課税制度などを活用した対策も検討してみてください。
詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方