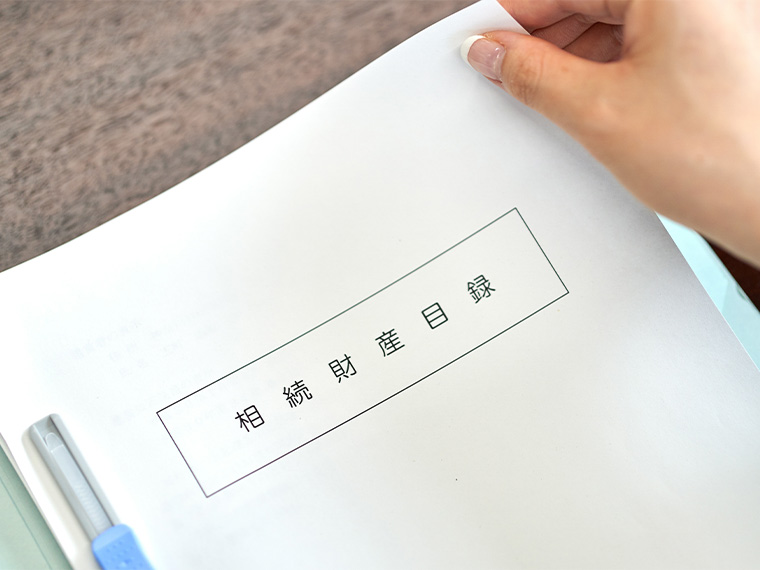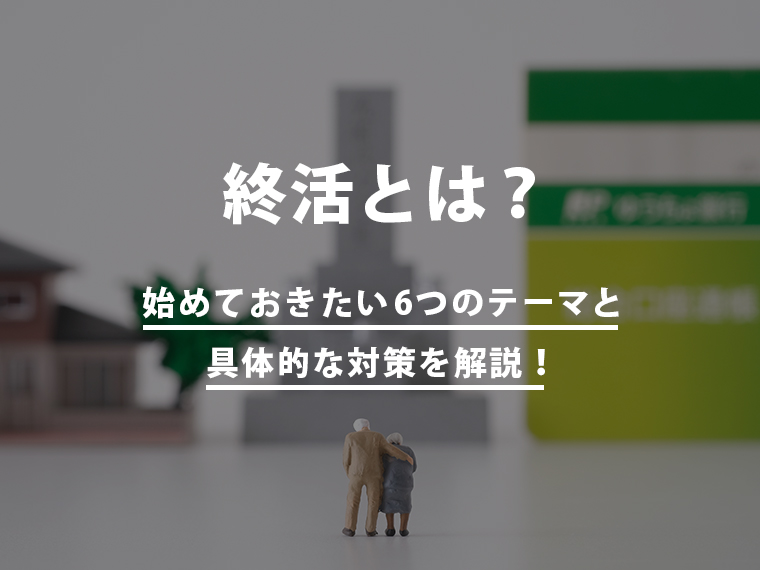共同相続人とは簡単に言うと、遺産分割協議が完了していない段階の相続人を指す言葉です。実は、この共同相続のままではいくつか問題があり、相続人の間でもめる原因となります。今回は、共同相続人について詳しく解説、相続時の注意点についても見ていきましょう。
- 共同相続人とは二人以上の相続人がいる場合に使われる言葉で、共有財産の範囲は限定される
- 共有財産の売却や名義変更は、共同相続人のうち一人ができるものではなく全員の許可が必要
- 相続登記は共同相続でも可能だが、登記費用の負担が増えたり相続人の間でもめたりする可能性がある
共同相続人とはどういうもの?
共同相続人という言葉をご存知ですか? 「法定相続人」という言葉のほうが、相続手続きでは頻繁に使われているかもしれません。共同相続人に関することは、民法898条に明記されています。
まずは、共同相続人とはどういうものか、法定相続人との違いについて見ていきましょう。
共同相続人とは?
共同相続の効力に関しては、民法898条に記載されており、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」、民法899条では「各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する」とあります。
そもそも相続とは、ある方が亡くなったときから発生するものです。そして相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人の財産へと移行します。
ただ、相続が発生した時点では、法律で決められた分割割合はあるものの、実際に誰がどのくらいの割合で相続するのかは決まっていません。この相続が開始して相続財産が分割されていない状態を「共同相続」といい、共同相続をする方のことを「共同相続人」と呼びます。
法定相続人との違いは?
それでは、共同相続人と法定相続人との違いはどこにあるのでしょうか?
共同相続人は、共同相続の状態、つまり相続が開始してから相続財産の分割が完了するまでの期間に使われる呼び名で、相続が開始してからでなければ誰が共同相続人となるのかは確定できません。また、相続人が一人の場合は、共同相続人と呼ばれることはありません。
一方、法定相続人は、「相続が発生した際に相続する権利を持っている人」という意味を持ち、民法に定められているため、誰が法定相続人に該当するのかは明確です。相続が発生する前には、「推定相続人」と呼ばれることもあります。
共同相続される共有財産の範囲
基本的には、相続時に遺産分割される予定の財産が共有財産の範囲で、具体的に言うと、以下のようなものです。
- 預貯金
- 不動産
- 株式などの有価証券
- ゴルフ会員権などの権利
- マンション経営などの賃貸人としての地位や権利
死亡保険や死亡退職金など、受取人があらかじめ決められている「みなし相続財産」は、共有財産にはなりません。
共同相続の注意点

共同相続のままだと、手続きに時間がかかるものや手続きができないものが発生します。そうすると、さまざまな面で支障が出るため、共同相続の状態はできるだけ早く解消するようにしてください。ここでは、共同相続における注意点を紹介します。
共有財産の預貯金を引き出すことは手間がかかる
財産のうち預貯金は、葬儀や生活費として必要なケースもあり、共同相続人のなかには「すぐに引き出したい」と考えている方もいるかもしれません。しかし、預貯金は相続が発生した時点で口座が凍結され、共同相続人の誰かが勝手に預貯金を引き出すことができなくなります。
万一、共同相続の状態で預貯金を引き出さなければならない場合には、共同相続人全員の同意がいるため、共同相続人全員の署名や実印、印鑑証明などの提出が必要です。
ただ、預貯金はほかの相続財産と比べると比較的簡単に相続手続きが完了します。共同相続で預貯金を引き出そうとするより、早めに遺産分割協議を終わらせて相続手続きを完了するほうがよいでしょう。
遺産分割が終わらないと共有財産全部の処分は不可能
共同相続人のうち誰か一人が、共有財産をすべて現金化したりまったく違うものに変えたりすることは不可能です。預貯金のケースと同じように、共同相続人全員の許可が必要となります。
たとえ、一人が手続きすることで相続手続きを簡単にしたい場合も例外ではありません。誰か一人に任せたい場合は、遺産分割協議を行い、相続人の一人に手続きの権限を与え、現金化した資産を相続割合に応じて配分する「代償分割」という方法にする必要があります。
不動産の相続登記は単独でもできるが問題も
共同相続の場合でも不動産の登記に関しては、共同相続人が単独で行える手続きです。ただ、いくつか問題があります。
たとえば、ある共同相続人のうち一人が、自分の権利を確保したいと思って登記の手続きをしたとします。しかし遺産分割協議で、相続割合や相続財産が変わった場合には、あらためて登記し直さなければなりません。2回の登記費用を負担することになるうえ、非効率です。
このほかに、仲のよい共同相続人全員がとりあえず共同相続として相続登記したとしましょう。この段階では、何かあった際には、共同相続人全員で連絡を取り合い、話し合いができるかもしれません。しかし、このうち誰かが亡くなった場合、亡くなった方の相続人が現れます。
比較的交流のある相続人であれば問題ないかもしれませんが、これが孫の世代まで共同相続の状態となると、面識のない相続人と連絡する必要があったり、意見が異なったりと問題が大きくなる可能性があるでしょう。
以上のようなことから、相続登記は共同相続人単独で登記できるものの、単独での登記や共同相続での登記はやめたほうがよいと言えます。
また以前は、相続登記に関して期限がありませんでしたが、2024年4月から不動産取得を知った日から3年以内に登記をしなければ、過料の対象になるため注意してください。
共同相続の状態はできるだけ早く解消しよう
共同相続人同士でこまめに話し合いができる状態であれば、手続きに問題はないと感じる方もいるかもしれませんが、共同相続の状態が続くだけで、大きなメリットはありません。仲のいい関係であっても、むしろ遺産分割協議を進めて相続人や相続割合を確定させたほうが効率的です。共同相続の状態はできるだけ早く解消しましょう。
不動産の相続について相談したい方は、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方