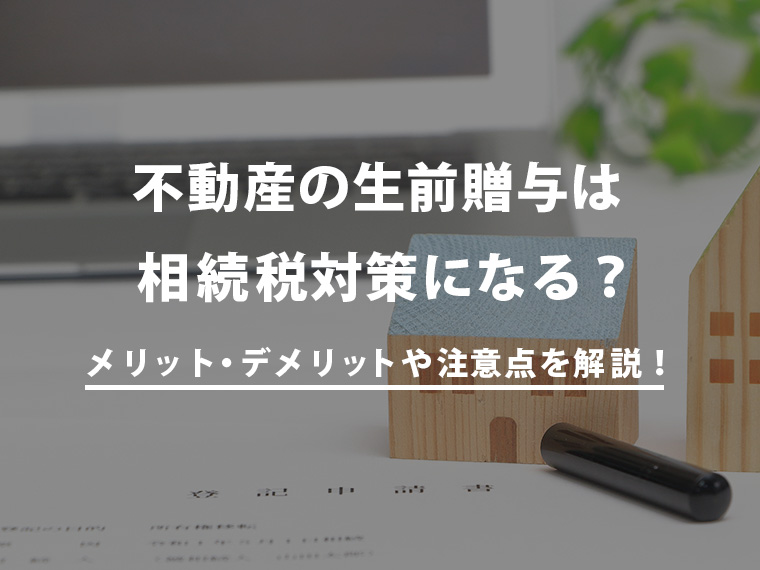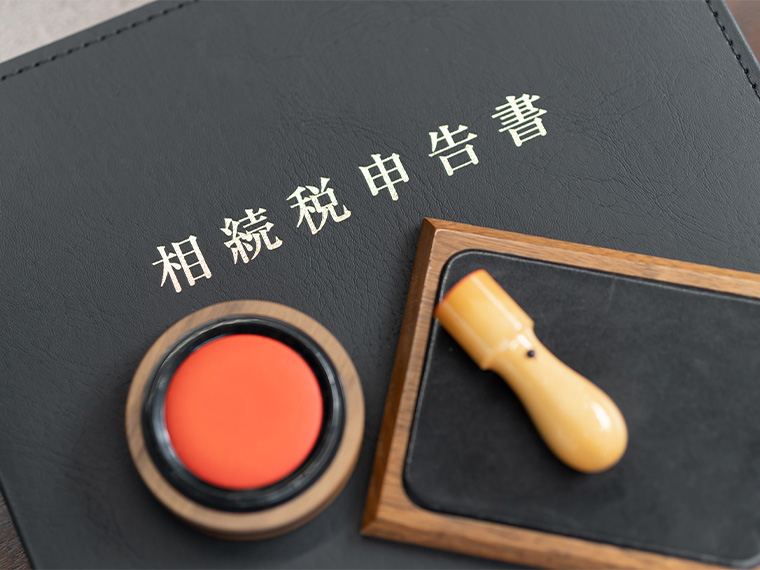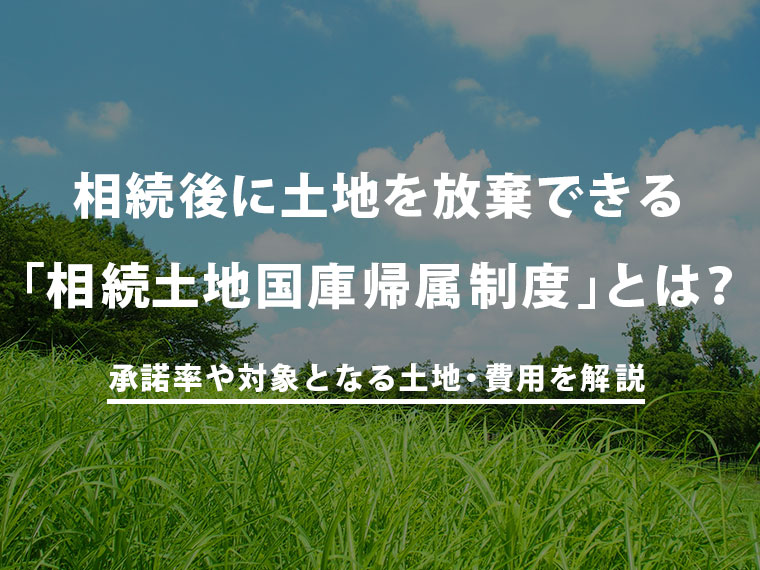- 固定資産税とは、所有している土地や家屋に課された税金のこと
- 固定資産税を算出する際に用いる課税評価額は、土地の用途によって特例措置を受けられる
- 300坪もの土地があれば、土地活用を通じて収益を得られる可能性がある
固定資産税の計算方法
300坪という土地の広さをイメージできるでしょうか?ほとんどの方にとっては、想像がつかないかもしれません。 300坪というと約990平米(㎡)で、学校にある体育館ほどの広さです。 25mプールなら3個分です。 これだけの土地を所有していたら、気になるのが「固定資産税」です。
ここでは、固定資産税の計算方法について見ていきましょう。
固定資産評価額を調べる
固定資産税は、所有している土地や家屋の評価額に対して課税される仕組みです。
まずは、土地の固定資産評価額を調べましょう。 調べ方は主に2つあります。
1つ目は、4月頃に不動産の所有者宛てに届く「固定資産税・都市計画税課税明細書」を確認する方法。2つ目は、所有する不動産がある自治体で閲覧できる「固定資産税課税台帳」や「固定資産評価証明書」を請求して確認する方法です。
固定資産評価額の算出方法は自治体によって異なり、3年に1回見直されます。
固定資産評価額をもとに課税標準額を算出
固定資産評価額をもとに「課税標準額」を算出します。課税標準額は、固定資産税算出時の基準となる金額のことです。固定資産評価額と同じ方もいれば、固定資産税の軽減措置によって税金が減額される方もいます。
課税標準額に税率をかけて固定資産税を算出
課税標準額にかかる税率は自治体によって違いますが、一般的には1.4%です。固定資産税を算出する計算式は以下のようになります。
固定資産税=課税標準額×標準税率
たとえば、課税標準額が1,000万円の土地の場合、標準税率が1.4%であれば、「1,000万円×1.4%」となり、このケースでの固定資産税は14万円です。
住宅用地であれば特例措置を受けられる
居住するための住宅用地として使用しているのであれば、特例措置によって固定資産税を減額することができます。特例の課税標準額算出方法は、以下の通りです。
小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで)
固定資産評価額×6分の1
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
固定資産評価額×3分の1
固定資産税の計算方法で困った場合は、土地がある地域の自治体に問い合わせてみましょう。
広大な土地はどう活用すべき?

先ほどもご紹介したように、土地のままではなく住宅用地にすることで、特例措置を受けられるようになります。また、土地活用によって固定資産税分の利益を出せるケースや、確定申告で経費として落とせる場合もあります。
以下では、広大な土地の活用方法や各方法のメリット・注意点について解説します。
アパート・マンション経営
平均的な一軒家(一戸建て)を建てるのに必要な敷地は40坪ほど。300坪もあれば、アパートやマンションといった集合住宅の賃貸経営も可能です。一軒家を数件新築して賃貸経営するのもよいでしょう。
つねに入居者がいれば、毎月継続して家賃収入を得られるというメリットがあります。しかし、アパートやマンション経営では建物という「箱」が必要なので、初期投資には費用がかかります。また、入居者がいない期間には家賃収入を得られないリスクもあるので考慮が必要です。
事業用定期借地
スーパーなどの商業施設やオフィスなどの事業用地として、貸し出す方法もあります。あらかじめ貸し出し期間を決めた事業用定期借地であれば、期間満了後は所有者が好きなように使うことが可能です。
事業用定期借地であれば建物を建てる必要がなく、地代も住宅用地より高くなります。退去する可能性が低いため、長期にわたって地代を受け取れるでしょう。
ただし、利便性が高い土地でなければ事業用定期借地として貸し出しできないことから、「どんな土地でも該当する」というわけではありません。また、居住用でないと軽減措置が適用されないため、居住用と比べると固定資産税は高くなるというデメリットもあります。
商業施設・オフィス
事業用地としての土地活用方法を紹介しましたが、土地の所有者が商業施設やオフィスなどを建設し、賃貸経営のオーナーとして管理する方法もあります。
毎月のテナント・オフィス賃料を得られますが、事業用なので先述した理由から一軒家よりも固定資産税が高くなります。土地の特性や近隣住民のニーズにマッチしていない施設だった場合、テナントが入らず、安定した家賃収入を得られないこともあります。
グループホームなどの福祉施設
障がい者や高齢者向けの福祉施設にするのも手です。福祉施設の場合、送迎バスを運行させるなどの対策を講じれば、土地の利便性に左右されることもないでしょう。
福祉や介護事業者による長期一括借り上げや、入居契約が持続する場合には、安定した収入となるでしょう。「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」であれば、アパートやマンションと同様に固定資産税が軽減されます。
土地活用を考える際は周辺ニーズの把握がポイント
ここでは300坪の土地を例に活用方法を紹介しましたが、土地の活用方法にはたくさんの選択肢があります。しかし、「金の卵」である土地も、その特性や周辺エリアのニーズなどを読み違えてしまうと、収益が出ないどころかコストだけがかかってしまう恐れもあります。
土地活用を考える際には、さまざまな方法を検討できる不動産会社に相談するのがおすすめです。土地活用に関するご相談は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方