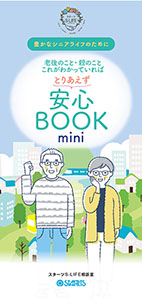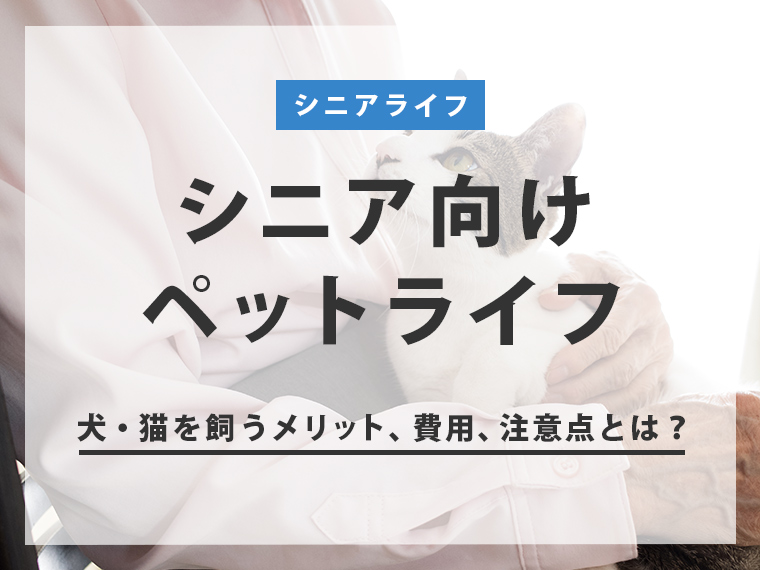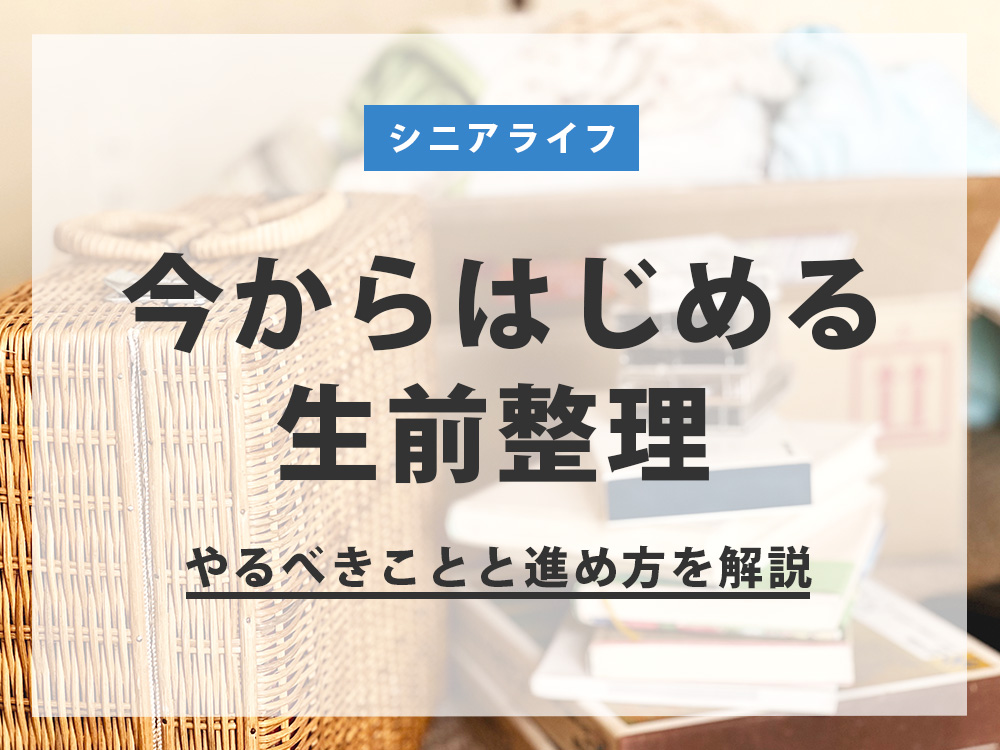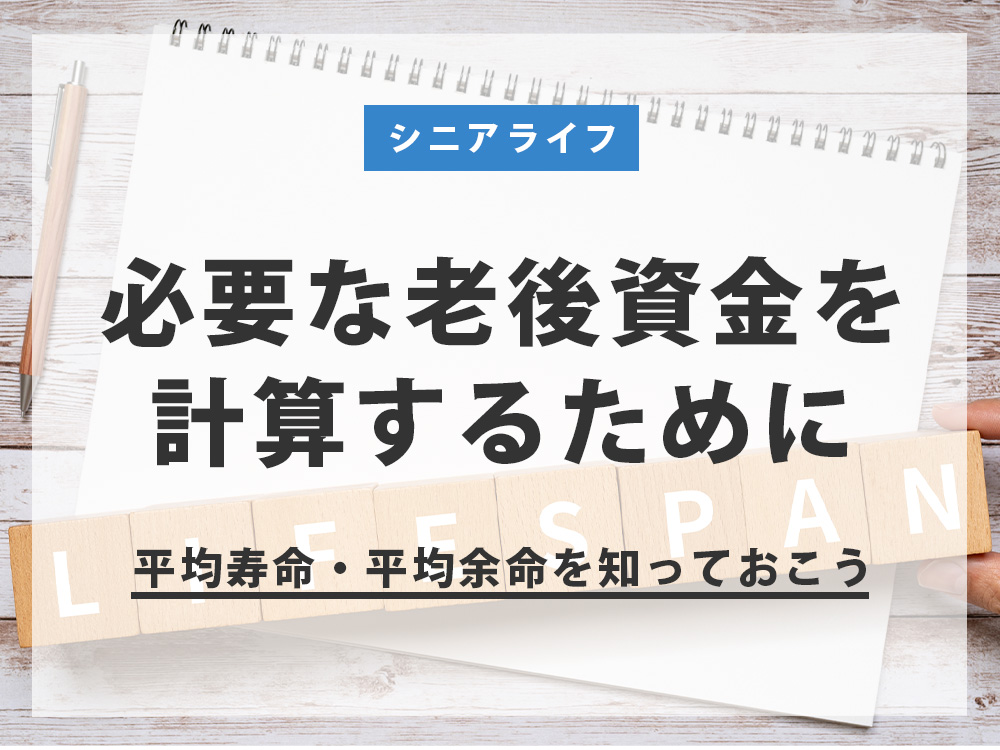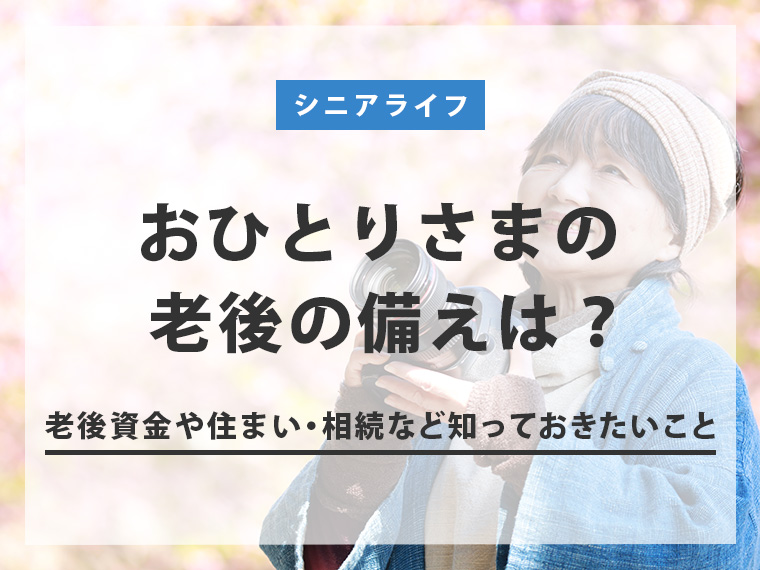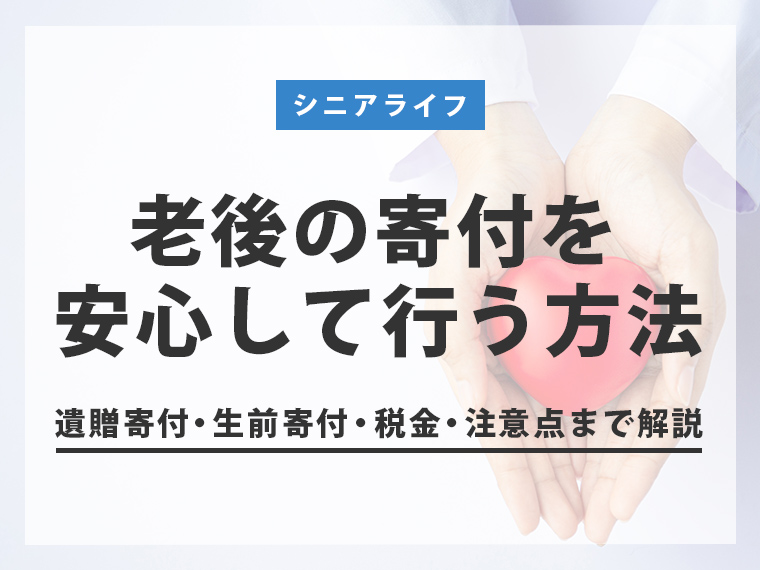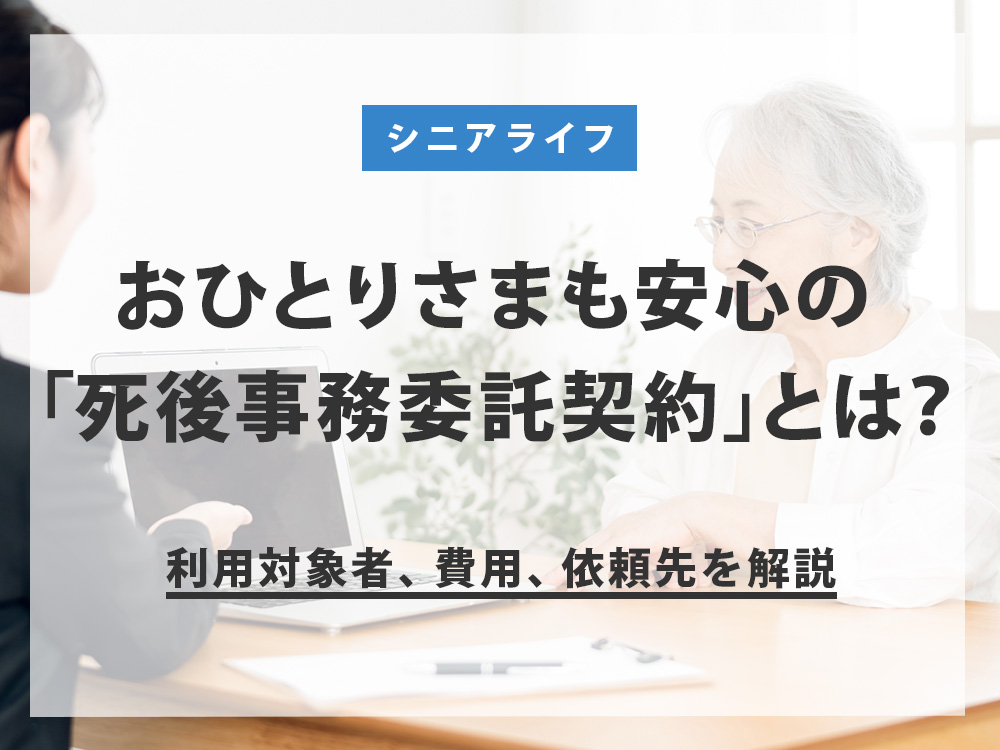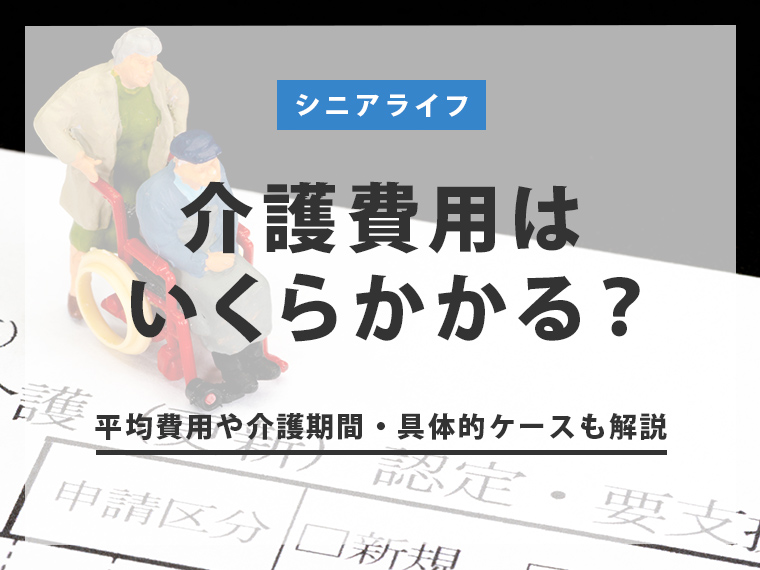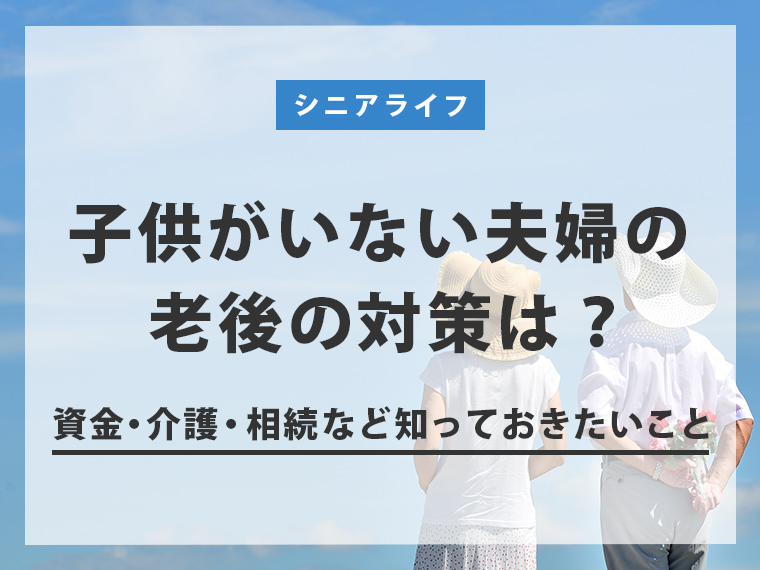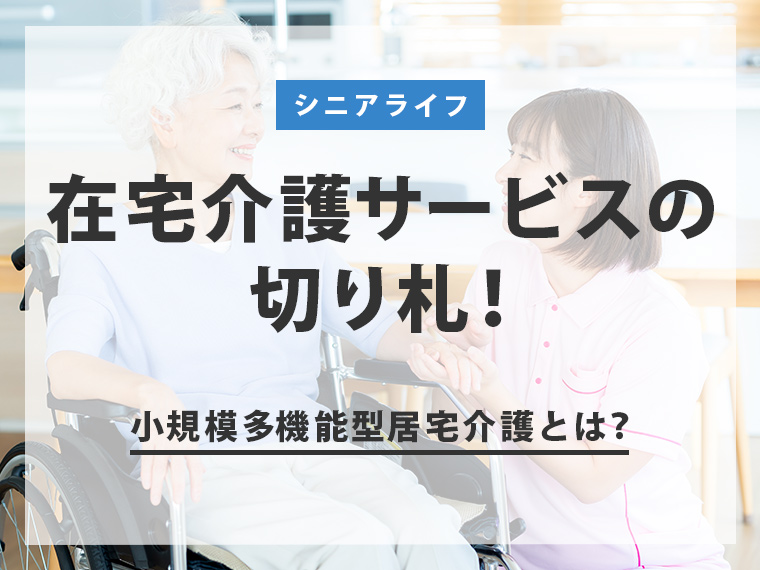ペットは私たちに癒しと喜びを与えてくれる大切な存在です。 万が一飼い主が先立ってしまった場合に備え、飼い主ができる対策やペットの将来を守る方法について詳しく解説していきます。
- 生前に引き取り先を探しておくことが大切
- ペットの情報をまとめて記録しておく
- 負担付遺贈や負担付死因贈与契約、ペット信託なども検討を
「介護」「老後資金」「施設・住まい」
「相続」「老後の暮らし」などの
ご相談が一つの窓口で対応可能
-

通話
無料 - 0120-952-870
受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)
飼い主が孤独死した場合、残されたペットはどうなる?
飼い主が孤独死した際にペットが取り残されるケースは、年々増加しています。 もし、遺族や友人・知人が引き取りをできない場合、ペットはどうなるのでしょうか?
ここでは、動物の引き取り先やその後の処遇について解説します。
動物愛護団体やアニマルシェルターが引き取るケース
亡くなった飼い主に遺族や友人・知人がいない、あるいはその人たちがペットなどの引き取りが難しい場合、動物愛護団体やアニマルシェルターが引き取ってくれる可能性があります。 アニマルシェルターは、動物の保護施設です。 捨てられたり迷子になったりした動物、飼育放棄された動物を保護し、新しい飼い主を見つけるための施設で、主にNPOやボランティア団体などが運営しています。 次項で説明する殺処分が決定した動物を保護・収容するケースもあります。
▼保護されるペットの流れ
- 飼い主の死亡後、警察や自治体がペットを保護
- 動物愛護団体やシェルターへ引き取られる
- 譲渡会などで新しい飼い主を募集
- 飼い主が見つかるまで一時的に保護される
保健所や動物愛護センターが引き取るケース
引き取り手が見つからない場合、保健所や動物愛護センターがペットを引き取ることになります。
保健所では保護した動物のケアなどは行われず、一定の期間をおいて動物愛護センターに引き渡されます。 動物愛護センターでは新しい飼い主に出会うための譲渡会などは行われますが、引き取り先が一定期間見つからない場合などは、殺処分が行われるケースもあります。
▼引き取り後の流れとリスク
- 飼い主がいないペットは保健所で一時的に保護
- その後、動物愛護センターへ引き渡される
- センターでは譲渡会を通じて新しい飼い主を募集
- ただし、一定期間内に引き取り手が見つからない場合は殺処分となるケースも
ペットに悲しい思いをさせないために準備しておくことは?
一人暮らしの飼い主が入院や死亡した際に、ペットが取り残されるケースは珍しくありません。 いざというときにペットが悲しい思いをしないよう、事前の備えが重要です。 ここでは、ペットのために準備すべきことと具体的な対策方法を解説します。
ペットの情報をまとめて記録しておく
引き取り手がスムーズにペットケアできるよう、必要な情報を事前に整理しておきましょう。
▼記録すべき情報
- 名前
- 生年月日
- 性別
- 種類、品種
- 病歴や持病
- ワクチン接種歴、証明書
- 好きな食べ物や生活習慣の注意点
これらの情報は、紙やデジタルメモでまとめ、家族や信頼できる人に共有しておくと安心です。
いざというときの引き取り先を事前に決めておく
万が一に備え、ペットを引き取ってくれる人をあらかじめ探しておきましょう。
▼引き取り先の候補
- 家族や親しい友人
もっとも安心できる選択肢です。 事前に相談し、同意を得ておくことが重要です。 - 里親募集サイトやマッチングサービス
信頼できる新しい飼い主を見つける手段として活用できます。
動物愛護団体・アニマルシェルターと連携する
身近に引き取り手がいない場合は、動物愛護団体やアニマルシェルターに相談するのも有効です。
▼事前に確認すべきポイント
- 引き取りが可能かどうか
- 譲渡条件や費用
- 緊急時の対応体制
早めに連絡を取り、いざというときに備えておくと安心です。
負担付遺贈・負担付死因贈与契約を検討する
ペットの引き取りを確実に行うために、負担付遺贈や負担付き死因贈与契約などを検討するのも一つの手段です。
▼負担付き遺贈と負担付き死因贈与契約とは?
- 負担付遺贈
遺言書で「遺産と引き換えにペットの世話を依頼する」旨を記載する方法。ただし受贈者が断る場合もあるので事前に約束をしておくことが望ましい - 負担付死因贈与契約
飼い主が生前に契約を交わし、死亡時に遺産と引き換えにペットの世話を依頼する方法
負担付遺言の遺言書や負担付新贈与契約の契約書を作成する際は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
死後事務委任契約を締結する
死後事務委任契約を結んでおくと、飼い主が亡くなった後にペットの引き渡しや飼育を第三者に依頼できます。
▼死後事後委任契約で依頼できる内容
- ペットの引き渡しや新しい飼い主への連絡
- 飼育費用の支払い
- 行政手続きや公共料金の精算
事前に信頼できる受任者を選び、契約内容を明確にしておきましょう。
ペット信託で将来の飼育を保障する
ペット信託は、信頼できる人を受託者とし、ペットの世話と費用管理を任せる方法です。
▼ペット信託のメリット
- 飼い主の入院や病気時にもペットの面倒を見てもらえる
- 飼育費用を信託財産として管理できるため、安心して託せる
信託契約は法的な手続きが必要なため、専門家への相談がおすすめです。
まとめ|事前の備えでペットの未来を守ろう
飼い主が万が一に備えて事前に準備しておくことで、大切なペットが悲しい思いをせずに済みます。 ペットの情報を記録し、引き取り先を決めるだけでなく、法的な対策も検討することで、より確実にペットの未来を守ることができます。
ペットと安心して暮らすために、早めの準備を始めましょう。
「介護」「老後資金」「施設・住まい」
「相続」「老後の暮らし」などの
ご相談が一つの窓口で対応可能
-

通話
無料 - 0120-952-870
受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室
シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。
⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方