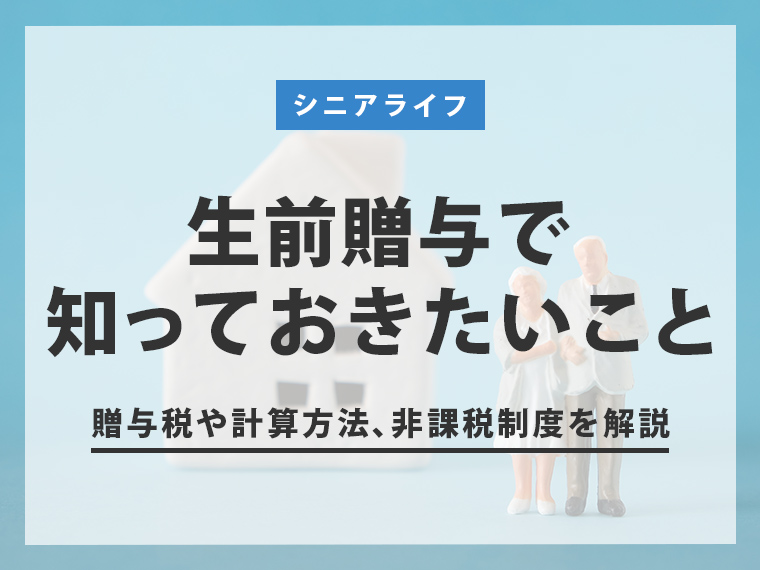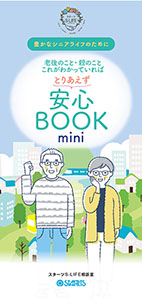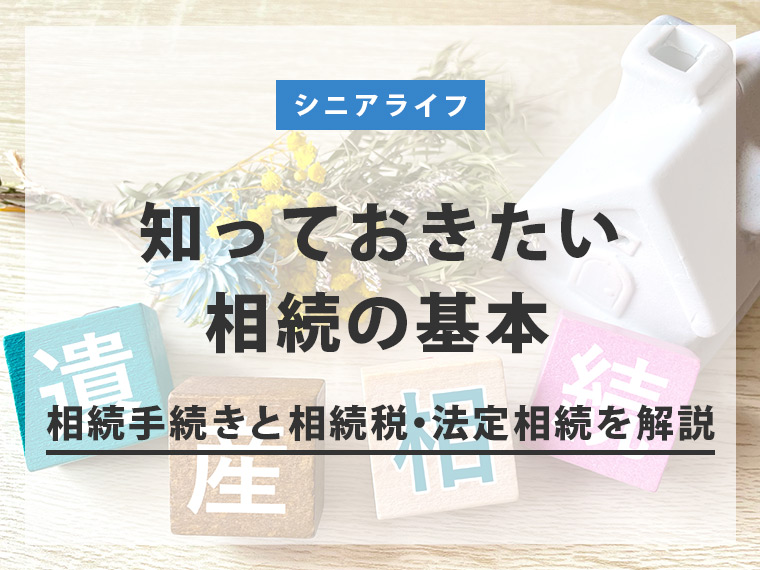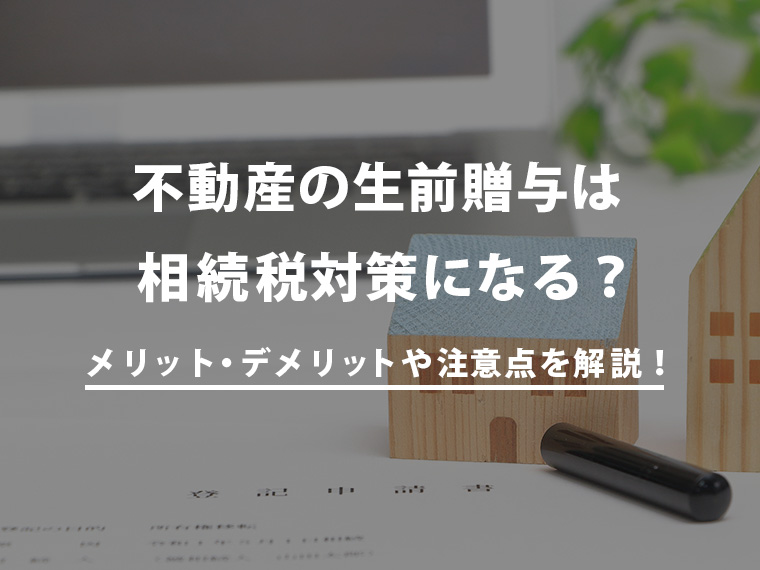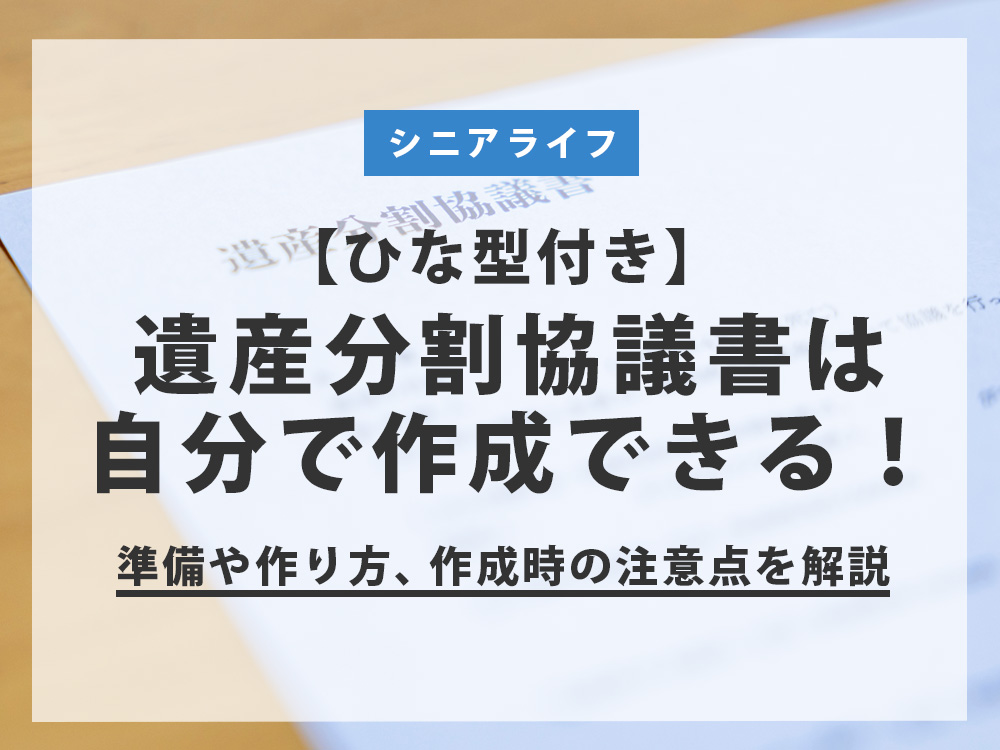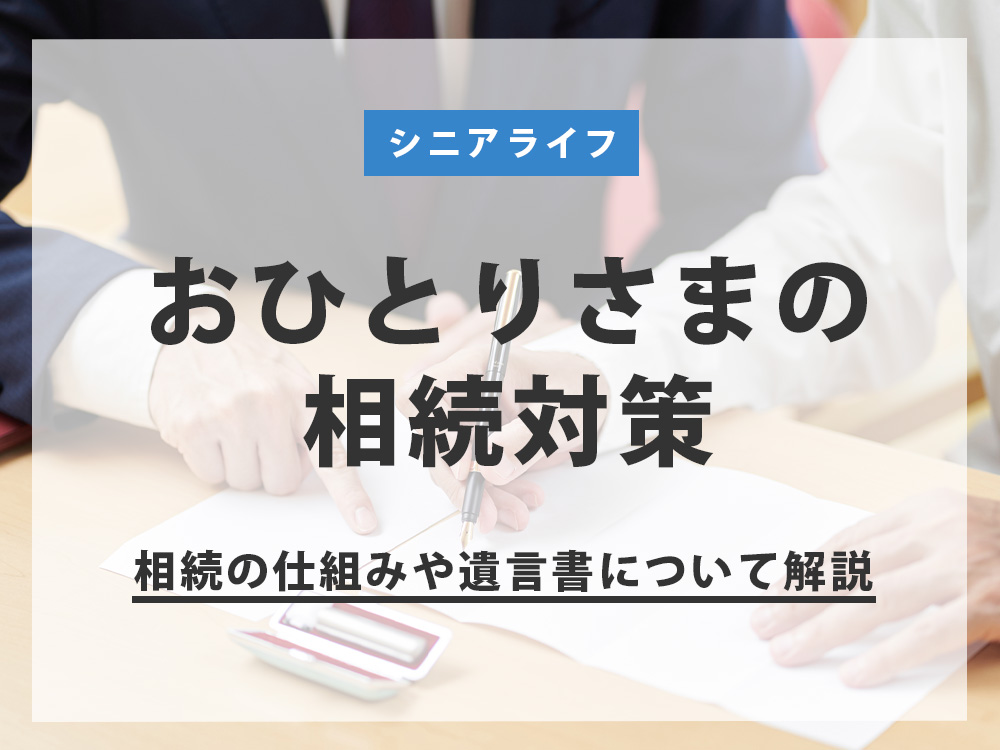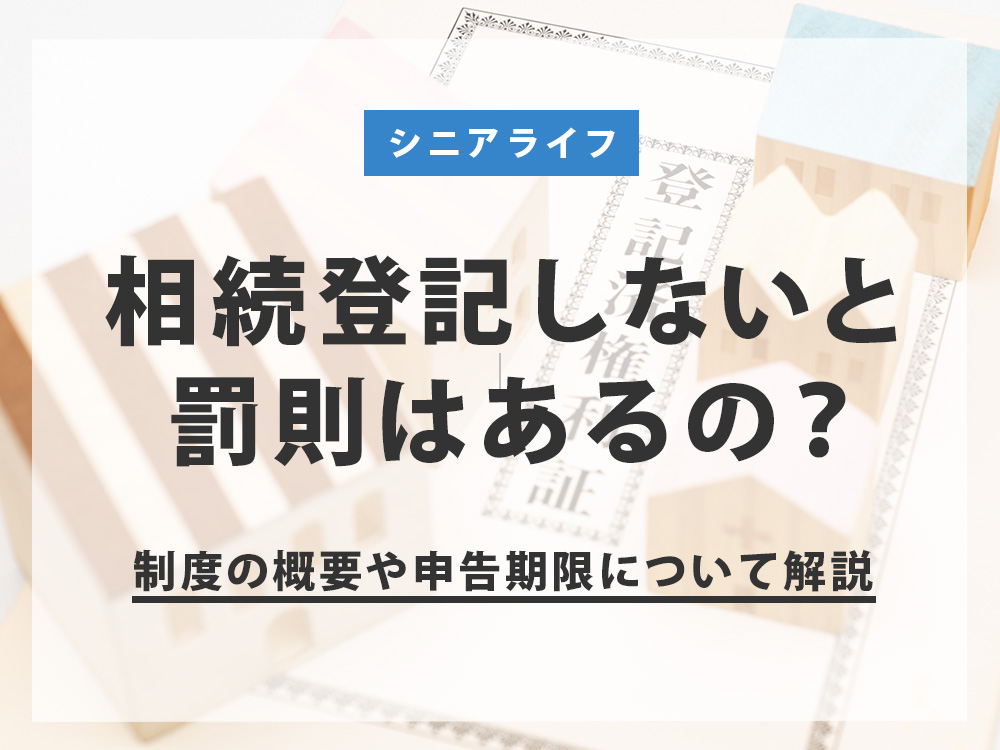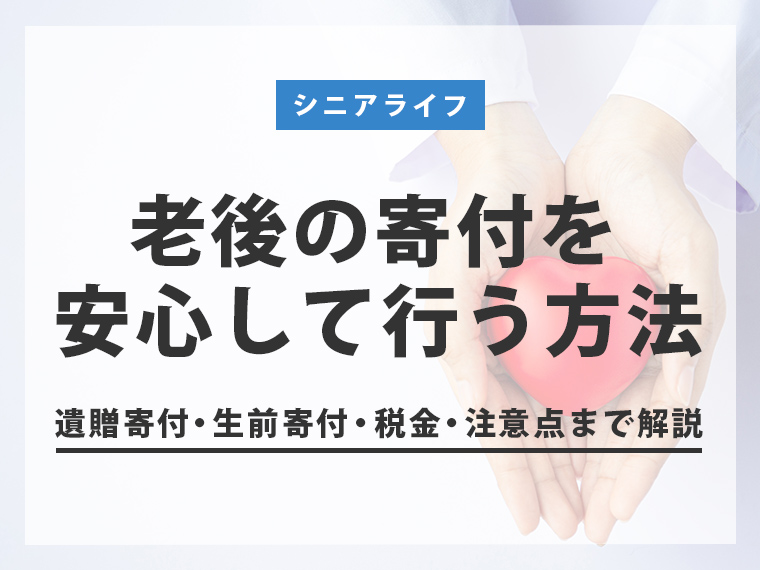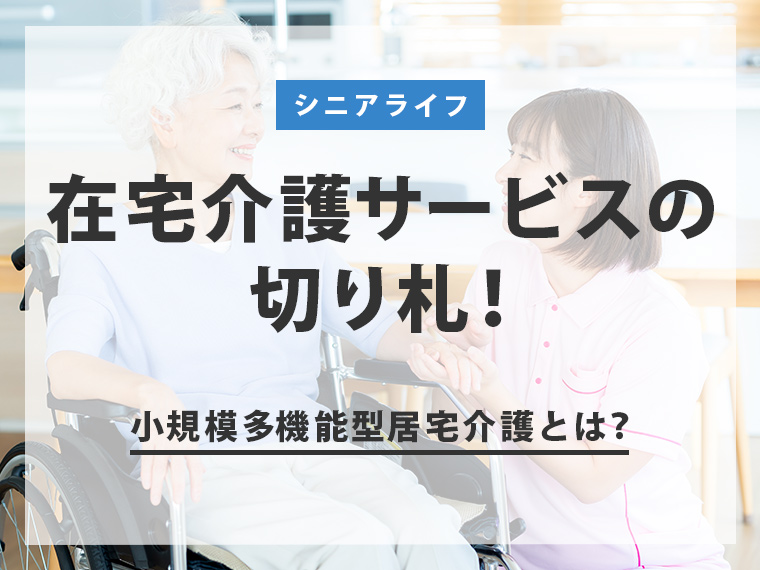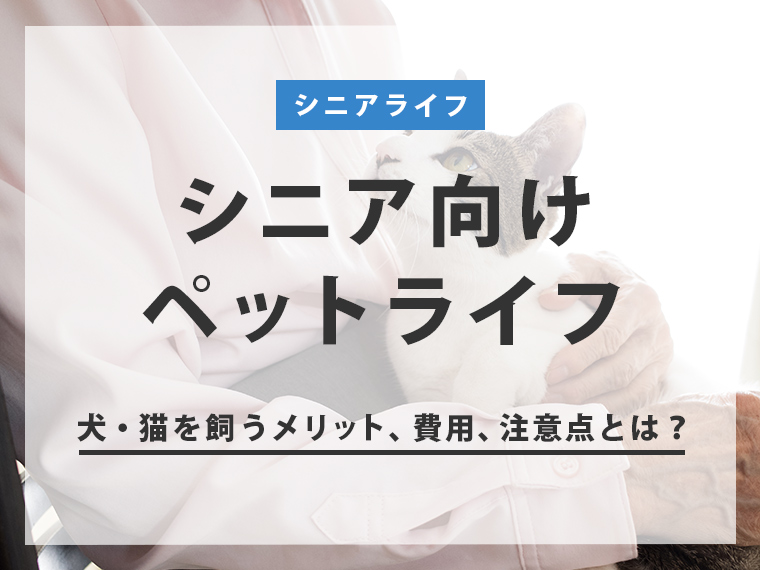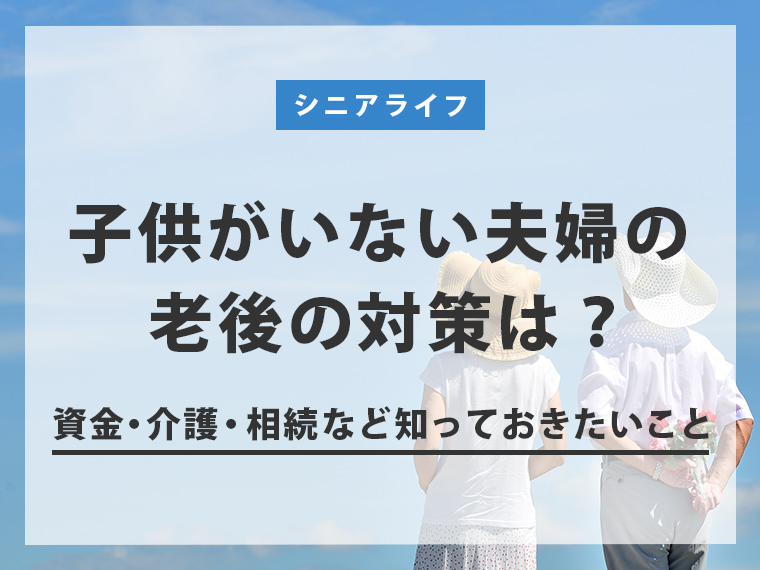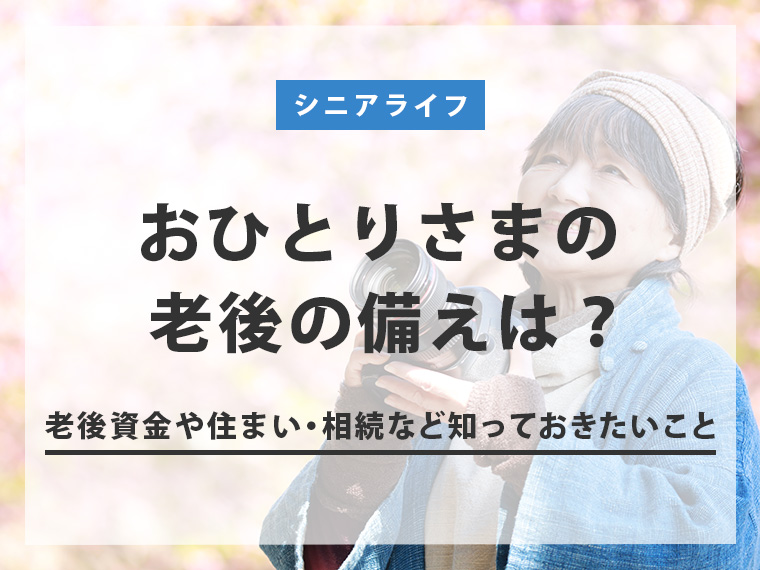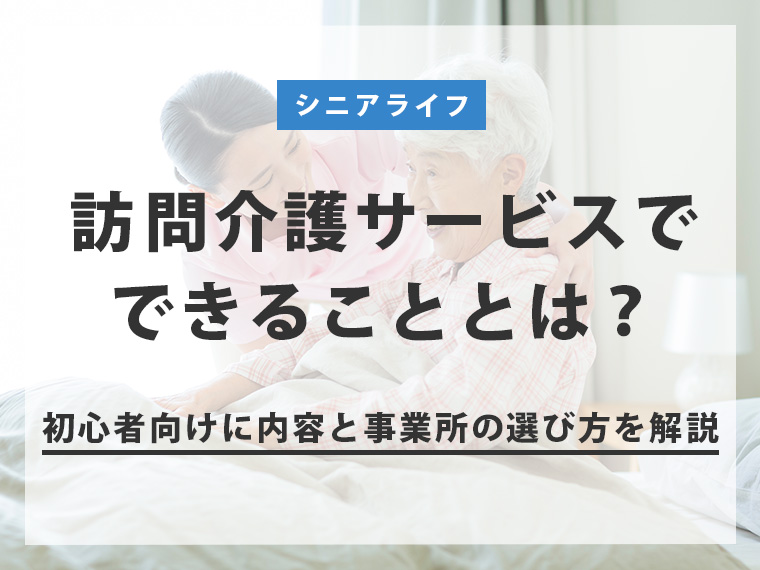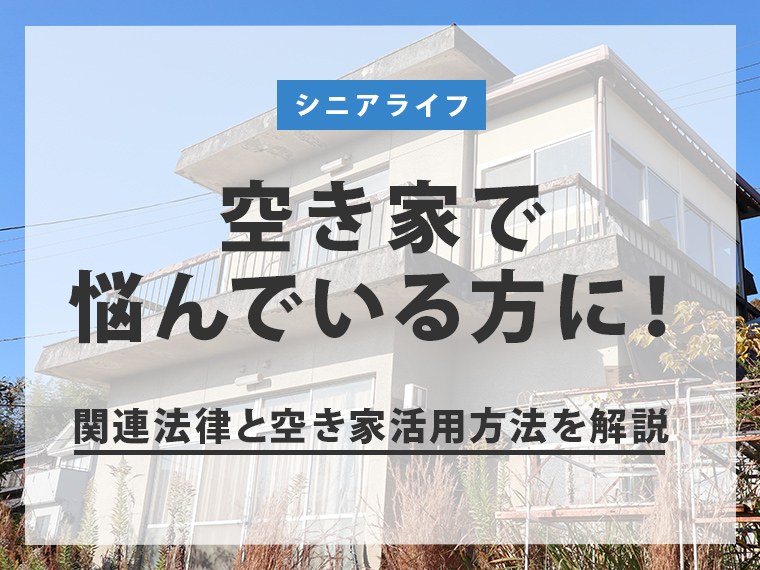- 暦年贈与は年間110万円まで非課税
- 相続時精算課税を選ぶと、累計2,500万円まで非課税
- 教育資金や住宅取得資金など、特例による非課税制度も活用可能
「介護」「老後資金」「施設・住まい」
「相続」「老後の暮らし」などの
ご相談が一つの窓口で対応可能
-

通話
無料 - 0120-952-870
受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)
贈与税の仕組みとは?課税対象者と基本ルール
贈与税とは、個人から財産をもらったときに課せられる税金です。 なお、法人から財産を受け取った場合は「贈与税」ではなく「所得税」の対象となります。
日本の税制では、財産を持つ人が亡くなった際に課される「相続税」とあわせて、財産の移転全体に課税する仕組が整えられています。 つまり、生前に贈与を受けても、相続で財産を取得しても、いずれの場合も税金がかかる可能性があるという点を理解しておくことが大切です。
課税対象となる人
贈与税の納税義務者は、「贈与した人」ではなく、「財産を受け取った人(受贈者)」です。 つまり、贈与によって財産を得た人が税金を支払うことになります。
贈与税の課税方法は2種類(暦年課税と相続時精算課税)
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法があります。 さらに、一定の条件を満たすことで適用できる非課税の特例制度も存在します。
もっとも一般的なのが暦年課税制度です。 暦年課税では、年間110万円までの基礎控除が認められており、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額のうち、110万円を超える金額に対し贈与税が課税されます。
暦年課税とは?贈与税の計算方法と注意点
暦年課税とは、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの額に対して贈与税を課す仕組みです。 つまり、年間110万円までは非課税ですが、それを超えた金額に贈与税がかかります。

注意したいのが、贈与を受けた人が複数の人から財産をもらった場合でも合算して計算される点です。
例えば、父から80万円、母から60万円受け取った場合は、「80万円+60万円=合計140万円」となり、課税対象は110万円を超える30万円に課せられます。
税率と控除額(贈与税の速算表)
暦年課税の贈与税は、基礎控除後の課税価格に応じて10%~55%の累進税率が適用されます。
また、贈与の対象によって以下の2種類があり、それぞれ税率と控除額が異なります。
- 一般贈与財産用(一般税率):
親族以外や兄弟姉妹からの贈与など - 特例贈与財産用(特例税率):
直系尊属(父母や祖父母など)から、子や孫への贈与
一般贈与財産用(一般税率)
一般贈与財産用の速算表は、特例贈与財産用に該当しない贈与の場合に使用します。
主なケースは以下の通りです。
- 兄弟姉妹間の贈与
- 夫婦間の贈与
- 親から未成年の子への贈与
- 親族以外の個人からの贈与
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
参考:国税庁 「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
特例贈与財産用(特例税率)
特例贈与財産用の速算表は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上(令和4年3月31日以前は20歳以上)の人が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合に使用します。
主なケースは、以下の通りです。
- 父母から子への贈与
- 祖父母から孫への贈与
※ただし、夫の父(養父)など、直系ではない親族からの贈与には適用できません。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
参考:国税庁 「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
暦年課税の計算方法
暦年課税の贈与税額は、以下の計算式で求められます。
(贈与財産の合計額―基礎控除110万円)×速算表の税率―速算表の控除額
=税額
▼計算例①(18歳未満の孫への贈与・一般税率の場合)
- 贈与額:500万円
- 基礎控除後:
500万円 - 110万円 = 390万円 - 税率・控除額:
一般税率20%、控除額25万円 - 贈与税額:
390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
▼計算例②(18歳以上の孫への贈与・特例税率の場合)
- 贈与額:500万円
- 基礎控除後:
500万円 - 110万円 = 390万円 - 税率・控除額:
特例税率15%、控除額10万円 - 贈与税額:
390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
暦年贈与の非課税枠と注意点
暦年課税では、毎年110万円まで非課税で贈与できます。
非課税枠を活用して計画的に贈与を行うケースが多いですが、以下の点に注意が必要です。
- 贈与契約書を作成する
口頭や送金のみでは「贈与の意思」が認められない場合があるため、必ず贈与契約書を作成しましょう。 - 受贈者本人名義の口座に振込む
現金手渡しよりも、普段使用している口座に振込む方が「贈与が成立した証拠」になります。 - 相続税の加算対象となる場合がある
贈与者が亡くなった場合、それまでの贈与が相続税の課税対象に含まれることがあります。
なお、相続税の加算対象期間は以下のとおりです。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年1月1日~ 令和12年12月31日 |
令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
出典:国税庁 「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
相続時精算課税とは?ポイントと注意点
相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与に適用できる制度です。 贈与税の支払いを相続が発生する時点まで先送りできるのが特徴で、相続税対策として利用されるケースが多くあります。
- 年間110万円の基礎控除:
暦年課税と同様、毎年110万円までは非課税。 - 累計2,500万円まで非課税:
生涯を通じて合計2,500万円までの贈与が非課税。 - 超過分は一律20%課税:
2,500万円を超えた部分には20%の贈与税がかかる。

相続時精算課税を利用する際の注意点は、以下のとおりです。
- 届出書の提出が必須
相続時精算課税を利用する場合は、所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要がある。 - 暦年課税への切り替え不可
一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、以降「暦年課税」を利用できない(※)。
※ただし、他の贈与者からの贈与については暦年課税の利用が可能。
生前贈与で使える非課税制度まとめ

生前贈与には、上の章で記載した「年間110万円以内の暦年贈与」や「相続時精算課税制度」以外にも、特定の条件を満たす場合に贈与税がかからない特例制度があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住宅取得等資金贈与の非課税枠
子や孫が、父母や祖父母からマイホームの購入費や増改築費用を贈与された場合に利用できる制度です。
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の一般住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。 この制度が利用できるのは「令和8年12月31日」までとなっているので、利用を検討している場合は、期限に注意しましょう。
参考:国税庁 「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
教育資金贈与の非課税枠
父母や祖父母から、30歳未満の子や孫に対して教育資金として贈与された場合、1,500万円まで非課税となります。
対象となる費用は、以下の通り幅広く利用可能です。
- 入学金、授業料、保育料
- 学用品や教材の購入費
- 修学旅行費用
- 学習塾や習いごと(スポーツ・文化活動)
この制度は「令和8年3月31日」まで有効となります。
参考:国税庁 「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
結婚・子育て資金贈与の非課税枠
父母や祖父母から、20歳から49歳までの子や孫に対して、結婚費用や子育て資金として贈与する場合に利用できます。 非課税枠は、以下のとおりです。
- 結婚に関する費用:最大 300万円まで
- 子育て資金:最大1,000万円まで(妊娠や出産、子どもの医療費など)
この制度は「令和9年3月31日」まで有効です。
配偶者控除(不動産や購入資金の贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合に適用されます。 非課税枠は、以下のとおりです。
- 基礎控除110万円+最高2,000万円まで控除(配偶者控除)
この制度を活用すると、最大2,110万円まで贈与税がかからずに不動産や資金を贈与できます。 長年連れ添った夫婦が安心してマイホームを譲渡できる仕組みとして、多く利用されています。
参考:国税庁 「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
まとめ
生前贈与は、生きているうちに大切な人へ財産を引き継ぐことができる制度で、相続税対策や相続トラブルの回避に役立ちます。 暦年贈与や相続時精算課税制度、その他の非課税枠などさまざまな制度を組み合わせて利用することで、贈与税や相続税の負担を軽減し、円滑な財産承継を実現できます。
ただし、それぞれの制度には利用条件や期限があるため、誤った方法を選ぶと余計な税負担が発生する可能性もあります。 最新の税制を確認しながら、専門家に相談して計画的に進めましょう。
生前贈与についてお悩みがある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
「介護」「老後資金」「施設・住まい」
「相続」「老後の暮らし」などの
ご相談が一つの窓口で対応可能
-

通話
無料 - 0120-952-870
受付時間:月~土 9:00~18:00(日・祝日定休)

スターツS-LIFE相談室
シニアの皆さまの暮らしをより豊かなものにしていただくための総合窓口です。日々の暮らしに潤いをもたらすサービスなど輝くシニアライフをお手伝いいたします。
⇒スターツS-LIFE相談室の記事はこちら
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方