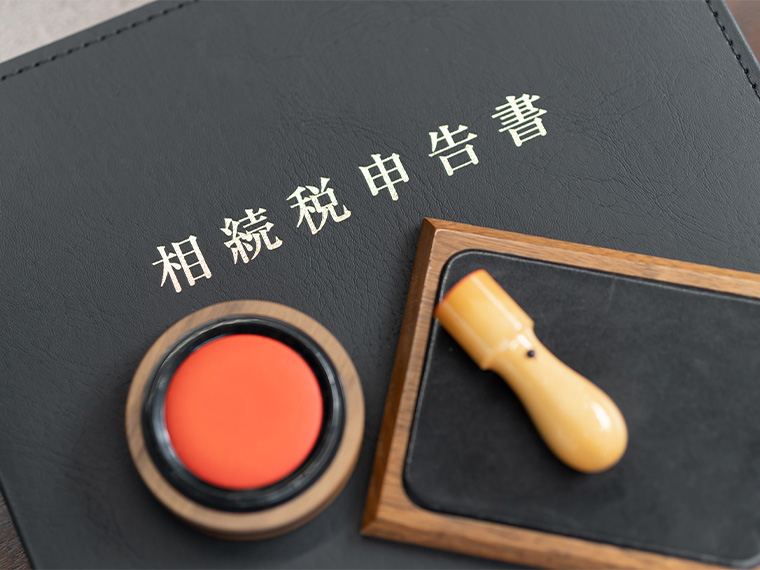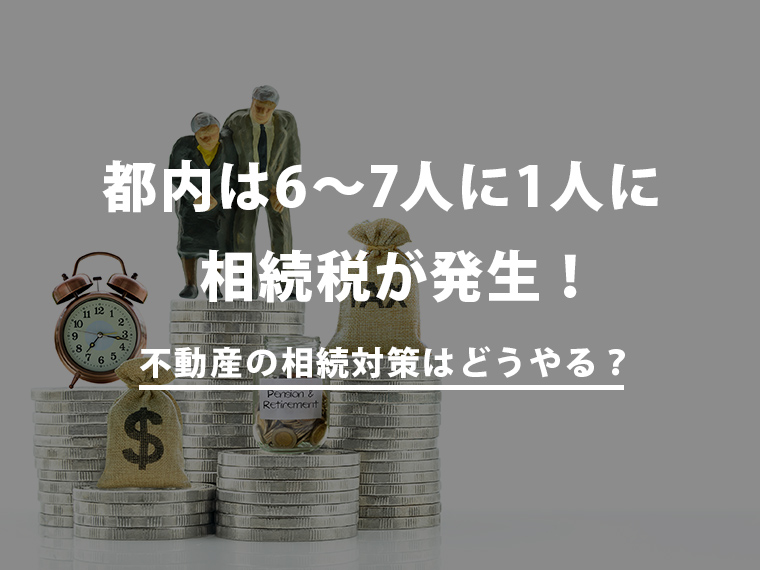- 相続しても相続税が課せられないケースもある
- 基礎控除を超える額の遺産があった場合に相続税が発生する
- 相続税がゼロでも申告しなければならないケースもある
基礎控除の計算式
相続において重要となる基礎控除とはどんなものなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
相続税の基礎控除とは
相続税とは、相続や遺贈によって遺産を得た人が、遺産の評価額に応じて負担しなければならない税金のことです。遺産を相続したら必ず相続税が発生するわけではなく、相続した財産が一定の金額を超えた額にのみ課税されます。一定の額を超えない場合は、相続税の申告手続きも納税もしなくてよい非課税枠に含まれ、このボーダーラインを示すのが基礎控除額です。
基礎控除はすべての相続の対象となるため、まず課税価格の合計額を計算したのちに、基礎控除額を上まわっている場合に申告準備を進めるという流れになります。相続における大半は基礎控除額を下まわり、申告不要となるケースがほとんどです。
ただし、財産の見落としや計算間違いなどにより、申告不要と思っていたのに実際は基礎控除を超えていた場合、延滞税や加算税などが加わり、実際の課税額よりも多く支払わなければならないこともあるため、注意が必要です。
基礎控除の計算方法
基礎控除は、以下の計算方法により確認することができます。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数 )
= 基礎控除額
この式に当てはめて計算し、基礎控除額を把握しましょう。たとえば法定相続人が3人だった場合、3,000万円 +( 600万円 × 3人)という式により、基礎控除額は4,800万円となります。遺産の総合計額が4,800万円を下まわるなら全額控除で申告も不要、総合計額が9,000万円だった場合、4,800万円を除いた4,200万円に対して相続税を支払うことになります。
法定相続人の範囲とは
基礎控除額を算出するには、法定相続人の数を定めなければなりません。法定相続人とは、民法により決められた相続人のことで、家族構成に応じ自動的に決まります。故人の配偶者はどんな場合であっても必ず法定相続人です。配偶者以外の親族は、「子ども→親→兄弟姉妹」という相続順位が決められており、順位の高い人が法定相続となります。
基礎控除算出の際に注意したい点
基礎控除額の算出の注意点として、相続放棄した人がいた場合でも、その人を法定相続人の数に含めて基礎控除額を計算しなければなりません。何らかの理由によって法定相続人の権利をはく奪され相続欠格になった場合は、基礎控除額の計算に相続欠格の対象者は含みません。また、故人の遺言書により、法定相続人以外が遺産を譲り受ける受遺者になることもありますが、受遺者の数は含めずに基礎控除額の計算をします。
申告が不要か判断するときの注意点

相続税の申告をするかどうかを判断するための基準となる基礎控除額ですが、算出の際にはいくつか注意しておかなければならない点もあります。見落とすことのないようきちんと確認しておきましょう。
計上漏れの財産やみなし財産の有無
遺産総額の計算には、故人の遺産をすべて含める必要があります。財産の見落としがあると、相続税の申告が必要かどうかの正しい判断ができないため、慎重にリストアップする必要があるでしょう。
現金や貯金、不動産はもちろん、株などの有価証券や車、美術品、ゴルフ会員権といったものも財産となるため、故人が保有していたかどうか確認しておく必要があります。また、借金やローンといった負の遺産がある場合は、それも合算対象です。
注意すべきは、民法上は相続財産ではないものの、相続税法では相続財産として換算されるみなし財産です。被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険や死亡退職金が、みなし財産の主なものです。もともと故人が保有していたものではないため、計上が漏れてしまう可能性も高いので忘れないようにしましょう。
なお、生命保険と退職手当金には非課税枠があり、すべての金額に対して課税されるわけではありません。生命保険と退職手当金の非課税額は、「500万円×法定相続人の数」という計算式で算出できます。
相続時精算課税制度を利用した贈与の有無
相続時精算課税制度による贈与を受けていた場合、受け取った贈与を相続財産に加える必要があります。相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親または祖父母から20歳以上の子どもや孫への生前贈与について、2,500万円までなら無税で贈与できるという制度です。
こちらの記事も読まれています
課税のタイミングが贈与時か相続時のどちらかになるというだけで、節税効果はほとんどありません。この制度を利用して課税を先延ばしにしていた場合、相続時に税を納めることになります。この制度を利用するかどうかは、子どもや孫自身の選択に委ねられるため、きちんと把握しておく必要があるでしょう。
亡くなる前3年以内の生前贈与の有無
亡くなった段階では個人のものではありませんが、相続税の計算に含めなければならないのが、亡くなった日から3年以内に故人から受け取った贈与財産です。3年以内に贈与を受けている場合は、贈与額を相続財産に加算しなければなりません。
ここで対象となる贈与は、相続や遺贈により財産を受け取った人に対する贈与のみです。相続人だけではなく、生命保険金の受取人や遺言で財産を受け取った人も対象となるので、注意が必要です。
相続税はゼロでも申告が必要な場合も
遺産総額を計算した結果、納める相続税がゼロになることもあるでしょう。ゼロなら申告は必要ないと思われがちですが、相続税がゼロだった場合でも、申告しなければならない以下のケースもあります。
配偶者控除によりゼロになった場合
配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減という特例があります。配偶者の税額軽減とは、配偶者の相続した遺産が法定相続分より少ない、または1億6,000万円より少ない場合、相続税が課されないという特例です。この特例により、配偶者に相続税が発生するケースは少ないでしょう。
配偶者の税額軽減を受けるには、税務署への申告が必須条件です。また、法的に婚姻関係であることや、申告期限までに遺産分割を終えているなど、特例を受けるための細かい規定が用意されており、それらを満たす必要もあります。
小規模宅地等の特例によりゼロになった場合
故人と同一生計により生活していた場合、小規模宅地等の特例により相続税が軽減されることがあります。小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす自宅の土地や事業用地、賃貸用地を相続した場合、一定面積までであれば評価額を最大80%減額できるというものです。
小規模宅地等の特例により不動産の評価額を減額し、相続税がゼロになった場合でも、この特例を利用するための申告が必要となります。また、適用を受けるには、要件を満たしていることを証明する書類を提出しなくてはなりません。
申告しないとどうなる?
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例により、相続税がゼロとなった場合でも、税務署への申告が必要となります。申告しなかった場合、これらの特例を受けられないことに加え、特例を踏まえない額の相続税を支払わなくてはなりません。
また、申告と納付の期限が過ぎた場合、さらに無申告加算税や延滞税がプラスされ、納税額がさらに高額になってしまうこともあります。特例を受けるなら、税務署への申告を忘れないようにしなければなりません。
基礎控除額の確認が相続税における第一ステップ
相続税がかかるかどうかは、基礎控除額を把握することが第一ステップです。遺産の総額を正しく確認し、申告が必要なのか不要なのかをきちんと見極めましょう。相続税がゼロであっても申告しなければならないケースもあるため、自分だけで判断するのが不安なのであれば、一度専門家に相談して、サポートしてもらうと安心です。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方