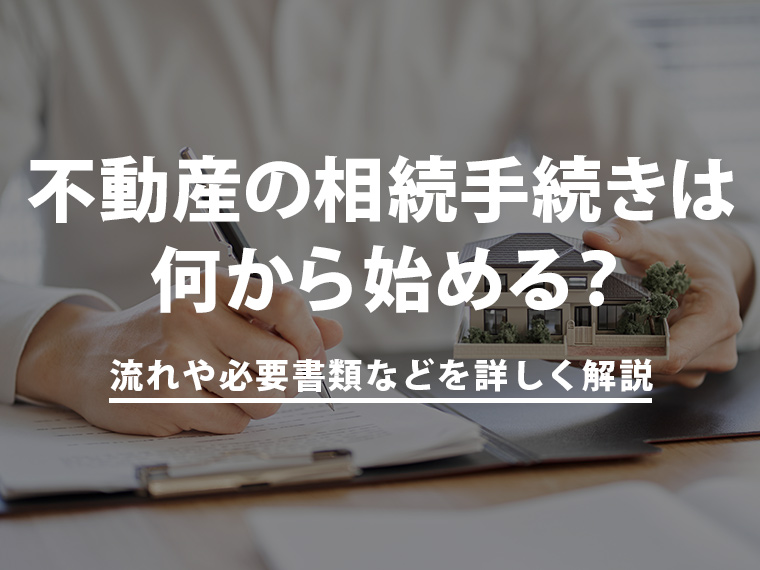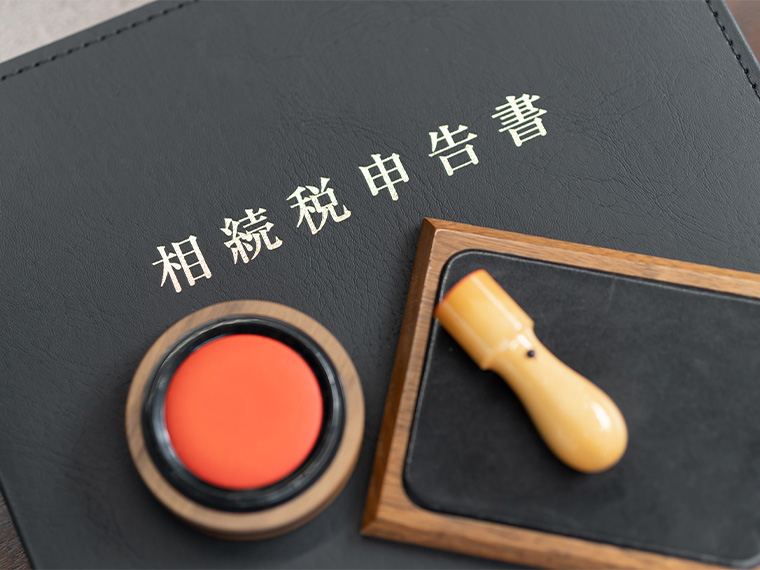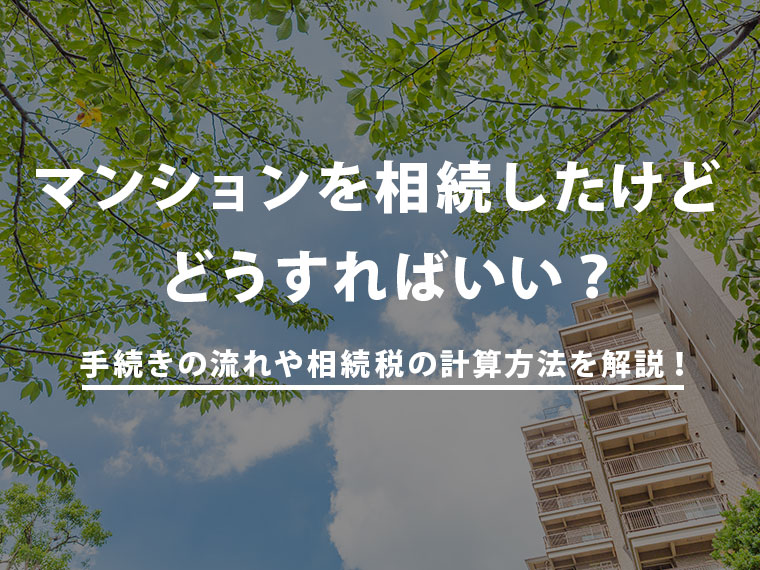- 「配偶者控除」など、一次相続時に適用された特例が二次相続時にはない場合がある
- 10年以内に相続が続く場合は、「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」が適用される
- 二次相続まで見据えた相続税対策が大切
二次相続とは?一次相続との違い
「父」と「母」、「子ども」という家族構成の場合、父親が亡くなると、遺産は母と子どもが相続することになります。まず浮かぶのが「母親のみ」あるいは「母親と子」という形でしょう。
「母親と子」のケースでは母が半分、残りの半分を子どもが相続することになります。そのため、父と母が死亡したときに合計2回の相続が行われることになります。このケースでは、父親から母親と子への相続が「一次相続」、母親から子への相続が「二次相続」となります。
一次相続で母親に相続をするのは、残された母親の生活のためです。一次相続でまず考慮したいのが、母親の生活を守ることでしょう。
一方、長い目で考えると、親世代の遺産が子世代に相続されるまで相続のたびに相続税が発生するため、それぞれの相続でできるだけ納税額を低く抑えたいと考えるのが一般的です。しかし、一次相続において相続税の金額が最も少なくなるようにしたのに、二次相続の分まで含めると負担額が増えてしまうケースがあります。
なぜこのようなことが発生するかというと、一時相続と二次相続では税の軽減制度など、節税につながる制度が同じではないからです。一次相続と二次相続では、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」など節税につながる制度の適用要件が異なります。
二次相続を見据えた相続税対策はある?
相続で損をしないためには、二次相続までを見据えた相続税対策が必要となります。
計画的に生前贈与を行う
相続税の節税対策として、生前贈与は欠かせません。贈与を受けた金額が年間110万円以下は、非課税となるためです。
たとえば、配偶者が一次相続で1,000万円を相続したとします。それを10年かけて子へ毎年100万円を贈与すれば、贈与税および相続税が発生しません。ただし、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の対象となってしまうため、注意が必要です。
二次相続への備えとして、この仕組みを活用しないのはもったいないでしょう。生前贈与は、早めにスタートすることをおすすめします。
配偶者の資産は増やさないようにする
配偶者控除とは、配偶者の法定相続分相当額、あるいは1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税が課せられないという制度です。ところが、二次相続では配偶者が相続人でないため、この制度が適用されません。
よって、「配偶者控除を適用させればお得だから」と、配偶者に大きな金額を相続して資産を増やしてしまうと、二次相続で負担増となりかねないため、注意しましょう。
一次相続で宅地を同居の子に相続する
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人と一緒に住んでいた親族が相続する場合に、宅地の評価額を一定面積まで最大で80%減額できる制度です。
ただし、80%の減額を受けるにあたっては要件が厳しくなるので注意が必要です。たとえば、相続予定者が実家から離れて暮らしていた場合や被相続人の死亡後に転居した場合、二次相続時には小規模宅地等の特例を使用できないケースがあります。
なお、住宅が「賃貸併用」であれば、賃貸部分の評価額が減額されるため、自宅のみ相続の場合より相続税を減らすことができます。
生命保険に加入する
亡くなった人が生命保険に加入していた場合、相続人に保険金が支払われるケースがあります。その際、相続人が取得した保険金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税扱いとなります。そのため、この非課税枠を利用した一時払い終身保険に加入することで、課税対象となる財産額を減らすことが可能です。
二次相続特有の「相次相続控除」とは?
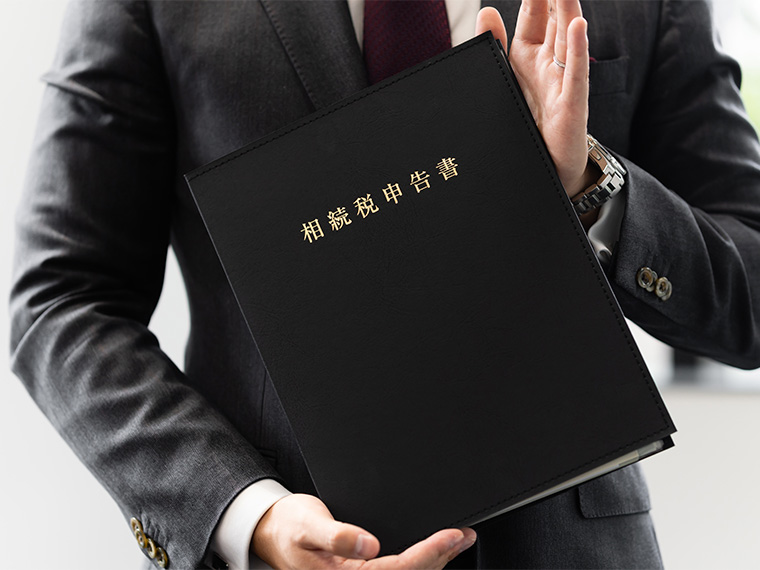
ただでさえ高額となる相続税。もし、短期間に相続が続くようなことになれば負担は大きいでしょう。そういった負担の重さや、同じ財産に課税が二重にされることを考慮し、設けられているのが「相次相続控除」という制度です。その名のとおり、相次いで相続が重なったときのための特例で、10年以内に相続が続けて発生した場合に、加重負担を減らすことができます。
たとえば、祖父が死亡し、父が相続。その父が祖父の死後10年以内に亡くなって再び相続が発生するケースなどです。その場合、二次相続時に納付する相続税から、父が相続によって課税された相続税の一部を控除できます。控除額は経過年数に応じて1年で10%減額されるため、前回の相続から期間が短いほど控除額が大きくなります。
二次相続まで見据えた相続税対策が必要
相続税は金額が大きいことから早めに対策を行うことが大切です。たとえ一次相続で相続税を抑えようとも、二次相続時に特例が適用されないなどの理由で、結果的に負担が大きくなってしまうケースがあります。ぜひ二次相続まで見据えた相続税対策を行いましょう。
二次相続についてより詳しく知りたい方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方