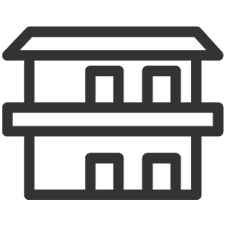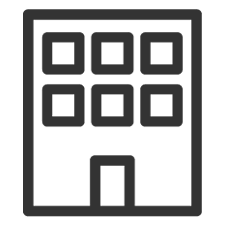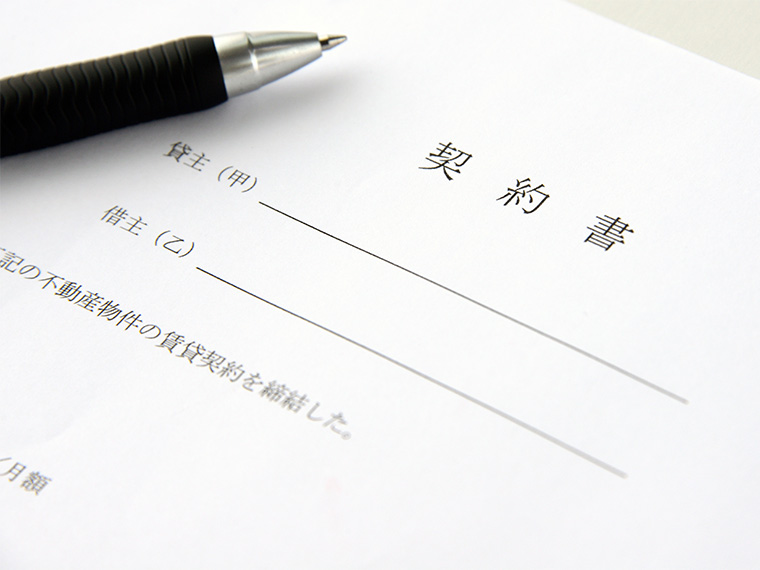日本の耐震基準は、大きな地震の影響を受けて変容してきました。最新の耐震性を自宅に導入して、もっと安心できる暮らしを手に入れてみませんか?耐震基準を満たした家に住むと、住宅ローンの控除を受けられるといったメリットもあわせてご紹介します。
- 安全な建物を作り災害時でも人々の命を守るために定められているのが耐震基準
- 大きな地震をきっかけに何度も耐震基準が作られ、より安全な建物を作れるようになった
- 耐震性を見るときには建築時期がいつなのか、建物の形状に着目
スターツ証券のお問い合わせページに移動します
日本は「地震大国」と呼ばれるほど、地震による災害が多く発生する国ですが、自宅の地震対策は万全でしょうか。いつ発生するかわからない地震に備えて、最新の耐震構造を取り入れれば、もっと安心できる暮らしが手に入るはずです。
この記事では、耐震基準の歴史や耐震性能に関する知識について解説します。専門知識がなくても耐震性を簡易的に判断できるポイントについても触れていきますので、自宅の耐震性を確かめてみてください。
耐震基準が作られた背景
地震が頻繁に起こる「地震大国」の日本では、安全な建物を作るための建築基準法が定められています。阪神淡路大震災など、大きな地震が起きるたびに耐震性が見直され、新しい法令に生まれ変わってきました。
1980年代に設定されていた旧耐震基準時代では、建物の崩壊を避けることに重点が置かれていました。その理由としては、1948年に発生した福井地震で、建物の崩壊により多くの死者が出たからです。地震が起きても崩壊しない建物を作るための基準が設けられていました。
しかし頻繁に起こる程度の地震では建物に損傷が出にくいことから、1981年に改正された新耐震基準では、「大きな地震から人命を守ること」が目的に掲げられました。建物ではなく人命を守ることに重きを置いたことから、耐震基準が大幅に引き上げられ、耐震性を測る指標などが導入されたのです。
建築時期によって耐震性能に差がある
先述した通り、大きな地震を経て耐震性が見直され、基準が改められてきました。そのため、いつどの基準に沿って建てられたものなのかによって耐震性能に差が出てきます。
1981年以前の建物は旧耐震基準に従って作られており、大地震の際に建物が崩壊しないような基準を設けていました。実際は、震度6程度で建物が崩壊する可能性が高いと言われています。
1981年から2000年の間に建てられた建物は、人命を守ることに重きを置いた新耐震基準に従って作られています。また、2000年6月以降は地盤仕様が明記されるようになりました。人命を守ることはもちろんのこと、最新の技術が導入されているので、最も頑丈で安全な建物と言えるでしょう。
2000年5月以前に建てられた建物は耐震診断を受けて、補強やリフォームをしておくと万が一の事態に備えることができます。
耐震基準の切り替え直後に建てられた住宅の耐震性能は?
1981年の6月1日に、旧耐震基準から新耐震基準に切り替わりました。ここで注意したいのは、1981年6月1日に完成した建物が新耐震基準を満たしている建物だとは限らないということです。
建物を建てる前には、建築計画に法律違反の箇所がないか審査を受ける必要があります。この審査に合格して建築確認された日付を見ると、いつの耐震基準に従った建築物なのかを判断することができるのです。そのため、ここの日付が1981年6月1日以降でないと、新耐震基準を満たしているとは言えません。
旧耐震基準の時期に建てられた物件でも新耐震基準を満たしている物件はある?
旧耐震基準の時期に建てられた物件でも、新耐震基準を満たしているケースがあります。耐震基準はあくまでも最低限のラインであり、上限が決められているわけではありません。
そのような建物の特徴は、低層のマンションやシンプルな箱型の家が挙げられます。低層のマンションでは、壁が厚くなっていることが多いので衝撃に強いのです。また、箱型の家だと、L字型やコの字型に比べて安定感があるので、新耐震基準を満たしている物件である可能性が高くなります。
実際に対象となる建物がどの耐震基準を満たしているのかを知りたいときには、専門家による耐震診断を受ける必要があります。
お問い合わせページに移動します
地震に強い構造とは

建物の地震対策には3種類あり、建築構造によってどのように地震から人命を守るのかが分かれます。最もオーソドックスな地震対策が、「耐震構造」です。地震の揺れを受けても崩壊しないような、高い強度の構造で建物を設計する方法です。
2つ目の「制震構造」は、建物のなかに重りやバネのようなものを組み込んで、制震装置として揺れを低減させる設計方法です。地震が起きたときに、制震装置がエネルギーを吸収してくれるので、建物全体の揺れを抑え、崩壊を防ぎます。
3つ目は「免震構造」で、建物と地面の間にゴムなどを入れるのが特徴です。建物と基礎になる地面を切り離すことで、直接的に地震エネルギーが伝わりません。そのため、地震による揺れを軽減でき、建物の崩壊を防ぐことができます。
これらの3種類の地震対策構造は、組み合わせて採用されることもあります。たとえば「耐震構造と免震構造」「耐震構造と制震構造」といったように、組み合わせることで耐震性を引き上げることができます。
熊本地震では、100年に1度と言われていた震度7の大地震が2日間で2度も起こりました。「耐震等級3」を満たしていた建物は、1度目の揺れは耐えましたが、2度目の揺れには耐えられませんでした。この結果を受けて、「耐震」だけでは地震対策としては不十分であると考えられたのです。「耐震構造」の強度は高いですが、地震エネルギーをダイレクトに吸収してしまいます。そこで、地震エネルギーを逃がすような「免震構造」「制震構造」が発展してきました。
耐震等級とは?
地震に対する強さを段階的に表したものが、耐震等級と呼ばれるものです。家の購入や建築を検討している方であれば、1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。耐震等級を見ることで、どの程度の地震に耐えられる建物なのかを判断することができるので、住宅を選ぶ際は必ず確認したいポイントです。
耐震等級1
地震に対する強さが弱いのが耐震等級1です。現在の建築基準法と同じレベルで建築され、最低限の耐震性能が備わっています。100年に1度くると言われているレベルの地震が来ても、建物が大破・崩壊しない程度の強度がある建物です。
耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の強度がある建物です。大きな地震にも耐えられるような耐震性能を持っています。災害時に避難所になる学校や病院などは、耐震等級2以上と定められているので、避難所の多くは耐震等級2と考えて問題ありません。
耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の強度がある建物です。災害時に拠点となり、人命を助けるための設備である消防署や警察署は、耐震等級3でなくてはいけないと決められています。
耐震基準適合証明書について
建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類が、「耐震基準適合証明書」です。この証明書は、国土交通省によって認められた性能評価機関や検査機関、建築士登録をしている住所に所属する建築士のみが発行できます。
専門家は、耐震診断を行い、その結果に応じて「崩壊しない」「一応崩壊しない」「崩壊する可能性がある」「崩壊する可能性が高い」の4段階で判定をします。「崩壊しない」「一応崩壊しない」と判断された場合には、耐震基準適合証明書の発行が可能となりますが、「崩壊する可能性がある」「崩壊する可能性が高い」と判断されてしまうと、補強工事をしなくてはなりません。
古い住宅で暮らしていく場合や、自宅の耐震性が気になる場合には、専門家に相談して耐震診断を受けてみるといいでしょう。自治体によっては、無料で耐震診断ができたり、補強工事に補助金を給付したりといった措置が取られています。条件を満たしている場合には、身の安全のために耐震診断を受けてみてはいかがでしょうか。
耐震基準を満たすメリット

耐震基準を満たす建物で暮らしていれば、安心感を得られることが最大のメリットでしょう。地震大国である日本で生活していく以上、地震にあうことは避けられません。そのほかにも、耐震基準を満たすことで住宅ローンの控除を受けられるなどのメリットがあるので、それらについて詳しく解説していきます。
住宅ローンの控除を受けられる
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローンの年末残高の1%(最大40万円)を10年間、所得税や住民税などの一部を控除できる制度です。収入が多ければ多いほど、減税効果が高くなるので、高所得者こそ利用がおすすめです。
住宅ローンの控除を受けるには、住宅の引き渡しから6ヶ月以内に入居すること、床面積や50㎡以上あることなどの要件が決まっています。それらの要件を満たしたうえで、提出書類を確定申告時に税務署へ提出しなくてはなりません。
1年目の確定申告は手間や時間がかかりますが、2年目以降は提出書類が減るので大きな負担ではないでしょう。
すまい給付金
耐震性能を満たしていると、すまい給付金を受け取れる可能性があります。床面積が50㎡以上(※)あること、5年以上の住宅ローンを組んでいること、工事や売買の検査で品質が確認されている住宅であることなどの条件を満たした人を対象に、給付金を支給する制度です。
住宅ローンの控除制度とは違って、収入が少ないほど給付額が高くなります。10万円から50万円の間で給付金額が決まるので、経済的な負担を軽減することができるでしょう。
※契約締結日、建物種別(注文住宅、既存物件)によっては40㎡以上に緩和されるケースも
耐震構造についてのチェックポイント
賃貸住宅において耐震構造をチェックするポイントについて解説していきます。建築に関する専門的な知識がなくても確認できるので、住まいを探す際は実践してみてください。
分譲マンションの場合は、耐震診断を受けるか否かは管理組合によって決断される場合もあります。個人では判断できないことがある点も心にとめておきましょう。
建築年数は1981年以前なのかそれ以降なのか
先述した通り、建物を建てる際には基準とされている耐震性能を満たさなくてはなりません。建築年によって耐震基準が異なるので、大まかな耐震構造を把握することができます。
まずは建築確認が行われた日程について、不動産会社へ確認してみてください。1981年6月1日よりも前の日付であれば、耐震性は期待できません。ただ、建物の年数と同じように耐震性も老朽化します。1981年6月1日以降に建てられたものでも、長い年月が経っている場合は注意が必要です。
建物の形状を確認してみる
建物の形状も耐震性を左右する重要なポイントです。最も地震に強いのは、長方形や正方形の箱型の家です。反対に地震に弱いのは、コの字型やL字型の家など、特定の部分に地震のエネルギーが集中するタイプです。エネルギーが偏ることで建物が崩壊する危険性が高いので、注意が必要です。
また、1階にガレージや倉庫があるような建物は、空洞化によって家を支える柱が少ない傾向にあります。より高い耐震性を追求したい方は、なるべくエネルギーの偏りが出ないような形の建物を選ぶことをおすすめします。
耐震性を意識した家づくりや物件探しを目指そう
頻繁に地震が起こる日本で暮らしていくには、耐震性に優れた建物を選ぶといいでしょう。耐震基準は1981年ごろから定められていますが、大きな地震による経験を生かして何度も改定されてきました。技術も進歩したことで、高い耐震性を誇る建物が多く建つようになったのです。
そうはいっても昔からある建物がなくなるわけではありません。より安全な生活を送るためにも、耐震診断を受けてみたり、補強やリフォームをしたりと耐震性を高める行動が必要になってくるでしょう。この機会に、ぜひ耐震性にすぐれた物件を探してみてください。
お問い合わせページに移動します
あわせて読みたい
よくある質問
-
お部屋探しに役立つ情報はありますか?
-
物件探し(不動産購入・売却)について役立つ情報はありますか?
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方