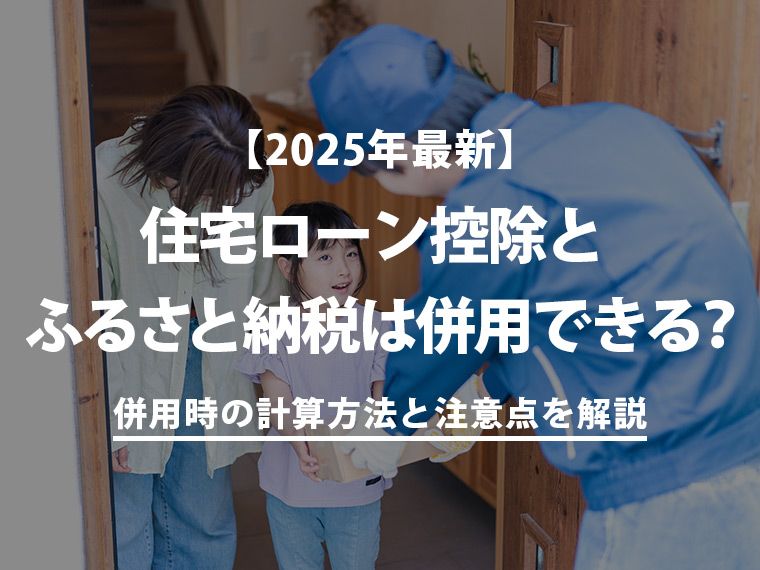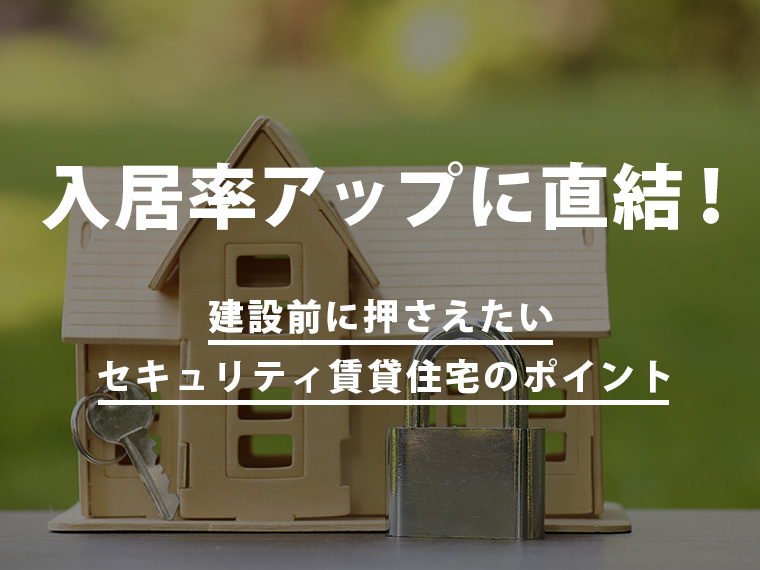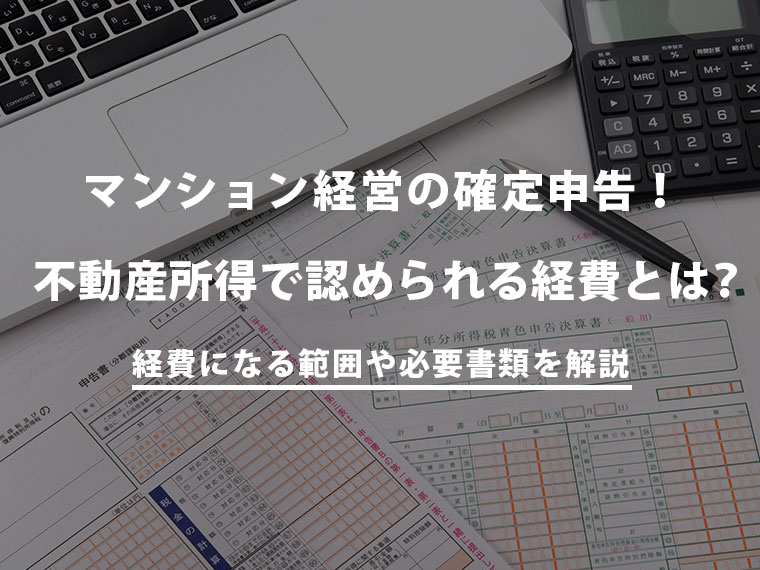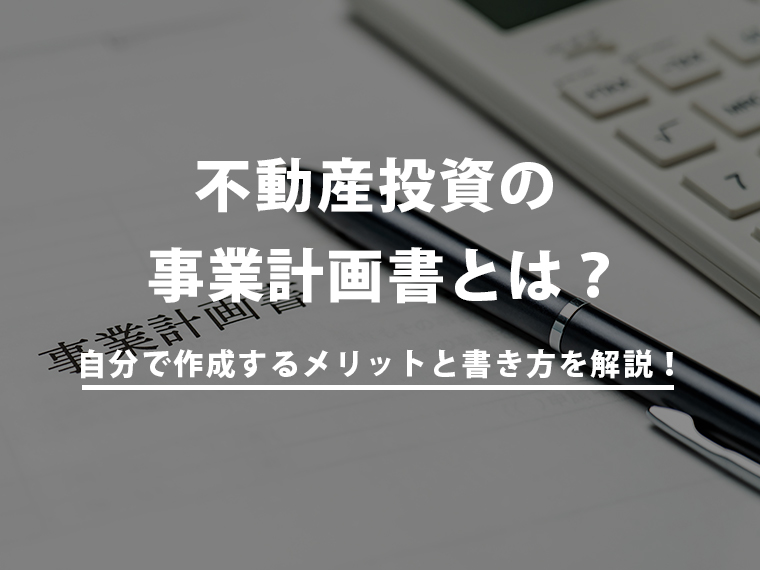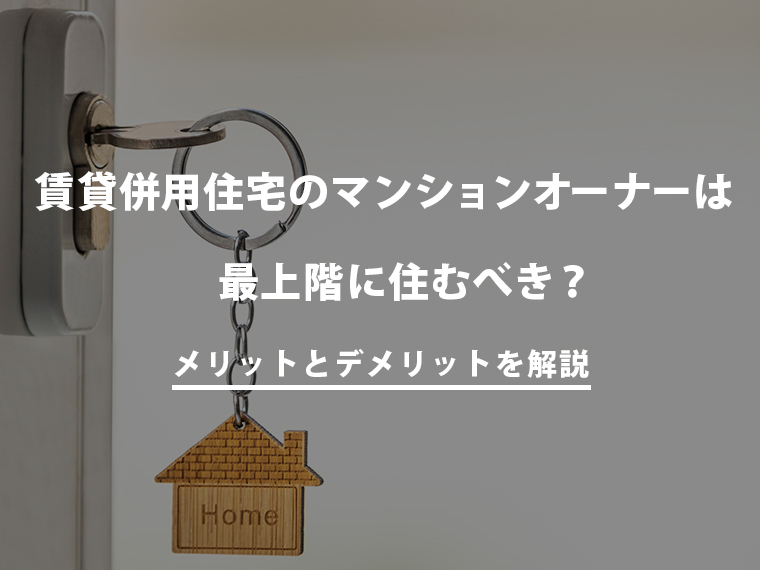- 相続財産の土地は、利用状況によって評価が異なる
- 土地、建物それぞれで評価減がある
- アパート建築は評価額が低くなるので、相続税が抑えられる
土地と建物の評価方法
相続財産は通常「時価」で評価されます。しかしその財産が土地である場合は、利用状況によって異なります。 そこで、まず押さえておきたいのが、土地、建物それぞれの評価方式についてです。まずはこの評価方式から順番に見ていきましょう。
土地の評価方法
土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
路線価方式
土地が面する道路(路線)に対して定められている1㎡あたりの価額(=路線価)を基に、土地の評価額が決まります。
土地評価額
=路線価×道路に面する状況、形状による加減(補正値)×土地面積
路線価は毎年1月1日時点のものを国税庁が評価し、7月に発表します。通常、国土交通省発表の「公示価格」の80%程度になります。土地に極端な奥行きがあったり角地であったりする場合は補正値で加減され、評価額が変わります。
倍率方式
市役所などで算定している固定資産税評価額に、各地域で定められている倍率を乗じて価額が決まります。
土地評価額=固定資産税評価額×倍率
建物の評価方法
自宅などの建物は、固定資産税評価額と同じ価額となります。
建物評価額=固定資産税評価額
土地の評価減について

相続財産が土地である場合は、利用状況によって評価が異なります。何も使われていない土地よりも、家やアパートを立てた土地の方が評価は下がるという点で、節税につながりやすいと言えるでしょう。ここでは、アパートが建っている土地の評価額の減額措置についてご説明します。
小規模宅地等の減額の特例
アパートが建っている土地は、特例で200㎡までを評価額の50%に減額することができます。
例1)土地200㎡、価額4,000万円の土地の場合
4,000万円×50%=2,000万円の減額
例2)土地400㎡、価額5,000万円の土地の場合
5,000万円×200㎡/400㎡×50%=1,250万円の減額
貸家建付地の評価
賃貸アパートを建てると、土地は「賃家建付地(かしやたてつけち)」となります。この土地は入居者がいることによって利用に制限がかかるため、評価額が下がります。計算式は次の通りです。
賃家建付地の評価額=自用地の評価額(※1)×(1-借地権割合(※2)
×借家権割合(※3))
※1 自用地の評価額は路線価によって計算します。通常、国土交通省発表の「公示価格」の80%程度
※2 借地権割合は土地により異なります(30~90%)
※3 借家権割合は全国共通で30%
例)価額1億円の土地、借地権割合60%の場合
自用地の評価額=1億円×80%=8,000万円
60%(借地権割合)×30%(借家権割合)=18%
8,000万円×18%=1,440万円
8,000万円-1,440万円=6,560万円
建物の評価減について
土地とは別に、建物もまた評価され、相続税が課されます。その際、建物は、固定資産税評価額(取得価格の60%程度、建物により異なる)で評価します。アパートの場合は、その評価額から借家権割合(全国一律で30%)を減額した金額になるため、土地とはまた異なる評価減があるということになります。計算式は次の通りです。
「建物の評価額=建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合)」
例)1億円のアパートの場合
1億円×60%=6,000万円
6,000万円×(1-30%)=4,200万円
遊休地にアパートを建てた場合のシミュレーション
では、実際に遊休地にアパートを建てた場合をシミュレーションしてみましょう。
例)自用地(※)価額1億円、借地権割合70%、借家権割合30%の土地、建設費1億円
<アパートを建てる前の資産>
自用地1億円+現金1億円=2億円
※他人が使用する権利のない土地
アパートを借り入れ1億円で建てた場合
- 土地:
賃家建付地の評価額
=1億円×(1-70%×30%)
=7,900万円 - 建物:
固定 資産税評価額
=1億円×60%
=6,000万円
アパートの評価額
=6,000万円×(1-30%)
=4,200万円 - 建築費:
1億円(全額ローン)
建築後の資産
=7,900万(土地)+4,200万円(建物)-1億円(当初の借入元本)+1億円(現金はそのまま)
=1億2,100万円
アパートを現金1億円で建てた場合
建築後の資産
=7,900万(土地)+4,200万円(建物)+0円(現金を建物に使ったため)
=1億2,100万円
ローンを利用した場合も現金で支払った場合も変わりません。年齢や資産状況によって検討しましょう。
マンションではなく、アパート建築である理由
節税のほかにも、アパート建築にはメリットがあります。たとえば大家として経営がうまくいけば、安定した家賃収入を得ることができます。同様に家賃収入を得られるマンションは、交通の便などの立地が求められるケースが多いです。そのため街中での需要が高く、建築エリアが限られます。
一方でアパートの場合は、閑静な住宅街を希望する場合も多く、郊外でも建てやすいことが選ばれる理由のひとつです。また、アパートはマンションより低層階であるため、コストの高い鉄筋コンクリートではなく、木造や軽量の鉄骨で建てることで、コストを抑えられるメリットもあります。
アパート建築を賢く利用して相続税対策を
アパート建築には、土地と建物それぞれで評価減があるため、相続税の対策として有効です。ただし賃貸アパートを建てるということは、不動産運用をスタートさせることを意味します。それらのリスクも踏まえたうえで、上手に節税へつなげていきましょう。
相続税対策のためのアパート建築をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。アパートも自宅併用アパートなどになると、条件が変わってきます。詳しい条件をお聞きになりたい方も、ぜひご相談ください。
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方