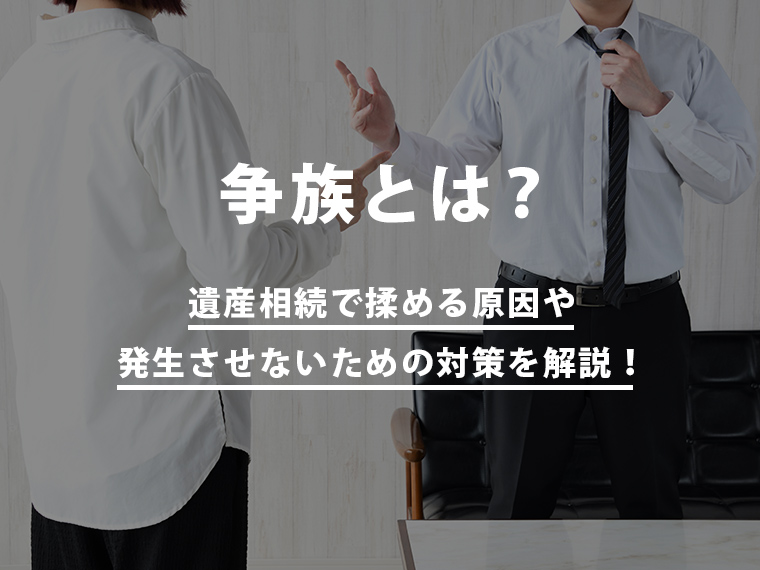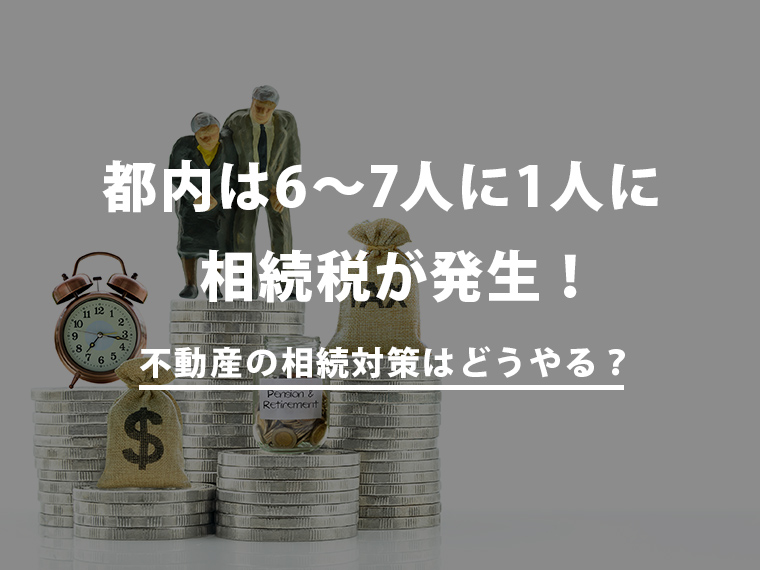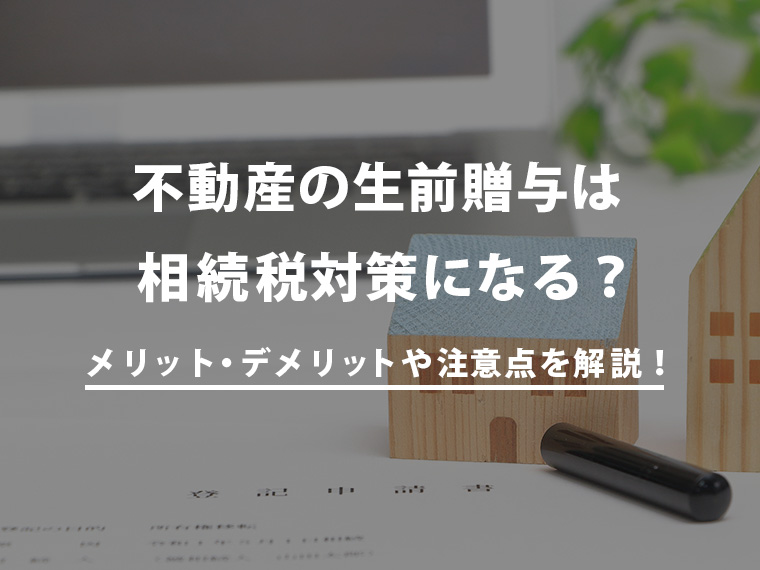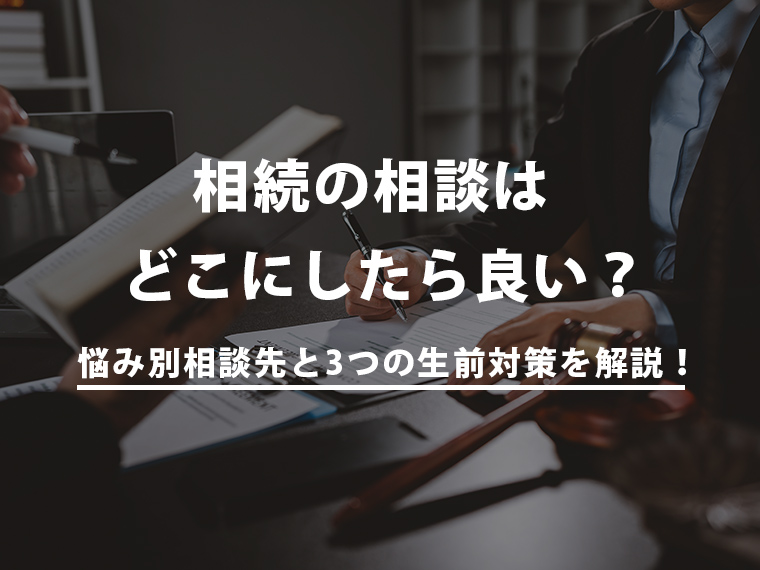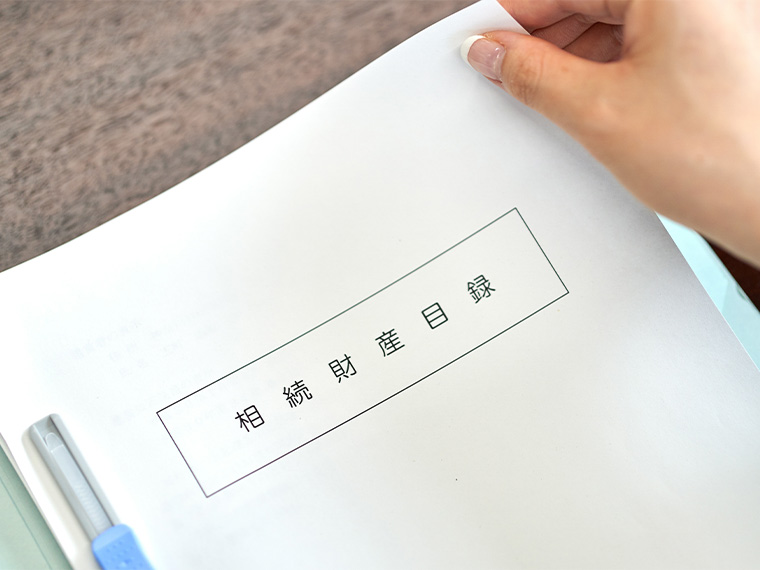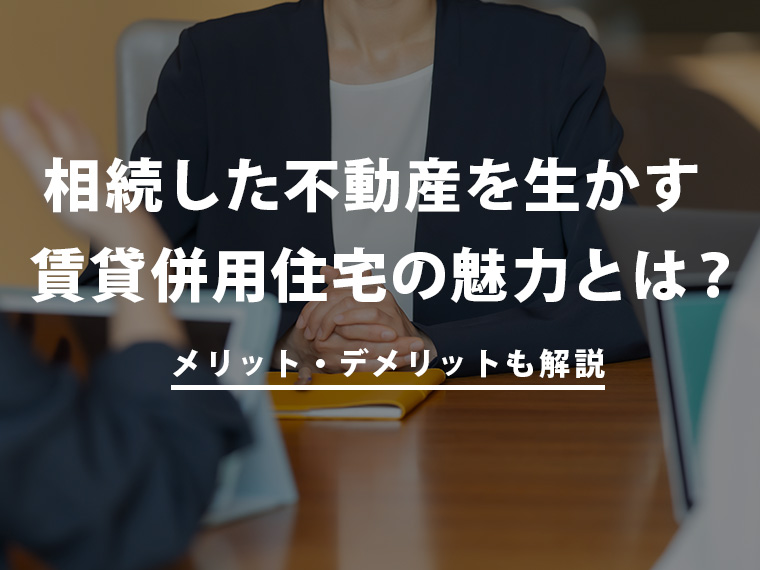- 争族とは、主に遺産分割を巡って相続人同士が争うことを指す
- 争族は、遺産が分割しにくい状況が備わっていると生じる可能性がある
- 争族を回避するには、遺言書を残すなどの対策が効果的である
いわゆる争族とは?
「争族」とは、主に遺産分割を巡って相続人同士が争ってしまうことを指す造語です。
相続人には、法定相続割合が定められており、法定相続割合だけ遺産をもらう権利を主張できます。
たとえば、相続人が子2人だけであれば、法定相続割合は50%ずつです。 しかしながら、実際には50%ずつ均等に分けられないことが多く、一方に遺産が偏ってしまうことから、争族が発生することがあります。
争族が生じる原因
争族が生じる原因としては、以下のようなものが挙げられます。
【争族が生じる原因】
- 遺産の過半を不動産が占めている
- 離婚した配偶者との間に子がいる
- 生前贈与された金額が相続人によって違う
- 相続人の配偶者が口出ししてくる
- 遺言書の有効性に疑念がある(認知症が発生した後に作成されているなど)
とくに「遺産の過半を不動産が占めている」点は、争族を生じさせる主たる原因となります。
不動産は現金とは異なり1円単位で分けることができないため、平等に分けにくい財産です。 遺産の過半を不動産が占めているケースは、資産家に限らず多くの被相続人に該当します。 そのため、争族はほとんどの人に起こりうる問題であり、対策しておく必要があるのです。
争族を回避するための対策
この章では、争族を回避するための対策について解説します。
生前に推定相続人と話し合っておく
争族を回避する対策としては、生前に推定相続人(相続が開始した際に遺産を相続するべき人のこと)と相続に関してよく話し合っておくことが基本です。 まず、相続税が発生する可能性があるか否かをはっきりさせ、相続税が発生する可能性がある場合には、対策や分け方について自分の考え方を伝えておきます。
しかし、親が「相続税対策してある」と伝えておいたとしても、1円でも相続税が発生すると、残された相続人の中には「なんだ、相続税対策してなかったじゃないか」といい出す子もいます。 親は相続税を十分に圧縮したため、相続税対策は行ったと考えていたとはいえ、子は相続税対策したら相続税はゼロ円になっていると勘違いしているケースも多いです。
親と子では、一般的に相続税に関する知識に大きな差があります。
とくに相続税が発生する人であれば、いくら発生する可能性があることを伝えておくことは必須です。
また、相続税は現金納付が原則となるため、子に相続税を支払える現金がなければ、不動産を売却して納税せざるを得ません。 納税資金を残せず、売却が必要な場合には、その旨も事前に伝えておくことが必要となります。
さらに、遺産分割案も子に提示しておき、どのような財産があり、誰が何を引き継ぐ予定であるかの理解を促しておくことが望ましいといえます。
遺言書を残す
争族は遺産分割で揉めることがほとんどであるため、遺言書を残しておくことが最も効果的な対策となります。 遺言とは、被相続人の生前の最終意思を尊重し、その意思の実現を死後に図る制度のことです。
遺言書があれば、原則として遺言書に従って遺産を分割することになりますので、遺産分割で揉めずに済みます。 離婚した配偶者との間に子がいるなど、遺産分割で揉める可能性が高い場合には、ぜひ遺言書を残しておくことをおすすめします。
ただし、遺言書を残したとしても、相続人同士が遺産分割協議(相続後に相続人同士で遺産の分割に関して取り決めを行う話し合い)を成立させれば、遺言書とは異なる方法で遺産を分割することは可能です。 遺産分割協議によって合意した内容は、遺産分割協議書(遺言書と同様に、相続を原因とした名義変更の際に必要となる正式な書類)と呼ばれる書面に記載されます。
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の同意が必要です。 相続人の中で1人でも反対者がいれば、遺産分割協議は成立しないことになります。 逆にいえば、遺産分割協議が成立するということは、1人も反対者がおらず、揉めていないということです。
また、遺言書を残しても、揉めなければ相続人が自分たちで遺産分割協議を行って遺言書とは異なる方法で分割ができますし、仮に揉めたら遺言書で分割することもできます。
もし遺言書がない状態で揉めてしまえば遺産分割協議が成立しないため、長年、揉めた状態のままとなる懸念が出てきます。 そのため、遺言書は遺産分割で争いを生じさせないための強力な役割を果たす書面であり、争族対策としては極力作成しておいた方が良いのです。
争族を生まない根本的な3つの対策

争族を生まないためには、遺言書を残すだけでなく、根本的な相続対策を行っておくことが大切です。 この章では、資産家などの相続税が発生する可能性がある人向けに、根本的な対策について解説します。
節税対策を実施する
相続税が発生する可能性がある場合、実施しておきたいのが節税対策です。
節税対策とは、言葉の通り、相続税そのものを減らす対策のことを指します。
代表的な節税対策としては、土地活用でアパートやマンション経営などの、不動産投資が挙げられます。 アパートなどの収益物件は、相続税評価額が時価よりも大幅に下がることから、同じ資産(時価)の額を現金で持つよりも、収益物件で保有した方が相続税対策になります。 また、土地活用や不動産投資で借入金を組めば、その借入金はマイナスの財産となるため、あえて残すことで相続財産を減らす効果があります。
納税対策を実施する
納税対策とは、相続税を納税するための現金を準備(確保)する対策のことです。
相続税は現金納付が原則であるため、相続人に納税するための現金がない場合、相続した不動産を売却して納税せざるを得なくなります。
不動産を手放したくない場合には、納税用の現金を準備しておくことが必要です。
納税対策としては、相続財産の中に納税できるだけの現金を残しておくか、生前贈与などを利用して現金を子に移しておくなどの対策が挙げられます。
こちらの記事も読まれています
分割対策を実施する
分割対策とは、遺産を分割しやすくするための対策です。
遺言書を残すことは、まさに分割対策となります。
そのほかとして、遺産を分けやすい形にしておくことも分割対策です。 たとえば、相続人となる子が2人いる場合、アパートを1棟建てるのではなく、戸建て賃貸を2棟建てて分けやすくするといったことも分割対策となります。
まとめ
以上、争族について解説してきました。
争族とは、遺産を巡って相続人同士が争うことで、争族が生じる原因としては「遺産の大半を不動産が占めている」や「離婚した配偶者との間に子がいる」、「生前贈与された金額が相続人によって違う」などが挙げられます。
争族を回避するための対策としては、遺言書を残すことが最も確実な方法です。
争族を生まない根本的な対策としては、節税対策と納税対策、分割対策の3つが挙げられます。争族を回避するために、本記事を参考にして頂けると幸いです。
相続対策にお悩みの方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

不動産鑑定士
竹内 英二
不動産鑑定事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
土地活用と賃貸借の分野が得意。賃貸に関しては、貸主や借主からの相談を多く受けている。
⇒竹内 英二さんの記事一覧はこちら
あわせて読みたい
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方