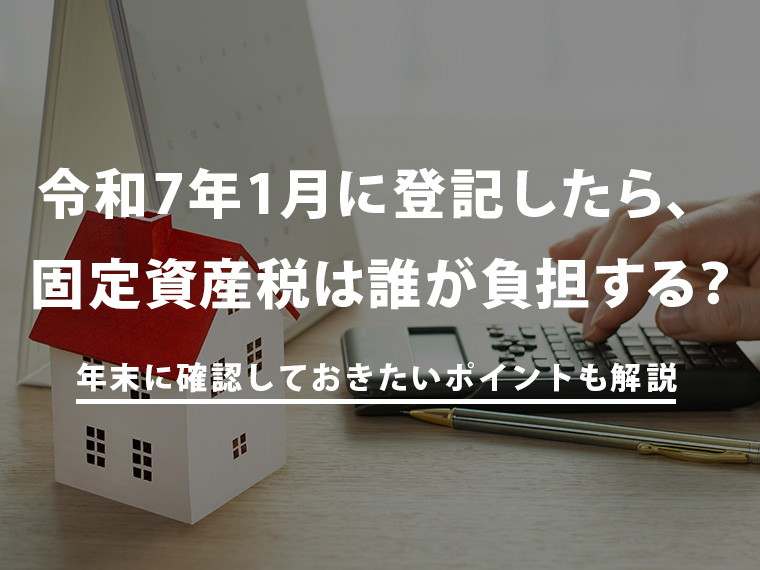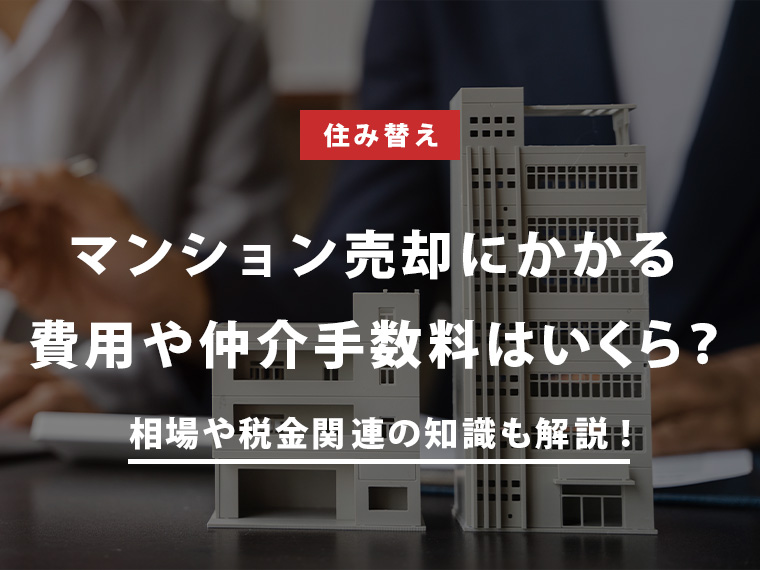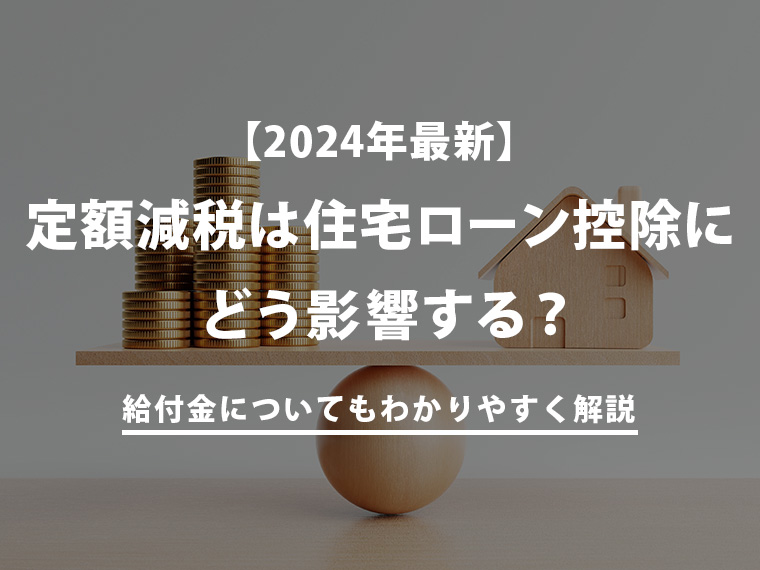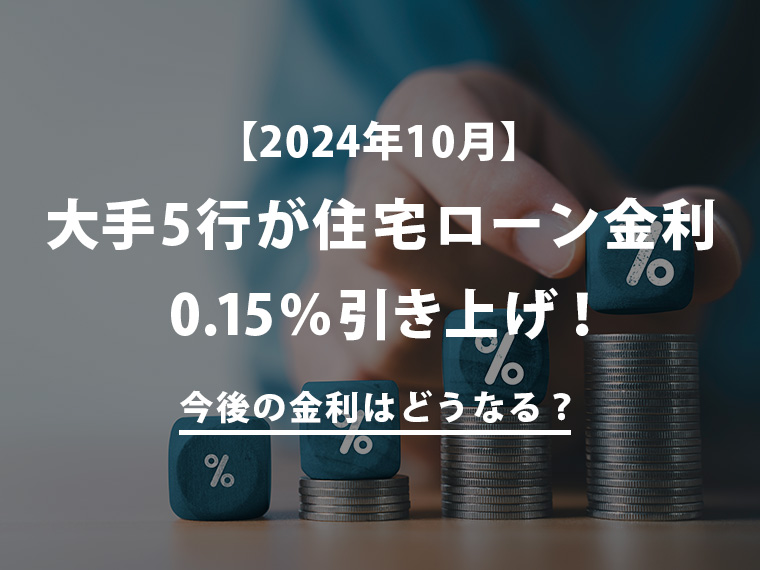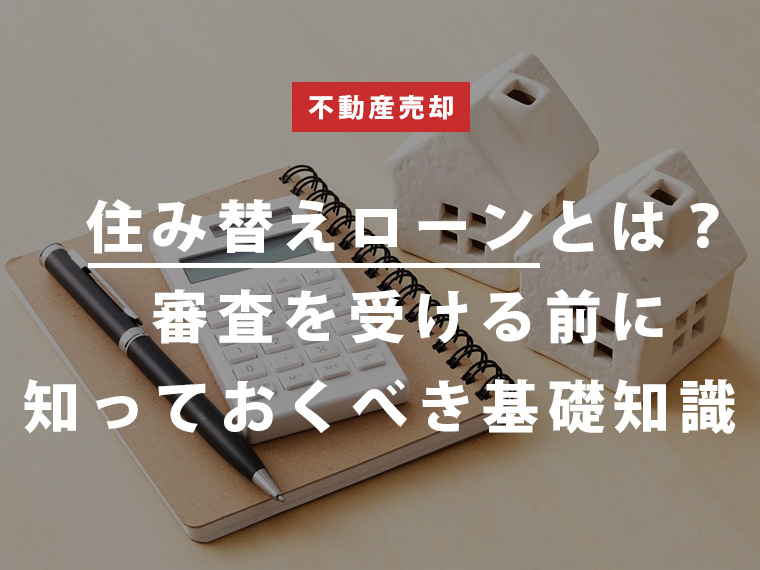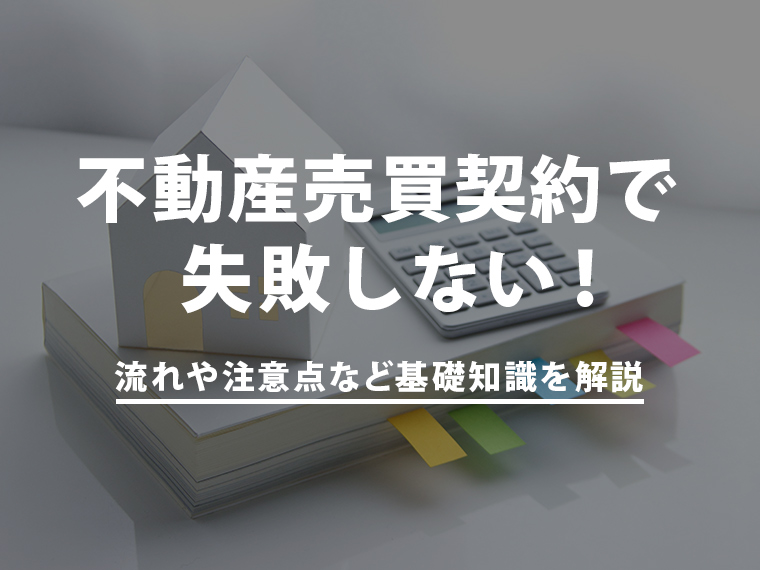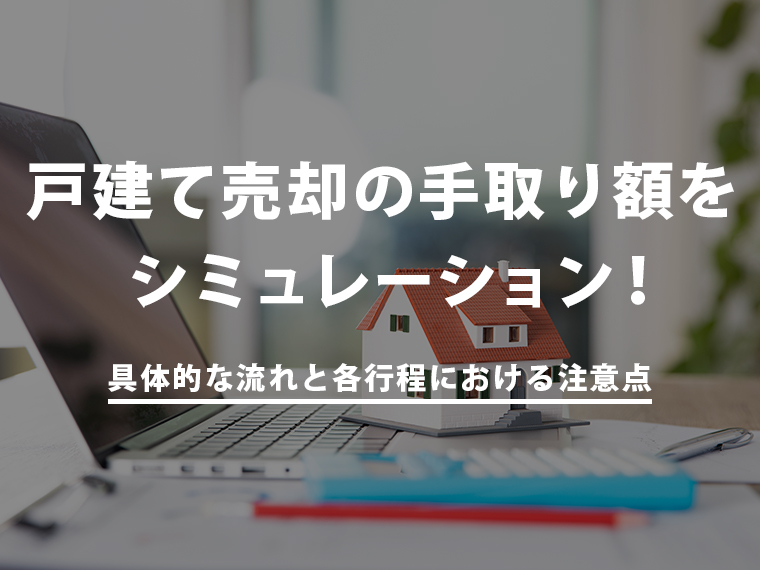- 固定資産税の納税義務者は、その年の時点での所有者である
- 固定資産税は、所有権移転日を基準にして、売主と買主で分担するのが一般的
- 固定資産税の分担金は、売主と買主の合意で定められるため、事前の確認が重要
固定資産税は1月1日時点の所有者に対して課税される
固定資産税は、1月1日時点での所有者に課税されると法律で定められています。 例えば、令和7年1月2日に所有権移転登記が行われた場合、令和7年分の固定資産税は元の所有者が支払う必要があります。
なお、所有者が誰であるかについては、法律で以下のように定められています。
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をいう。
引用:e-gov 法令検索 「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第三百四十三条」
令和6年中に売買契約を結び令和7年に所有権移転した場合の納税義務者は?
不動産の売買契約は通常、2週間~1ヶ月程度の期間がかかることが多いです。
ここでは、令和6年中に売買契約を結び、令和7年に決済と所有権移転が行われた場合の納税義務者について解説します。
売主が納税義務者となる
令和6年中に売買契約を結び、所有権移転が令和7年に行われた場合、1月1日時点の所有者は登記上売主となり、固定資産税の納税義務は売主にあります。 これは、税法によってその年の1月1日に不動産を所有している者に課税されるためです。
そのため、売主は令和7年に実際には不動産を所有していなくても、固定資産税の納付書が送られてくることに注意が必要です。
所有権移転日を境に、固定資産税を日割り計算するのが一般的
不動産の売買契約では、所有権移転日を境に固定資産税を日割り計算するのが一般的です。
例えば、令和7年4月1日に所有権移転登記した場合、売主は1月1日~3月31日までの固定資産税を負担し、買主は4月1日~12月31日までの固定資産税を負担することになります。
このように、売主と買主の間で日割り分の固定資産税が分担され、買主から売主に支払う税金の日割り分は「固定資産税分担金」として処理されます。
固定資産税が確定していない場合の手順
固定資産税の納付書が届くのは、自治体により若干の違いはありますが、概ね4月~5月頃です。 そのため、所有権移転登記を1~3月にすると、その年の正確な固定資産税納付額が確定せず、差額が発生する可能性があります。
このような場合、売買契約において「差額が発生した場合には、固定資産税の納付額が確定した段階で差額を清算する」という取り決めを行うことが一般的です。
【固定資産税が確定していない場合の手順の例】
- 令和7年1月に決済した場合、買主が前年の固定資産税納付額を参考にして分担金を売主に支払う
- 令和7年4月に固定資産税が確定し、1万円不足していたことが判明
- 買主が不足分の1万円を売主に支払う
このような手順で進められることが多いですが、固定資産税分担金については法律で定められているわけではなく、商取引における慣習として行われています。 売主と買主の合意に基づくものであり、差額が少額であれば、清算しないこともあります。
そのため、所有権移転登記を行う前に、固定資産税分担金について差額が生じた場合にどう対応するかを、事前に相手方としっかり打ち合わせておくことが大切です。
新築物件の登記と固定資産税に関する判例
中古物件の固定資産税については、基本的に登記の有無により納税者が決められます。 新築物件についても、原則としては中古物件と同様ですが、固定資産税分担金を支払う必要がないことから、例えば「12月に建物が完成したが、1月以降に登記を完了させることで固定資産税を回避する」といったことが可能となってしまいます。
こうした背景もあり、過去に最高裁で新築物件の登記と固定資産税に関する問題が争われています。
その結果、最高裁判所は、「土地または家屋について、賦課期日(1月1日)※に登記がされていなくても、賦課決定処分時までに登記があれば、登記された所有者がその年度の固定資産税を負担する必要がある」と判決しました。
※「賦課期日(ふかきじつ)」・・・税を課税する基準日
この判決により、賦課期日に登記が未完了であっても、賦課決定処分時に所有者として登記されていれば納税義務が発生することが確定しました。
年をまたぐ家の売買で損をすることはある?
最後に、年をまたぐ家の売買において、買主・売主の双方が損をすることがあるかについて、改めて確認していきましょう。
Q.【売主・買主】固定資産税は年をまたいでも基本的に損はしない
A.結論からいうと、固定資産税に関しては、売買契約を令和6年、所有権移転登記が令和7年になったとしても、基本的に損をすることはありません。 納税義務者は1月1日時点の所有者である売主ですが、決済日を境に日割り計算して、買主から売主へ固定資産税分担金が支払われるのが一般的だからです。
ただし、固定資産税分担金は法律で定められているものではなく、売主と買主の合意によって決まります。 そのため、売買契約を結ぶ前に、この分担金の取り決めをしっかり確認しておくことが重要です。
Q.【買主】住宅ローン控除は年をまたぐと損をする
A.不動産の買主が年をまたいで所有権移転登記を行う際、特に注意すべきなのが「住宅ローン控除」です。 住宅ローン控除は、年末時点でのローン残高の0.7%が控除される制度です。
住宅ローン控除の適用額は、住宅ローンの年末残高のため、例えば令和6年12月中に所有権移転登記するのと、令和7年1月に所有権移転登記するのとでは、控除額に違いが出てしまいます。
仮に、住宅ローンを組んで毎月10万円返済する場合(10万円×12ヵ月=120万円分)で見てみましょう。
【令和6年12月に3,000万円の住宅ローンを組んで所有権移転登記した場合】
住宅ローン控除額:3,000万円(令和6年の住宅ローン年末残高)✕0.7%=21万円
【令和7年1月に3,000万円の住宅ローンを組み所有権移転登記した場合】
住宅ローン控除額:2,880万円(令和7年の住宅ローン年末残高)✕0.7%=20.16万円
結果として、21万円-20.16万円=0.84万円、つまり【8,400円】損をしてしまう計算です。
そこまで大きな損というわけではありませんが、覚えておくとよいでしょう。
まとめ
ここまで、年をまたいで不動産登記を行う可能性がある方向けに、固定資産税の納税義務者や損をする可能性について解説しました。 固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されるため、たとえ令和6年に売買契約を結び、令和7年に所有権移転登記した場合でも、元の所有者である売主が令和7年分の固定資産税を納めなければなりません。 しかし、通常は、売主と買主の間で「固定資産税分担金」を設定し、売主から買主へ日割り分の金額が支払われることで、損をすることはありません。
なお、この「固定資産税分担金」は法律に基づいた義務ではなく、商取引における慣習にすぎません。 そのため、売主と買主の合意に基づいて取り決めを行う必要があります。 年をまたぐ不動産売買を行う場合は、損失を避けるために、売主と買主の間でしっかりと事前に取り決めをしておきましょう。
不動産売買の際には、税金や費用の分担について疑問があれば専門家に相談することをおすすめします。
不動産売却や査定についてのお問合せは、下記よりお気軽にお問合せ下さい。
あなたの不動産、今いくらで売れる?
無料売却査定
種別を選択してください
STEP1物件種別
種別を選択してください
エリアを選択してください
STEP2査定物件住所
エリアを選択してください
大変申し訳ございません。
対応エリア外のため査定できません。
訪問査定完了で
Amazonギフト10,000円分プレゼント!
訪問査定完了で
Amazonギフト1万円分!
※クラモア対応エリア外の場合、NTTデータグループ運営の「HOME4U(ホームフォーユー)」で、一括査定サービスがご利用できます。
※訪問査定キャンペーンの詳細はこちら

宅建士・2級FP技能士(AFP)・相続管理士
逆瀬川 勇造
大学卒業後、地元の地方銀行に入行し、窓口業務・渉外業務の経験を経て、2011年9月より不動産会社に入社。不動産会社では住宅新築や土地仕入れ、造成、不動産売買に携わる。2018年より独立し、2020年合同会社7pocketsを設立。
金融や不動産分野におけるコンテンツにおいて、現場での経験を活かし、読者の方が悩みやすいポイントを分かりやすく解説することを心がけている。
⇒逆瀬川 勇造さんの記事一覧はこちら
あわせて読みたい
この記事をシェアする
お部屋を探す
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
売りたい
訪問査定完了で
Amazonギフト1万円!
土地活用・相続の相談がしたい
売るか貸すかお悩みの方はこちら
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
売りたい
訪問査定完了で
Amazonギフト1万円!
土地活用・相続の相談がしたい
売るか貸すかお悩みの方はこちら