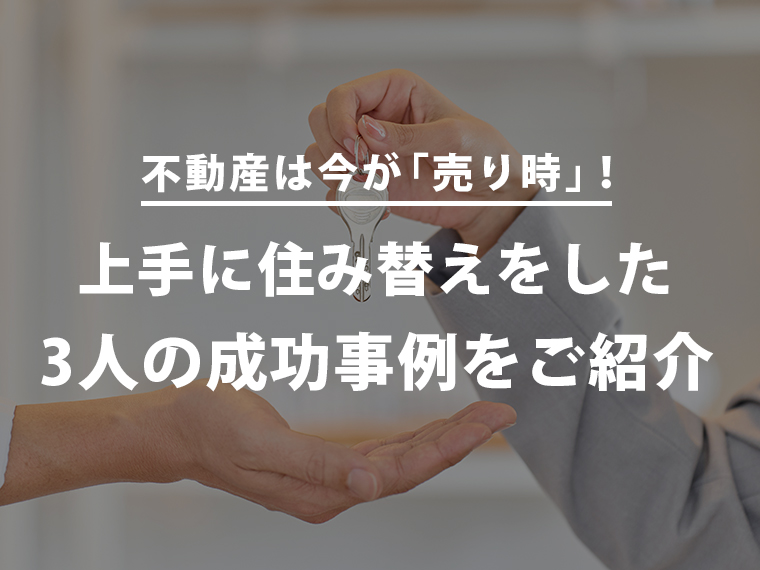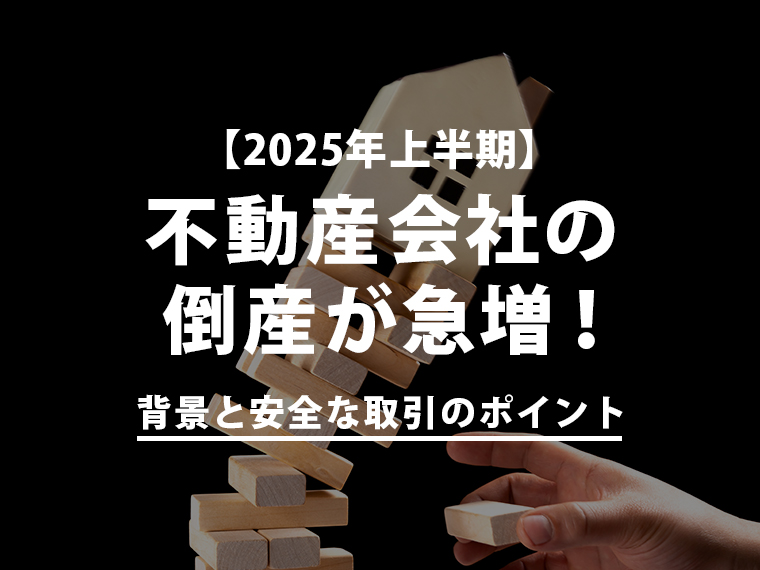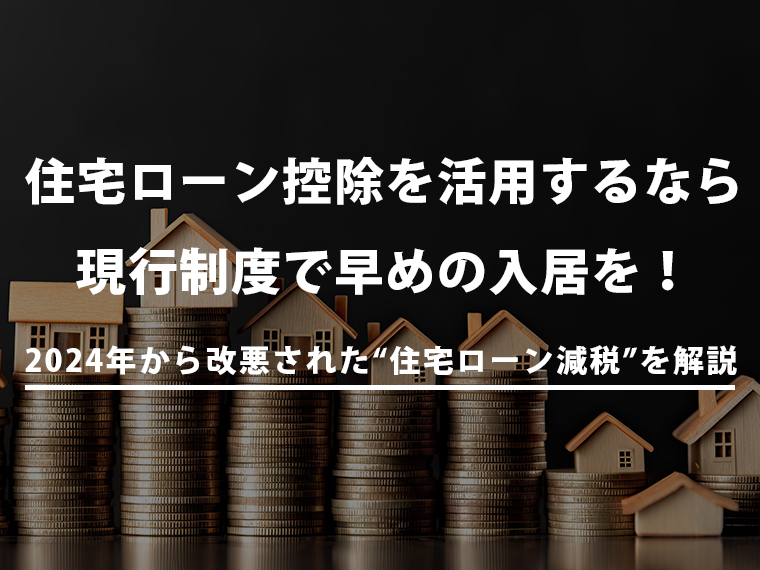- 「バリアフリー」を正しく理解し、誰もが安心して生活できる環境に整えよう
- 住宅や建物だけでなく「心のバリアフリー」も意識しよう
- 普段生活している家にもバリアフリーを取り入れて転倒や事故のリスクを減らし、豊かなセカンドライフを送ろう
お問い合わせページに移動します
「バリアフリー」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。普段生活のなかで意外と身近にあるバリアフリーは、公共機関や住宅にも取り入れられています。
日本では2007年に超高齢社会に突入しました。これからさらに高齢化が加速するなかで、バリアフリーはより一層重要性が高まってくると考えられます。しかし、まだまだバリアフリーが取り入れられていない公共機関や住宅は少なくありません。
現状は生活するうえで不便を感じていない場合でも、いざ自分や家族、親戚などがバリアフリーを必要とするケースを考えて備えておくことは重要です。
あらためてバリアフリーの意味と目的について理解を深めよう
「バリアフリー」が持つ言葉の意味をご存知でしょうか。もしかすると、世の中で定められているバリアフリーと個々が持つイメージが異なっているかもしれません。
バリアフリーの意味とは?
バリアフリーの「バリア」とは英語で「障壁」を示し、バリアフリーとはさまざまな人が社会に参加するうえでの「障壁をなくすこと」を意味します。
生活するなかで不便に思うことや、活動の際に障壁になっているバリアをなくすこと(フリーにすること)は、障がいの有無にかかわらず、誰もが安心して自由に生活を送るために不可欠と言えます。
バリアフリーとユニバーサルデザインの違い
バリアフリーと一緒に用いられることが多い「ユニバーサルデザイン」という言葉を耳にすることも多いかもしれません。バリアフリーの社会に参加するうえで「障壁をなくすこと」という考え方に対して、ユニバーサルデザインとは、障がいの有無や度合いにかかわらず「誰でも自由に、できるだけ多くの方が使いやすい都市や生活環境をデザインする」という考え方です。
つまり、性別や年齢、国籍などに関係なく一人ひとりが利用しやすいように考えられており、一時的に怪我をしている方や子育て中のベビーカーを利用している方なども対象になります。
誰もが使いやすいという視点で世の中をデザインしていくことは、今後より一層求められる考え方でしょう。そういった意味では、バリアフリーはユニバーサルデザインの一部と言えるかもしれません。
バリアフリー新法の概要について
バリアフリーについて政府が法律を定めたことによって、公共交通機関や住宅でバリアフリー化が進んできました。それだけでなく国民がバリアフリーへの認識を高めて、実行や改善を測ってきた結果が出てきています。しかし、バリアフリー新法がどのような法律なのかは知らない方も多いのではないでしょうか。
バリアフリー新法とは?
総合的なバリアフリー化を推進するために、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が策定されました。これがバリアフリー新法であり2006年に成立、施行されています。
ひと昔に比べると建築物や交通機関などでは着実にバリアフリー化が図られてきました。しかし、施設ごとや部分的にバリアフリー化が進められたことで「連続的なバリアフリー化が図られていない」などの課題がありました。そこでバリアフリー新法が施行され、広範囲のエリアが対象となったのです。
高齢者や障がい者が、公共交通機関を移動する際に使うことを想定して、電車や駅、歩道、施設のなかに至るまで、不便を感じる場所をなくすように進められてきました。実際に計画段階から高齢者や障がい者に意見を求めて反映させた点が、この法律の最大のポイントと言えます。
今までのバリアフリーの法律と何が変わったの?
バリアフリー新法によって変わった点としては、「バリアフリーの基準が詳細に設定されるようになったこと」です。
具体的には、利用者が5,000人以上の駅やターミナルなどのバリアフリー化を100%にすることが義務付けられています。また、従来対象となっていた公共交通機関や建築物に加えて、路外駐車場や都市公園にもバリアフリー化の基準に対する適合が求められるようになりました。そうすることでより円滑に移動できるように図られています。
バリアフリー新法には、主に二つの基準が設けられています。一つ目は「建築物移動等円滑化基準」です。建築物に対するバリアフリーの基準として、不特定かつ多数の人が利用する百貨店や劇場、ホテルなど、高齢者、障がい者が利用する老人ホームなども対象になっています。
他にも、建築工事をする床面積の合計が2,000㎡の新築物に適合させる必要があると定めています。最低限として、車いす利用者と人がすれ違う廊下の幅の確保、車いすの方でも利用できるトイレを一つは設けること、目の不自由な方でも利用しやすいエレベーターなどを設置することも含まれています。
二つ目に「建築物移動等円滑化誘導基準」はできるだけ適合させる努力をするべきと定めています。具体的には、出入り口や廊下、エレベーターやトイレなどの設備に関して、「最低限どのくらいの幅か」「数はいくつなのか」などを確認するチェックシートが用いられており、「出入口の幅などは80cm以上確保すること」といった内容が細かく定められています。
建築物移動等円滑化誘導基準を満たす場合は、所管行政庁による計画の認定を受けてさまざまな支援措置を受けることが可能です。具体的には「表示制度」「容積率の特例」「税制上の特例」「補助制度」などの支援措置があります。
しかし、規模の大きな駅などでは以前より国内でのバリアフリー化が進んだのは確かですが、行き届いていない箇所や利用者の視点で考えると課題は多く残っています。これまで取り組んできた施策と合わせて、さらなる改善をしていくことが求められているのです。
また、社会や住宅でのバリアフリー化の促進を図るには、私たちが高齢者、障がい者などの自立した日常生活および社会生活を確保することについて理解を深めることが重要になります。
街中に溢れるバリアフリーを知ろう
バリアフリーは、普段使っている道路や公園などの場所でもたくさん見かけることができます。たとえば、車いすでも利用しやすいエレベーター、多目的トイレ、視覚障害の方のための誘導ブロック、音声ガイドシステム、誘導鈴スピーカーを設置している場所などが多くあります。
人によって不便に思うところはさまざま!「心のバリアフリー」の重要性
バリアフリー新法にも組み込まれた「心のバリアフリー」という考え方も重要視されています。「心のバリアフリー」とはバリアを感じている人の身になって考え、行動に移すことです。
バリアフリー新法により、国が国民に対して「心のバリアフリー」の理解や協力を求め、責務としていることもあり、国全体で促進を図っていることがうかがえます。
心のバリアフリーは公共施設や住宅の内外はもちろんのこと、場所に限らず「一人ひとりが多様な相手を思いやること」が重要になります。そうは言っても、日常生活においてどのような場面で行動すればいいのか、戸惑う方もいるかもしれません。まずは、困っていそうな方に声をかけて「〇〇しましょうか?」と聞いてみることが大切です。
街中でよくある事例
・車いすの方が店の出入り口の段差を乗り越えられずに困っているとき
・電車のなかで杖をもった高齢者が近くに立っているとき
・電車のなかで妊婦さんが目の前に立っているとき
・ベビーカーを押している方が階段で大変そうにしているとき
こういった方を見かけたときに、自分だったらどのような行動をするでしょうか。自然に行動にうつせる方もいれば、知らない方に声をかけることに躊躇して見て見ぬふりをしてしまう方もいるかもしれせん。
なるべく人に頼らず自分でやりたいと思っている方もいるので、もしかすると断られることもあるかもしれません。そういった場合でも、バリアを感じている方の身になって相手の気持ちを「尊重」しましょう。
一人ひとりの意識上の「バリアフリー」を実践することが、バリアのない社会をつくっていくために重要です。普段生活しているなかで、周りの人などを少し意識して見てみましょう。
困っていそうな方にひと言「聞いてみる」こと、目の前にいる方に今してあげられることは何かを考えることは、誰かのバリアを取り除くことにつながるかもしれません。自分とは異なる生活をしている相手でも、同じ社会で活動していることをお互いに認識し合う意識が大切です。
お問い合わせページに移動します
住宅にバリアフリーを取り入れるメリットは?

住宅には段差や階段、風呂場などさまざまな場所に危険が潜んでいます。若いときにはなんともなかった場所が、歳を重ねていくことで転倒の原因になる可能性があります。最悪の場合、死亡事故につながることもあるのです。
外出する際は、段差に気を付けたり注意して周りを見たりしている方も多いですが、普段生活している場所では注意力が低下してしまいがちです。
転びそうになったらとっさに手が前に出たり、受け身を取れていたりした若いときの感覚のままでいると、それが過信につながって事故を招く可能性があります。筋力やバランス機能などの身体能力は、徐々に低下していくので本人も気づかない場合が多いのです。
そうならないために、最も長い時間過ごす場所である住宅で、バリアフリー対策をして転倒や事故を防止することが大切です。
「万が一」が起きてしまったときの対策まで考えておくことが大事!
高齢者の介護が必要になる要因として、「認知症」「脳血管疾患」「高齢による衰弱」の次に「骨折・転倒」が多いことをご存知でしょうか。
高齢者の転倒・転落は骨折や頭部外傷を招くケースもあり、それが原因で介護が必要な状態になってしまうことがあります。そのようなリスクを抑えるには、転倒や事故を防止するために本人や家族、親戚などの身近にいる方が一緒に対策していくのが望ましいでしょう。
転倒や事故を防止・軽減するには、とくに次の3つを確認しておきましょう。
①危険な場所はないかあらためてチェックする
一つ目は、住宅や普段利用している場所で段差や転倒の危険があるところはないか、あらためて意識して確認することです。
事故の多くはリビング、階段、玄関、風呂場など毎日利用する場所で起きています。ドアや和室とリビングをつなげている戸の敷居など、床のほんの少しの段差でも転倒する恐れがあります。また視力も衰えてくるため、段差や階段がある場所には明るい照明を設置することも防止策の一つです。
もし危険な場所があった場合、床をフラットにするバリアフリーにしたり、暗い場所には照明を取り付けたりしてリスクを減らすことを意識してみましょう。
②身体能力の低下と向き合い、服用中の薬もチェックする
二つ目は、加齢による身体機能の低下や、薬の副作用による転倒の可能性があることを把握しておくことです。
歳を重ねていくと持病などが増えてくるのと同時に、服用している薬も複数になりがちです。なかには副作用によりふらつきや立ちくらみが起こりやすいものも。副作用が不安な場合は薬を変更したり、薬の量を減らせないか主治医に相談したりするのも一つの手です。
また、「まだ衰えていないから」と、自分の身体機能を過信することが事故につながる場合もあります。身体の状態を本人や周りが正しく認識、把握することも大切です。
必要に応じて手すりの設置や、転んでも怪我をしにくいクッション性のある床材に変更するなどの対策がおすすめです。
③もしものことを考えて事前に確認する
3つ目は、万が一転倒や事故が起きた際に、冷静に対処できるように準備しておくことです。まず、転倒の場合は慌てて起こそうとしたりせず意識があるかを確認し、痛みがある箇所に腫れや異常がないか確認しましょう。顔色や不自然な汗をかいていないかなども観察する必要があります。
転倒や転落によって見た目には問題がない場合でも、時間が経ってから異常が現れることもあります。数時間後に急に体調が悪化したり、数日後に症状が出たりする場合もあります。普段と変わったところがないか、会話をするときに変化がないかなどを注意深く観察し、少しでも気になる症状が出た場合は早めに受診しましょう。
年齢が上がると転倒リスクも比例する
年齢とともに身体能力は低下していきます。消費者庁のデータから救急搬送者を年代別に人口10万人あたりで見てみると、65~69歳の年代から年齢が上がるにつれて搬送者数が増加するとともに、危害の程度も重くなりやすい傾向があります。さらに75歳以上になると、事故の発生に加えて死亡者数も増加傾向に。年齢が上がるにつれて外出の機会が減ってくる一方で、家のなかで過ごす時間が増える分、自宅内の環境を整えることを意識しておくのが大切です。
家族みんなが快適に過ごすための配慮を
今回は、公共施設や住宅でのバリアフリーについてご紹介しました。「バリアフリーとは何か」を一人ひとりが理解して共通の認識を持てると、周りの方への配慮ができるようになります。家を建てるときやリフォームする際には、現状では必要なくても将来のために対策をすること、大切な家族のために配慮した家づくりを目指すことで長く快適に過ごすことができるはずです。
本当に必要になってからバリアフリー対策をするのは意外と大変なこと。年齢を重ねれば身体機能は低下していくため、年齢とともにバリアフリー化が必要になってくることはある程度予測できるかもしれません。しかし、何かの事故や病気で急に対策が必要になる可能性は誰にでもあります。家を建てるときや購入する際には、なるべく段差をつくらないようなデザインや将来的に手すりを設置できるように備えておくことで、セカンドライフも安心して過ごせる住宅を目指しましょう。
お問い合わせページに移動します
あわせて読みたい
よくある質問
-
お部屋探しに役立つ情報はありますか?
-
物件探し(不動産購入・売却)について役立つ情報はありますか?
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方