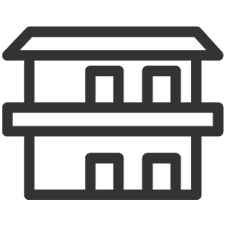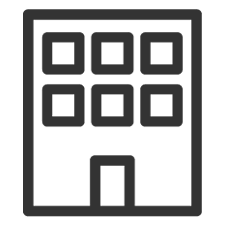- 扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある
- 収入(所得)を扶養範囲内におさめると、世帯の手取りを増やせる
- 扶養に入る方が得か否かは、6つある「●●円の壁」を基準に考える
そもそも、「扶養」って何?

まず理解しておきたいのが、「扶養家族」という言葉です。扶養家族とは、扶養者(いわゆる一家の大黒柱)の収入によって生活している人を指します。扶養家族は税金や社会保険料の支払いが免除され、扶養している本人も各種控除を受けられるため、世帯の税負担軽減につながる仕組みです。
「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つに分けられ、扶養家族の年間収入(所得)により扶養に入れるかどうかが決まります。扶養制度に合わせた働き方をすることで、世帯収入を効率よく増やすことも可能です。
近年では、結婚後も扶養に入らず働き続ける女性、あるいは夫が妻の扶養に入るケースも珍しくありません。しかしここでは、多数派である「妻が夫の扶養に入るケース」を前提に解説します。
妻が夫の扶養に入るメリット・デメリット

扶養制度にはメリットがある一方、デメリットも存在します。そのため、夫婦が互いの働き方やライフプランについて話し合い、理解したうえで扶養に入るかどうかを決めるのが望ましいでしょう。
妻が夫の扶養に入るメリット
扶養家族となる妻の収入が扶養範囲内におさまる場合、所得税を納める必要がない点が税法上のメリットです。加えて扶養者である夫は、配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を受けることができます。
社会保険上のメリットとしては、妻が将来的に国民年金を受け取れるという点が挙げられます。厚生年金に加入している配偶者に扶養されており、かつ収入合計が130万円未満である場合、妻は国民年金の「第3号被保険者」となり、年金保険料を納付していると見なされます。また、保険証も夫の勤務先から発行されるため、妻は3割負担で医療機関を受診できます。
このように、収入を扶養範囲内におさめることができれば、妻は税金や社会保険料を支払う必要がなくなります。また、配偶者控除(配偶者特別控除)により夫の税額を抑えることもでき、世帯全体の手取りを増やすことにつながるのです。
妻が夫の扶養に入るデメリット
一方、妻が夫の扶養に入ることがデメリットとなるケースもあります。税法上の扶養も社会保険上の扶養も、主に妻の収入(所得)金額に応じて決定されるため、妻は扶養の範囲を超えて収入を得ることができません。
妻が扶養の範囲を超えて働こうとした場合、収入が扶養範囲を少し上回る程度だと、かえって世帯収入が減ってしまうことが考えられます。なぜなら、妻自身の税金や社会保険料の負担が増え、夫も配偶者控除を受けられないからです。
また、扶養家族である妻は国民年金の第3号被保険者となるため、将来受け取れる年金は老齢基礎年金のみに限られます。付加年金や国民年金基金は利用できないため、扶養から外れて働く人に比べ、老後に受け取れる年金は少なくなるのです。
働き方を考えるうえで理解したい「●●万円の壁」

扶養制度について考えるとき、「103万円の壁」「130万円の壁」など、「●●の壁」という言葉を聞くことがあります。しかし、存在する「壁」はこれだけではありません。ここでは、よりよい働き方を見つける指針となるよう、6つの「●●万円の壁」についてわかりやすく解説します。
なお、文章内に「所得」と「収入」という言葉が出てきますが、所得と収入は異なる意味を持つ言葉なので注意が必要です。働いて得た給与は「収入」で、そこから必要経費を差し引いて残った額が「所得」となります。
100万円の壁
【妻の納税:不要、社会保険料納付:不要/夫の税控除:あり】
妻の年間収入額が100万円未満の場合は、所得税・住民税を納める必要がありません。
103万円の壁
【妻の納税:不要(住民税のみ)、社会保険料納付:不要/夫の税控除:あり】
妻の年間収入額が100万円以上、103万円以下の場合は、住民税を納める必要があります。ただし、所得税を納める必要はありません。
扶養制度において「103万円の壁」が注目されるのは、103万円が「配偶者控除」の基準となるためです。たとえば、妻の年間給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額(55万円)を差し引いた合計所得金額が48万円以下となることから、配偶者控除の対象となります。この場合、所得税および社会保険料の支払いは必要ありません。
また、扶養者である夫の住民税・所得税も控除により減額されるため、妻の収入がそのまま手取り収入として残ることになります。
なお、仮に100万円を少し超えてしまったとしても、住民税は数千円程度です(自治体によって異なります)。
106万円の壁・130万円の壁
【妻の納税:必要、社会保険料納付:不要/夫の税控除:あり】
従来、社会保険の加入基準は130万円以上でした。しかし2016年の法改正により、妻の年間収入額が社会保険加入の基準(106万円)を超える場合は、社会保険料を支払わなければならなくなりました。
106万円以上で社会保険加入となる条件は次の通りです。
平成28年10月から、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。
(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一(※)である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(※)「事業主が同一」である適用事業所とは
・法人事業所(株式会社、社団・財団法人、独立行政法人等)で、法人番号が同一の適用事業所
・個人事業所(人格なき社団等を含む)で、現在の適用事業所
(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
(※3)任意特定適用事業所とは
国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所
引用:日本年金機構 「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
150万円の壁
【妻の納税:必要、社会保険料納付:必要/夫の税控除:あり】
夫の所得が900万円(会社勤めなら給与収入1,095万円)以下、かつ妻の年収が150万円以下の場合、夫は配偶者特別控除を満額(38万円)受けることができます。このときの妻の年収上限が、「150万円の壁」です。夫の所得、妻の所得が上限を超えると、金額が増えていくにつれて控除額が段階的に減っていきます。
201万円の壁
【妻の納税:必要、社会保険料納付:必要/夫の税控除:なし】
妻の年収が201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられません。社会保険上の扶養はもちろん、税法上の扶養にも入れないことになります。
扶養に入るメリットとデメリットを理解しておこう
結婚して配偶者の扶養に入ることには、多くのメリットがあります。税金や社会保険料の支払いが免除されるだけでなく、扶養者も税控除を受けられるなど、条件が合えば「家計の助けになる制度」と言えるでしょう。しかしその一方で、将来受け取れる年金が減るなどデメリットもあります。扶養に入るか否かは、家族の状況や将来設計に合わせて選択することをおすすめします。
自分たちの将来設計にマッチした住まいを探したい、物件探しについて相談したいという方は、下記の窓口よりお気軽にお問い合わせください。
ピタットハウスのお問い合わせページに移動します
お問い合わせページに移動します
あわせて読みたい
よくある質問
-
お部屋探しに役立つ情報はありますか?
-
物件探し(不動産購入・売却)について役立つ情報はありますか?
この記事をシェアする
不動産を買いたい
特集から記事を探す
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の注意点とは?流れや費用、失敗例を把握しよう!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方
記事カテゴリ
おすすめ記事
-

「クラシアム神奈川台場」の魅力ポイントは?横浜・みなとみらい生活圏の理想的な新築賃貸マンションをご紹介
-

【2025年最新】港区(東京都)のマンション売却相場は?価格推移や高く売るためのコツを徹底解説
-

2025年版!品川区(東京都)のマンション売却相場と価格推移|高く売るためのポイントとは?
-

【2024年改正】使いやすくなった相続空き家の3,000万円特別控除とは?
-

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!
-

マンション売却の流れ10ステップとは?初心者さんにわかりやすく解説
-

2024年以降の不動産市況はどうなる?2023年の特徴と今後の動向を解説
-

【最新】2024年以降に住宅購入される方必見!住宅ローン控除の注意ポイント!
-

2024年住宅ローン金利は上昇するの?これから家を買う予定の人はどうすべき?
物件をご所有されている方、
お住まいをお探しの方